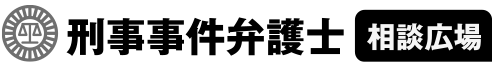取調べのルールや時間は決まっている?
- 2025年1月20日
- 148,964 view
- 10分でわかる刑事手続き
- 刑事事件弁護士相談広場

取調べのルール~現在の取調室事情~
冤罪事件を取り扱ったドキュメンタリー番組や書籍では、無実の罪を着せられた人が、「昼夜を分かたず、長時間にわたって取調べを受けた」と証言している場面を目にすることがあります。
また刑事ドラマや映画でも、薄暗く狭い取調室の真ん中に小さい机が置かれ、電気スタンドがひとつあり、容疑者を厳しく詰問するシーンがまだ出てくることがあり、実際の警察での取調べは、このように厳しいものだと理解している人が多いでしょう。実際に、昭和時代の取調べは被疑者を休ませず、長時間にわたり取調室にカンヅメにして、追い込むだけ追い込んで自白を迫る方法が普通に行われていました。
その結果、犯してもいない罪が問われる冤罪が多発し、取調室での暴力も問題視され始め、拷問と同じような手法で取調べを行うことに社会的な批判が高まりました。被疑者の人権を守ろうという動きも強くなり、過去の事件捜査における自白の信用性を裁判所が疑問視し始めたこともあり、当時行われていた多くの取調べの方法が禁じ手となっているのです。
では、現在の取調べがどのように行われているのかを紹介しましょう。
取り調べは1日8時間以内に制限
現在の警察による取調べは、特別な許可がない限り、1日8時間以内、基本的に午前5時から午後10時までの日中のみという制限が設けられています。1日8時間でも取調室に入れられ詰問が続けられれば、取調べを受ける被疑者はかなりの苦痛を強いられることになりますが、このルールを知っていれば、いつ終わるとも知れない取調べを受けている、という感覚が少しは楽になるでしょう。
取調べ中に体調が悪くなり倒れたり意識を失ったりして、適切な処置を行わなかったために被疑者が重篤な状態に陥ってしまうという事件もありましたが、そのような事態を避けるために、被疑者の体調管理については取調べを行う部署とは違う部署が担当することになっています。
そして取調べは基本的に日中に行うこととされていますが、逮捕は24時間365日、時刻を選ばず行われますので、夜中に発生した現行犯事件などは、深夜に取調べが行われることもあります。この時間制限で問題となってくるのが、警察での48時間、検察での24時間という逮捕の有効期限です。
取調べの時間が昔より短くなっても、この逮捕の有効期限は変更されていませんので、警察や検察は、より効果的に取調べを行い、次の刑事手続きに進めるように証拠などを揃えなければなりません。
「警察捜査における取調べ適正化指針」
上記の取調べ時間の制限を含め、取調べに関するさまざまな規定は、「警察捜査における取調べ適正化指針」にまとめられています。これは冤罪の続発や警察捜査の問題点が多く指摘されたことを受け、信頼回復を狙って国家公安委員会が決定し、警察庁が2008(平成20)年に取りまとめて発表したものです。
この指針の中には取調べに対する監督の強化として、「捜査部門以外の部門による取調べに関する監督」において、取調べにおける捜査員の不適正行為がまとめられていますので、以下に抜粋して紹介します。
取調べに関する監督を的確に行うことができるよう、次に掲げる取調べに係る不適正行為につながるおそれがある行為を監督の対象となる行為として国家公安委員会規則に類型的に規定する。
(イ)直接又は間接に有形力を行使すること。
(ウ)殊更不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
(エ)一定の動作又は姿勢をとるよう強く要求すること。
(オ)便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
(カ)被疑者の尊厳を著しく害するような言動をすること。
(キ)一定の時間帯等に取調べを行おうとするときに、あらかじめ、警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長の承認を受けないこと。
この規定がまとめられたということは、これらに類する行為が過去の取調べの現場で行われていたということになります。
被疑者の立場からすれば、過去の取調べは恐ろしかったのだと実感するところですが、現在はこれらの行為は禁止されていますので、もし取調べにおいてこれらの不適正行為を受けた場合には、取調べに関する監督を担当する監督担当者に申し出るか、弁護士を通じて改善を求めるようにしましょう。
留置場の監督は別部署が行う
1980(昭和55)年まで、被疑者が身柄を拘束される留置場の管理は、被疑者の取調べを行う刑事課が行っていました。そのため、警察の捜査員は自分たちの都合で好き勝手な時に被疑者を留置場から出して、昼夜関係なく長時間の取調べができていたのです。
しかしこうしたシステムでは強引な取調べが横行し、裁判所の法廷においても「強引な取調べで、自白を強要された!」と証言を翻す被告人もいたため、1980年に留置場の管理を刑事課から切り離し、留置場を管理する部署を新設したのです。
「留置業務管理体制の改善整備について」
古い話になりますが、この1980年に警察庁は、「留置業務管理体制の改善整備について」という通知を出し、刑事部門が管理していたために人権侵害などの弊害を生んでいた留置業務を、捜査を担当しない管理部門への移行を進めたのです。1980年には留置施設の処遇改善も行われ、各居室のプライバシーを重視するような造りに変更されたり、居住面積や弁護士と会う接見室が広げられたりしています。
これ以降、設備の建て替えや更新により、留置場の居心地やよくなってきたと言われていますが、拘置所と比べて留置場生活には比較的制限が多く、数が足りないという理由で勾留中でも代用監獄として使用されているなど、被疑者の待遇に関する問題は残っています。
「担当さん」に頼ってみよう
現在では刑事事件の担当捜査員が被疑者の取調べを行いたいと考えた時、まず留置場管理課から被疑者を引き渡してもらう手続きを行う必要があります。書類を準備するのは事件の捜査員ですから、逮捕または勾留されている被疑者には直接関係がないことですが、裏ではこのようなお役所仕事が進められています。
また地方や施設によって呼び名は違いますが、留置場管理課は、被疑者の健康を管理することも大きな役目のひとつとなっています。従って、警察署長などの許可がない限りは夜中や早朝といった極端な時間に取調べをしたいと捜査員が要請しても、留置場管理課側で却下するというシステムになっているのです。
事件の担当捜査官も、「担当さん」と呼ばれる留置場の管理係も同じ警察官同士ですので、この仕組みが導入されたばかりの頃はうまく機能しなかったようですが、現在では捜査員無茶な要求をすることもなくなり、留置場管理側主体で被疑者は刑事課に引き渡されて、取調べが始まることになります。
ちなみに、「担当さん」は被疑者の味方として健康管理を行うなど、頼れる存在として知られていますので、留置場生活で分からないことがあれば、何でも「担当さん」に聞いてみるのもよいでしょう。
取調べはどのように進められる?
留置場の日常は非常に時間に厳しく、規則正しい生活となります。
朝の布団上げや朝食、あるいは運動などの留置場の行事とも呼ばれる活動が一通り済んだ頃、被疑者は「担当さん」から、「調べだから出なさい」と呼ばれるのです。
居室から出され、留置場の扉の前で手錠をかけられ腰縄を打たれると、外では担当捜査員が待っていて、そのままの姿で取調室まで連行されていき、取調べが始まります。
取調室の様子は?
留置場から取調室に連行されると、施設にもよりますが、まず被疑者の手錠が外されます。ただし腰縄までは解かれず、逃亡防止のために、外された手錠とともに被疑者の座るパイプ椅子繋がれます。
ひとつの警察署内に取調室は複数ありますが、机以外には何もない殺風景な部屋で、事務机を向かい合わせに2つも置けば一杯になってしまうほどの広さしかない部屋、もしくはもうひとつ壁際に机を置ける程度の広さがある部屋などとなります。
机の上には担当の捜査官が持ち込んだファイルなどの資料とノートパソコン、そして供述調書をプリントアウトするための小型プリンターが置いてあります。
ちなみに刑事ドラマでは定番の電気スタンドは、実際の取調室にはありませんし、マジックミラーになっている鏡もすべての取調室についているわけではなく、窓もなく殺伐とした雰囲気が漂っている部屋なのです。
取調べの可視化が進められている
取調室で強引な取調べが行われることが問題になったことから、その防止策として取調べ中、取調室のドアは開けておくことになりました。
もっともドアが開いているということは、部屋の奥に座らされる被疑者の顔が入口から丸見えになってしまいますので、取調べ中は開いたドアの前にパーテションなどを立てて、声は筒抜けでも中の被疑者の顔は見えないという状態にされています。
以上のように、刑事事件の取調べにおいては、被疑者のプライバシーや人権を守ることが重視される時代になってきましたが、いくら制度やルールが定められても運用するのは警察であることに変わりはありません。
もし理不尽な対応をされ、ルール違反の取調べを受けたと感じた場合には、泣き寝入りせずに弁護士に相談し、有効な対応策を考えて動いてもらいましょう。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

この記事で分かること 逮捕された被疑者が求めるべきは「不起訴処分」「不起訴処分」を得る...
-

この記事で分かること 刑事事件で加害者が被害者と示談するメリット被害者と示談交渉を行う...
-

自首すると刑が軽くなるって本当?自首と出頭の違いについても解説
この記事で分かること 自首とは自首と出頭の違い自首をするメリット自首をするとどれくらい...
-

この記事で分かること 盗撮行為の余罪が捜査機関に露見する流れ過去の盗撮行為は余罪として...
-

この記事で分かること 刑事手続きの流れ(1)事件発生から逮捕まで刑事手続きの流れ(2)...
-

この記事で分かること 刑の確定は14日後どこの刑務所に収監されるのか?未決勾留があった...
-

この記事で分かること そもそも「事件」とは?「刑事事件」と「民事事件」の違いは?「民事...
-

警察からの呼び出しに応じないとどうなる?参考人として逮捕される?
この記事で分かること 警察からの呼び出しに応じると逮捕される?警察からの呼び出しの理由...
-

この記事で分かること 逮捕には原則がある再逮捕とは?再逮捕はどう行われる?再逮捕されて...
-

この記事で分かること 刑事裁判とは刑事裁判の種類によって流れが異なる一般的な刑事裁判の...