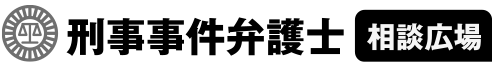刑事事件に関わる組織とそれぞれの役割を知る~警察、検察、裁判所~
- 2025年1月20日
- 53,348 view
- 刑事事件の基礎知識
- 刑事事件弁護士相談広場
刑事手続きに関わるのは「警察」「検察」「裁判所」

刑事事件の手続きを理解するためには、日本の司法制度を知っておくことが大切です。何故ならば、現実の司法制度はテレビドラマや映画で描かれるものは違うからです。
フィクションの場合、主人公が所属する組織を中心に物語が描かれていきますから、現実の世界では越権行為になりかねない行動を平気で行い、他の組織が簡略化した形に表現されていることも珍しくありません。
純粋に物語として楽しむのであれば、そうした設定を鵜呑みにしたままでも結構なのですが、実際に刑事事件に巻き込まれ、手続きを進めることになってしまった場合、最初に少し混乱するかもしれません。
特に、刑事事件の被疑者など、事件の当事者となってしまった場合には、初動が肝心ですから、どの組織がどういう理由と手続きで自分を逮捕して、これから何が行われるのかを知っておかないと、ただただ不安に襲われるだけになってしまいます。
弁護士に手続きを依頼することが最も効果的なのですが、当然ながら自身でも制度を知っておいた方が、より効率的に素早く手筈を整えることができるでしょう。
「警察」「検察」「裁判所」は独立したもの
日本で刑事事件の司法手続きに関わる主な組織は、「警察」、「検察」、「裁判所」の3つです。被疑者から見ると手続きは一貫して行われているように感じますが、これらの組織は独立しており、所轄官庁も違うのです。
それぞれの組織と役割については後述しますが、現場では「警察」と「検察」が一緒になって捜査しているように思われ、「検察」と「裁判所」は共に犯罪者を罰するために手続きを進めているように見えることもあります。
しかしその役割は厳密に分担されており、それぞれの立場から事件に向き合い、刑事事件についての捜査を行い、誰が犯人かを突き止め、無罪か有罪かを判断し、どれくらいの量刑が妥当かを決めているのです。
取調べ中に取調官が、「素直に認めたら釈放してやる」などとドラマの中で言っていることがありますが、それは単なる憶測であり、約束されたものではありません。刑事事件の司法制度を理解しておくことは、自身の自由と権利を守るためにも重要なのです。
3つの組織は、上下関係はないはずだが?
刑事事件に係る司法制度は、分業制となり、罪を犯した疑いのある者を裁くにあたって、その手続きをすべてひとつの組織に任せないようにしています。ひとつの組織に手続きが集中すると、特定の捜査機関の一存での犯罪のでっち上げや検証なしでの有罪認定、最終的には刑罰の執行までが可能になってしまうからです。
そのため、日本の司法制度は「警察」が被疑者を捕まえ、「検察」が被告人を起訴し、「裁判所」が有罪か無罪かを判断して刑罰を言い渡し執行する、という役割分担になっています。これら3つの組織は、「警察」が「警察庁」、「検察」は「法務省」の管轄で、「裁判所」は三権分立の原則から、すべての行政官庁や国会からも独立しています。
まったくの別組織で運営されていることになるため、どの組織が上位ということはなく、原則として立場は対等です。しかし、実際の刑事事件の手続きの流れを考えると、被疑者や被告人の身柄を拘束する逮捕や勾留に「裁判所」の許可が必要で、「警察」と「検察」という現場からの要請を受けて捜査令状などを発行しているという事実があります。
「裁判所」の許可がなければ、「警察」や「検察」はガサ入れと呼ばれる捜索や逮捕も勾留もできませんし、安直な勾留請求は却下されるケースがあるのです。「警察」と「検察」の関係性も地方によって違うと言われていますので、分業制を敷き役割分担を行っていると言っても、現場では微妙な力関係が働くということがあるかもしれません。
「警察」の組織と役割
「警察」の組織は、内閣府の外局「国家公安委員会」に置かれる「警察庁」に属し、現場の責任は各地方の自治体にあります。「国家公安委員会」が所轄する「警察」は「警察庁」がトップで、「警視庁」と各道府県警がその下に存在します。
東京都だけは「東京都警」ではなく、「警視庁」と呼ばれることが特徴的ですが、明治時代に、現在の「警察」が初めて設置されたのが東京で、当時は国家機関として「警視庁」と呼ばれていたものの名残です。
犯人を逮捕するのは「警察」の「警察官」
罪を犯した疑いがある者を逮捕する警察官は、「警察」組織に属する公務員で、役職と階級が与えられています。
役職とは警察署と呼ばれる各道府県の「警察」、また県警本部、警視庁、警察庁によって位は違いますが、
- 係
- 主任
- 係長
- 課長(補佐)
- 署長(副署長)
- 部長
- 本部長
- 管理官
- 参事官
- 理事官
- 審議官」
…、と多くの役職名があります。一方で警察官の階級は、すべての所属によって一定であり、その署に存在しているかいないかはありますが、権限も定まっており、共通認識が持てる職位です。
階級は「巡査」から始まり、「巡査長」、「巡査部長」、「警部補」、「警部」、「警視」、「警視正」、「警視長」、「警視監」、最高位は「警視総監」となり、階級を上げるために警察官は昇任試験を受けて合格する必要があるため、上下関係は非常に厳しいと言われています。
なお、「巡査部長」以上の警察官は「司法警察員」となり、「巡査」や「巡査長」は「司法巡査」として、捜査権限に制約が設けられています。具体的には、「司法巡査」は「裁判所に令状を請求できない」、「直接被疑者を取調べして調書を作れない」、「被疑者を送致できない」などと定められています。
逮捕が可能な専門機関も存在する
刑事罰が定められている法律や条令に違反した疑いのある者を逮捕できるのは「警察」だけではありません。最も有名なのは薬物を取り締まる専門の組織に属する「麻薬取締官」で、厚生労働省の職員となり、警察官ではないのですが、薬物犯罪の疑いがある者を逮捕する逮捕権を持っています。
他にも「皇宮護衛官」、「海上保安官」、「労働基準監督官」、自衛隊の「警務官」などが特別司法警察職員という立場で、警察の職務を行うことができます。また「国税庁職員(収税官吏)」や「税関職員」は強制捜査の権限を持っているため、広い意味で刑事事件に関わる組織は意外と多くあります。
「検察」の組織と役割
「検察」とは多くの場合に「検察官」を示す略称で、「検察官」の事務を統括する官署が「検察庁」です。法務省の特別の機関として、「最高検察庁」が最高裁判所に、「高等検察庁」が高等裁判所に、「地方検察庁」が地方裁判所と家庭裁判所に、簡易裁判所に「区検察庁」がそれぞれ置かれています。
「高等検察庁」は8庁(支部6庁)、「地方検察庁」は同じく50庁(支部203庁)、「区検察庁」は438庁と、全国の管内に分かれて「検察庁」があります。
「検察」はこれらの「検察庁」に属する組織ですが、それは「検察官」の事務を統括する官署に過ぎないため独任制の官庁とも呼ばれ、「検察官」が単独で検察権を行使し、「裁判所」に公訴を提起する権限を持っている点が特徴的です。
「検察」は事件を調べて犯人を裁判にかける
「検察」という言葉を聞いて最初に思い付くのは、テレビドラマなどの裁判の場面で警察側に付く検事(検察官の官名)かもしれませんが、実際には逮捕直後、あるいはそれ以前から刑事事件に関する捜査を行っている存在なのです。
「検察官」は、犯罪の捜査を行い、起訴するか不起訴にするかの決定をし、公判においては被告人の犯罪事実の立証をして論告や求刑を行います。場合によれば、上訴や裁判の執行などの役割を果たすこともある、刑事事件の手続きにおいては非常に重要な役割を果たしていますが、一般的には「警察」と「裁判所」はよく知られていても、「検察官」は馴染みの薄いものです。
ドラマの題材として「警察」や弁護士がよく取り上げられ、「検察官」が主役となるものは少ないからかもしれません。しかし「検察官」は、単に被告人の有罪や重罰を求めるだけではなく、法と正義の実現を目指して公平・公正に職務を行う立場にあり、そのためには証拠収集や立証に関して権限は限定されないため、刑事事件に関わるすべての人にとって重要な立場であることは間違いありません。
「検察官」の名称と職名
検察庁法に基づき、「検察官」には、「検事総長」、「次長検事」、「検事長」、「検事」、「副検事」という官名が与えられています。
「検事総長」、「次長検事」、「検事長」は内閣が任命し天皇が認証し、「検事」は司法試験に合格し司法修習を終えた者で一定の法律職の経験者から、「副検事」は司法試験合格者で公務員3年以上の経験者で審議会の選考を経た者から、それぞれ法務大臣が任命します。
また「検察官」には職名もあり、「検事正」(地方検察庁の長)、「次席検事」(高等検察庁及び地方検察庁にそれぞれ1名)、「三席検事」(地方検察庁に1名)、「部長」(各検察庁の部の責任者、刑事部長や公安部長など)、「支部長」(高等検察庁支部および地方検察庁にそれぞれ1名)、「上席検察官」(区検察庁の長)となっています。
「裁判所」の組織と役割
刑事事件に関わる司法制度上の組織として、「警察」と「検察」そして最後に「裁判所」があります。「裁判所」の仕事は、個人間の法律的な紛争(民事事件)を解決したり、罪を犯した疑いがある人が有罪か無罪か(刑事事件)を判断したりして、国民の権利を守り生活の平穏と安全を保つというものです。
当事者としては被害者と加害者(被疑者・被告人)がいますが、たいていの場合は弁護士を伴って「裁判所」に出向くことになります。「裁判所」は一般的に、原告と被告が向かい合い、お互いに意見を主張してどちらが勝つか、被告は無罪か有罪か、などを争う場所というイメージがあります。
しかし「裁判所」や「裁判官」、そしてどの法廷で何がどういう方法で取り扱われているのかは、テレビドラマなどでは簡単に描かれてしまっていることから、実際にはあまり知られていないのではないでしょうか。
「裁判所」には種類がある
取り扱う事件によって、それぞれの法廷が開かれる「裁判所」は違います。まず「裁判所」には、
- 「最高裁判所」(東京)
- 「高等裁判所」(本庁8、支部6、知的財産高等裁判所1)
- 「地方裁判所」(本庁50、支部203)
- 「家庭裁判所」(本庁50、支部203、出張所77)
- 「簡易裁判所」(438庁)
があります。
日本の裁判制度は、正しい裁判を実現するために三審制度が採用されているため、第一審、第二審、第三審と原則として3回までの審理が行われる仕組みとなっています。「地方裁判所」、「家庭裁判所」、「簡易裁判所」で第一審、「高等裁判所」で第二審、「最高裁判所」で第三審が行われるといった形となります(例外あり)。
そして刑事事件であれ、民事事件であれ、すべての裁判はこれら同じ「裁判所」で行われるのです。
「警察」から「検察」、「裁判所」への流れ
最後に、万が一刑事事件の被疑者となってしまった場合、これらの組織にどのような扱いを受けることになるのかを、典型的なパターンで簡単に説明します。まず、逮捕状(現行犯逮捕の場合はなし)を持った「警察」に逮捕され、多くの場合は警察署に連行され留置場に入れられます。
この逮捕の有効期限は48時間となり、その間に「警察」は必要な証拠や書類を揃えて、事件を「検察」へと引き渡す送検手続きを行います。逮捕の効力は「検察」に身柄が移されてから24時間以内となり、この間に「検察」の「検事」は事件を立件して起訴を行うか、不起訴処分にするかを決めます。
また「検察」は勾留請求を行って10日間の拘束を行うことができ、さらに10日間の勾留延長を申請することも可能です。そして、最初の逮捕状を発するのも、勾留請求を認めるかどうかの判断も、「裁判所」の「裁判官」が行い、起訴された後の法廷では、双方の言い分を聞いたうえで有罪か無罪か、量刑はどれくらいかの判決を下します。
一方、原則的には逮捕後いつでも、被疑者は唯一味方になってくれる弁護士に会って、弁護やさまざまな手続きを依頼することが可能です。
-
- 相談料
- 初回無料
※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。
-
- 土日
対応 - 可能
- 土日
-
- 夜間
対応 - 可能
- 夜間
-
- 夜間
対応 - 全国対応
- 夜間

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません
今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります!
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

弁解録取書と身上調書とは?逮捕後、警察の捜査官が作成する書類
この記事で分かること 被疑者の逮捕後に作成される書類とは?逮捕後に作成される書類「弁解...
-

この記事で分かること 逮捕後、取調べの前に行われる手続き写真撮影・指紋採取は強制科学的...
-

この記事で分かること 拘置所とは?拘置所はいつも満員?拘置所に移送されない他の理由弁護...
-

この記事で分かること 拘置支所とは?拘置所と拘置支所との違いは?拘置支所と刑務所の違い...
-

この記事で分かること 逮捕による身柄拘束は必ずしも必要ではない!身柄の拘束を伴わない「...
-

この記事で分かること 送検とは?逮捕後の手続きには時間制限がある実際の「送検」手続きは...
-

この記事で分かること 拘置所とは?拘置所には誰が収容される?拘置所と留置所や刑務所の違...
-
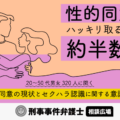
性的同意をハッキリ取るのは約半数!男女320人に聞く性的同意・セクハラ認識に関する行動・意識調査
この記事で分かること 性的行為の際、約半数は相手とハッキリした性的同意を取らず相手の不...