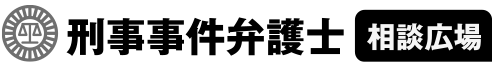交通事故は立派な刑事事件!逮捕になる場合はどんな時?
- 2025年1月20日
- 157,481 view
- もし逮捕されてしまったら
- 刑事事件弁護士相談広場
-
- 相談料
- 初回無料
※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。
-
- 土日
対応 - 可能
- 土日
-
- 夜間
対応 - 可能
- 夜間
-
- 夜間
対応 - 全国対応
- 夜間

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません
今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります!
交通事故が刑事事件・犯罪になるケースとは

交通事故を起こしても、常に「犯罪」が成立するわけではありません。まずは交通事故が犯罪になるケースがどのような場合か、確認しましょう。
基本的には人身事故
交通事故の加害者に犯罪が成立するのは、基本的に「人身事故」のケースです。つまり、被害者が「死傷」した場合に刑事事件になります。軽傷でもけがをしていたら犯罪となる可能性があります。また、ひき逃げや飲酒運転などの場合、通常の交通事故とは別の犯罪(道路交通法違反)が成立するので、罪が重くなります。
これに対し、車や施設、建物などが壊れただけの「物損事故」は基本的に犯罪になりません。そこで物損事故の場合、事故現場に警察を呼んでも「実況見分」が行われません。実況見分は、後の加害者の刑事裁判の資料にする目的で作成されるものだからです。
物損事故でも犯罪が成立する場合
ただし物損でも、以下のケースでは加害者に犯罪が成立します。
- 当て逃げのケース
- 飲酒運転のケース
- 無免許運転のケース
- スピード違反のケース
このようなケースでは、加害者の行為が「道路交通法違反」となるので、道路交通法によって処罰されるのです。
交通事故(人身事故)を起こして成立する犯罪
交通事故の加害者に具体的にどのような犯罪が成立するのでしょうか?
適用される可能性のある法律は「自動車運転処罰法」と「道路交通法」です。それぞれがどのような法律で、どのような行為を規制しているのかご説明します。
自動車運転処罰法
自動車運転処罰法は、人身事故の加害者を処罰するために作られた特別法です。
自動車運転処罰法がなかった頃は、交通事故によって被害者を死傷させた場合、刑法の「業務上過失致死傷罪」によって処罰されていました。しかしその刑罰があまりに軽く「悪質な交通事故が頻発している現状に即していない」という批判があったため、「自動車運転処罰法」が制定されました。
今では人身事故を起こすと、基本的にこの法律によって処断されます。以下で、自動車運転処罰法によってどのような犯罪が成立するのか、みていきましょう。
過失運転致死傷罪
過失運転致死傷罪は、人身事故の加害者に適用される基本的な犯罪です。交通事故の一般的な過失によって被害者を負傷させたり死亡させたりしたときに成立します。たとえば脇見運転、信号無視、見落とし、巻き込み事故、前方不注視、ながら運転などによって事故を起こすと、たいてい過失運転致死傷罪となります。
刑罰は、7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金刑です。
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪とは、故意と同じくらい悪質で危険な運転によって交通事故を起こし、被害者を死傷させたときに成立する犯罪です。たとえば飲酒や薬物によって正常な運転ができない状態で車に乗って事故を起こした場合や異常かつ危険な乗り方をしていた場合、高スピードで赤信号の交差点や人の集まっている場所に突っ込んだケースなどで、成立します。
危険運転致死傷罪の刑罰は、被害者がけがをしたケースと死亡したケースとで異なります。被害者がけがをした場合(危険運転致傷罪)、15年以下の懲役刑、被害者が死亡した場合には1年以上の有期懲役刑となります(有期懲役の限度は20年です)。
人身事故の加害者への厳罰化が進む!自動車運転処罰法|交通事故の種類
道路交通法違反
自動車を運転する人は「道路交通法」を守る義務を負っています。道路交通法とは、車両を運転する人や同乗者、歩行者などが公道を走行したり歩いたりするときに守るべきルールを定めた法律です。信号を守るべきこと、左側通行や徐行義務、交通事故を起こしたときにとるべき対処方法など、さまざまな細かいルールが定められています。
交通事故を起こしたとき、加害者が道路交通法違反の行為をしていると、自動車運転処罰法だけではなく道路交通法違反によっても処罰されます。
以下で、道路交通法違反の犯罪にどのようなものがあるのか、みていきましょう。
救護義務違反、危険防止措置義務違反
道路交通法は、交通事故の加害者に対して「救護義務」「危険防止措置義務」を課しています。これらを合わせて「緊急措置義務」と言います。
救護義務とは、交通事故で「車両」を運転していた人や同乗者がけが人を救護すべき義務です。自動車だけではなくバイクや自転車のケースでも義務を負いますし、運転者だけではなく同乗者にも義務が及びます。
危険防止措置義務とは、交通事故現場を片付けて車を脇に寄せ、後続車に危険を知らせるなど、二次被害を避けるべき義務です。これらの緊急措置義務をしない場合「ひき逃げ」扱いとなり、重大な刑事責任が発生します。
自ら事故を起こしておきながら救護義務違反、危険防止措置義務違反(ひき逃げ)をすると、10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が適用されます。
警察への報告義務違反
道路交通法は、交通事故の当事者に対して「警察への通報義務」を課しています。これは人身事故だけではなく物損事故にも適用されるので、物損事故でも報告を怠ると道路交通法違反となって処罰を受けます。いわゆる「当て逃げ」です。
報告義務違反の罰則は、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金刑です。
酒気帯び運転、酒酔い運転(飲酒運転)
「飲酒運転は犯罪」であることは一般的によく知られていますが、飲酒運転は道路交通法違反です。
道路交通法は、2種類の飲酒運転の罪を定めています。
- 酒気帯び運転
酒気帯び運転とは、呼気1リットル内に0.15mg以上、もしくは血液1ミリリットル内に0.3mg以上のアルコールが含まれている状態で運転することです。
- 酒酔い運転
酒酔い運転は、飲酒量や呼気血中内のアルコール量にかかわらず、「酒の影響で酩酊状態になっており、正常な運転ができない状態」で運転することです。
酒気帯び運転の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑、酒酔い運転の刑罰は5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑となっています。
無免許運転
道路交通法は四輪車やバイク、原付などを運転するとき、必ず有効な運転免許を取得しなければならないと定めています。無免許でこれらの車両を運転すると刑事事件となって処罰されます。
無免許運転の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。なお、有効な免許を取得しているけれども免許証をたまたま携帯していなかった場合「免許証不携帯罪」として3000円の罰金刑が科されます。
スピード違反
交通事故を起こすとき、加害者が高スピードを出しているケースも多いですが、道路交通法は、速度超過に対しても厳しい態度をとっています。スピード違反に適用される刑罰は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金刑です。
よく「10キロくらいなら超過してもOK」などと思われていることがありますが、道路交通法上は、制限速度を1キロでも超過したら法律違反となるので注意が必要です。処罰されていないように見えるのは、軽いスピード違反ならわざわざ逮捕されないことが多く、また反則金を支払うことで刑罰を免除してもらえるケースもあるからです。
スピード違反は本来道交法違反の罪なので、交通事故を起こしたときにスピード違反をしていると、適用される刑罰が重くなってしまいます。
救急車など緊急自動車の優先に対する違反
救急車や消防車、パトカーなどの緊急車両が後方から走ってきた際、同じ道路を走行する自動車は左側に寄って一時停止し、道を譲るのが一般的です。
通常、一種の交通マナーと思われているケースが多いようですが、実は、この対応は道路交通法の中で正式に定められた、れっきとしたルールです。
道路交通法40条(緊急自動車の優先)では、「緊急自動車が接近してきたとき、車両は、道路の左側に寄って、これに進路を譲らなければならない。」と定めています。
緊急車両が接近しても、左側に寄らず、意図的に道を譲らなかった場合、この法律に対する違反となります。
この違反が発覚すると、警察から交通反則告知書(青キップ)による告知を受け、違反点数1点、反則金6,000円の納付の対象となります。
反則金を納付せず放置した場合、罰金5万円以下の刑事処分を受ける場合があります。
交通事故犯罪の特徴
交通事故は、たいていが過失によって引き起こされるものですし、加害者は普段真面目に生活している人であることが圧倒的に多数です。いわゆる「前科者」「悪人」とは異なります。そこで、一般の犯罪とは異なり、以下のような特徴があります。
軽傷の事故なら「在宅捜査」が多い
刑事事件になったときの捜査方法には「身柄捜査」と「在宅捜査」があります。身柄捜査とは、被疑者の身柄を警察の留置場に拘束した状態で捜査を進める方法です。逮捕後引き続き10~20日は警察で勾留されるので、身柄拘束期間が長引いて、日常生活や仕事に対する影響が大きくなります。
在宅捜査とは、そもそも逮捕されなかったり、逮捕されても勾留されなかったりして、被疑者に自宅で過ごさせながら捜査を進める方法です。被疑者は普通に日常生活を送ることができて、刑事手続による影響が小さくなります。
交通事故では被害者が軽傷の場合、在宅捜査になるケースが多数です。
過失運転致死傷罪なら「略式裁判」が多い
次に「裁判」になったときの手続きにも特徴があります。
刑事裁判には「略式裁判」と「通常の刑事裁判」があります。略式裁判とは、裁判所が書類上だけで審査をして罰金刑を下す手続きです。法廷での審理は開かれません。被告人は自宅で普通に生活していると、起訴状と罰金の納付書が送られてくるので、それを使って罰金を支払ったら、刑罰を終えたことになります。
これに対して通常の刑事裁判は、一般の方が思い浮かべる法廷での審理です。被告人は毎回出頭して検察官から追及を受け、裁判官によって裁かれることになります。判決は最終的に裁判官から言い渡され、懲役刑や禁固刑となる可能性もあります。
交通事故の過失運転致傷罪の場合には、略式裁判が選択されるケースが多いです。
自覚がなくても前科が残る
このように、交通事故を起こしても「在宅捜査」→「略式裁判」が選択されると、加害者の日常生活にはほとんど影響が及びません。加害者は「犯罪を犯した」自覚を持たないケースもあります。ただし罰金刑が適用された場合でも、検察庁のデータベースに「前科記録」が登録されて、一生残ることには注意が必要です。
死亡事故や重傷事故の検挙率は高い
交通事故には「ひき逃げ」のケースがありますが、ひき逃げの「検挙率の高さ」についても知っておきましょう。ひき逃げの検挙率は事故の重大性によって大きく異なります。
平成28年度のデータによると、ひき逃げ事故の検挙率は、全体で56.8%でした。これを重傷事故に絞ると74.9%に上がります。さらに死亡事故では100.7%となり、100%を超えます(前年度以前の検挙数も含むために100%を超えています)。
つまり交通事故では重大事故になるほど検挙率が上がります。被害者を死亡させた場合などには、逃げても逃げ切れるものではありません。交通事故を起こしたら、決してひき逃げをせずに、その場にとどまって被害者の救護や警察への通報を行うべきです。
交通事故で逮捕されやすいパターン
交通事故を起こしても、物損事故なら逮捕されませんし、人身事故でも逮捕されないケースは多いです。
一方逮捕されやすいのは、以下のようなケースです。
死亡事故、重傷事故
事故によって被害者を死亡させたり重傷を負わせたりすると、逮捕につながりやすいです。これらの重大事故では加害者の責任が重くなるので厳正に処断する必要性がありますし、刑罰をおそれた加害者が逃げたり証拠隠滅したりする可能性も高くなるからです。
死亡事故が発生すると、その場で逮捕されて警察に連行されるケースも多数です。その場合、身柄捜査となって10~20日間の身柄拘束につながることも覚悟すべきです。
ひき逃げ
加害者がひき逃げをした場合にも、逮捕される可能性が高くなります。ひき逃げは非常に悪質な犯罪ですし、自動車運転処罰法の罪とひき逃げが成立すると、非常に処罰が重くなることが予想されます。またひき逃げの加害者は一度事故現場から逃げているわけですから、在宅捜査にすると再度逃亡する可能性が高いと考えられるからです。
飲酒運転
交通事故時に飲酒運転をしていた場合にも、逮捕の可能性が高まります。そもそも飲酒運転だけでも(交通事故を起こしていなくても)道路交通法違反となって厳しく処罰されますし、そのような危険な状態で交通事故を起こして被害者を死傷させた責任は非常に重いからです。
また飲酒運転をするような遵法意識の低い人は、外で生活させると逃亡したり証拠隠滅したりする可能性もありますし、再度車を運転して問題を起こす可能性もあります。
交通事故で逮捕された後の流れ
交通事故で逮捕されると、以下のような流れで刑事手続きが進みます。
在宅捜査の場合
- 逮捕される
- 48時間以内に送検される
- 身柄を解放される
- 捜査が継続する
- 検察庁で取り調べを受ける
- 不起訴処分または略式起訴される
- 罰金を支払う
上記は略式起訴のパターンですが、通常起訴された場合には、公判で裁かれて判決を受けます。

こちらも読まれています
身柄捜査の場合
- 逮捕される
- 48時間以内に送検される
- 24時間(逮捕後72時間)以内に勾留される
- 10~20日間勾留されて取り調べを受ける
- 不起訴処分、略式起訴、あるいは通常起訴される
- 刑事裁判の審理を受ける
- 判決を受ける
上記は通常裁判を前提とした流れです。判決で、懲役刑や禁固刑(実刑)になると、その場で収監されて拘置所や刑務所に送られます。
交通事故で逮捕されたときの対処方法
交通事故で逮捕されたら、以下のような対応をとりましょう。
示談交渉を進める
まずは、被害者との間で示談交渉を進めることが大切です。交通事故の場合、保険会社が示談金を支払うので保険会社が示談を進めることが一般的ですが、検察官による処分決定前に示談すれば不起訴になる可能性が高くなります。また刑事裁判になった後でも示談が成立すれば刑罰を軽くしてもらえます。
そこで刑事弁護人が代理で被害者に示談を申し入れて、早急に示談を成立させられるケースもあります。
在宅捜査にしてもらえるように対応する
交通事故で逮捕されたときには、なるべく「在宅捜査」にしてもらえるように努力すべきです。検察官や裁判所に勾留決定しないように申し入れをしたり、勾留を争う手続き(準抗告や勾留執行停止申立、勾留理由開示請求等)をしたりする方法が考えられます。
不起訴処分を目指す
交通事故が立件されてしまったら、なるべく不起訴処分を目指すべきです。そのためには、被害者との示談も重要ですが、加害者が反省の態度を示し、もう二度と事故を起こさないことをわかってもらう必要があります。
また初犯であること、事故が悪質ではないこと、今後は運転をしないと誓うことなども必要ですし、家族による監督を期待できることも示しましょう。
なるべく刑罰を軽くしてもらえるようにする
刑事裁判になってしまった場合には、なるべく刑罰を軽くしてもらえるように弁護活動を行うべきです。被害者との間で示談を成立させることが重要で、特に被害者から「嘆願書」を提出してもらえたら、刑罰を軽くしてもらいやすいです。
また被告人が法廷でしっかりと反省の意を述べて今後同じような事故を起こさないためにどのような対処をするのか、説得的に説明することも必要です。家族や勤務先の人に情状証人になってもらうことも考えましょう。
なるべくなら罰金刑を目指し、懲役刑や禁固刑を避けられないケースでも執行猶予判決を獲得しましょう。
交通事故で逮捕されたら弁護士に相談を!
交通事故で逮捕されたときには、被害者との示談交渉や勾留や起訴を防ぐための対応、刑事裁判への対応など、加害者本人だけでは対処できないことが多く、適切に対応して不利益を小さくするには弁護士の力が必要です。
弁護士であれば、被害者と示談交渉を進め、検察官に不起訴の申し入れをしたり、刑事裁判で弁護人として防御活動を展開しれたりして加害者の立場を有利にしてくれます。刑事手続きでは、早めの対応が重要です。逮捕されたらすぐに刑事事件に強い弁護士に相談して、刑事弁護人の活動を開始してもらいましょう。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

住居侵入罪(不法侵入)とは?罪の重さや不法侵入してしまい逮捕された時の対処法!
この記事で分かること 住居侵入罪(不法侵入)とは?住居侵入罪(不法侵入)の刑罰住居侵入...
-

この記事で分かること 器物損壊罪とは器物損壊罪の刑罰器物損壊罪の具体例器物損壊罪の「現...
-

痴漢の示談書に記載する内容とは?そのまま使える書き方のテンプレートを紹介
この記事で分かること 痴漢事件の示談書に記載する内容痴漢事件の示談書テンプレート痴漢事...
-

この記事で分かること 「のぞき」とは「のぞき」で成立する犯罪とは住居侵入罪・建造物侵入...
-

この記事で分かること 準強制性交等罪などの性犯罪は2017年に改正された準強制性交等罪...
-

暴行罪と傷害罪となる基準とは?ケンカで相手を殴ってしまった場合はどうする?
この記事で分かること ケンカの場合にも「犯罪」が成立する暴行罪と傷害罪の違い暴行と傷害...
-

この記事で分かること サイバー犯罪は増え続けているサイバー犯罪の種類電磁的記録を対象に...
-

逮捕されたらどうなる?警察に捕まったら身に起きる3つの出来事を徹底解説
この記事で分かること 逮捕はある日突然やってくる通常逮捕は早朝に行われるのが通例警察に...
-

この記事で分かること 盗撮事件での慰謝料金額の相場慰謝料と示談金はどう違うの?未成年が...
-

この記事で分かること 傷害罪初犯だと軽い処分で済みやすい傷害罪の初犯でも重い罰が与えら...