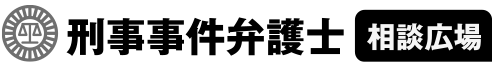暴行罪で逮捕されたら弁護士に相談!示談交渉のポイントと弁護士費用相場
- 2025年1月20日
- 23,786 view
- 犯罪の種類
- 刑事事件弁護士相談広場

会社の帰りに一杯飲んで、酔って喧嘩して逮捕されたという話はよく聞きます。しかし、そのようなことでも暴行罪という犯罪を犯したことには変わりなく、前科となれば自分だけでなく家族への影響も小さくありません。また恐喝、強盗、強姦などの犯罪の手段として使われることもあり、重大犯罪の入り口としての性格もあります。
暴行事件で身近な人が逮捕された場合
暴行罪は「相手を殴ったり蹴ったりした時に成立する罪」ですが、法的にはもう少し緻密に考えられています。暴行罪とはどういう罪で、逮捕された場合、被逮捕者はどのような状況になるのでしょうか。
暴行罪とは?
刑法では暴行罪は傷害罪とセットで考えられています。傷害罪に至らない犯罪が暴行罪という位置付けです。
暴行罪の構成要件と法定刑
暴行罪(刑法208条)の定義は①暴行を加えたものが、②人を傷害するに至らなかったこと、です。つまり、人に暴行を加えたけれど、相手は傷害を負わなった場合に成立します。もし、相手が傷害を負えば、傷害罪になります。法定刑は2年以下の懲役、若しくは30万円以下の罰金又は拘留、もしくは科料です。
「暴行」とは?
暴行の定義は「有形力の不法な行使」とされるのが一般的です。「有形力の行使」とは、直接殴る蹴るなど、人に触れて暴行することを意味しますが、そうなると指で軽く突いた場合も暴行罪が成立しかねません。そこで刑法では暴行を主に4種類に分類しています。
| 最広義の暴行 | 有形力の行使すべてを含み、人だけでなく物も対象になります。 |
|---|---|
| 広義の暴行 | 人に対する有形力の行使と、人に物理的、心理的に影響を与える物への行使です。直接、身体に対しての暴行とは限らず、例えば人の耳元で大きな音を鳴らし、不快感を与えたり、フラッシュでの目くらましなどが挙げられます。 |
| 狭義の暴行 | 人の身体に対する有形力の行使で、暴行罪にあたります。 |
| 最狭義の暴行 | 人が反抗できないように抑圧する有形力の行使で、強盗罪や強姦罪などが当たります。 |
身体に接触しない暴行もある
前述しましたが、暴行罪の成立には必ずしも身体へ接触した有形力である必要はありません。例えば、被害者の耳元で大音量を発する行為や、メガホンで大声を発する行為、通行人の数歩先を狙って石を投げつける行為などが暴行罪とされた例もあります。
「傷害」とは?
傷害は、一般的に「身体の生理機能の障害または健康状態の不良な変更」と理解されています。つまり、骨が折れたり、歯が折れたり、失神したりする状態になることです。そのような状態になったら暴行罪ではなく傷害罪となります。
暴行罪の刑罰、拘留と科料とは
拘留とは、刑罰の一種で刑事施設に1日以上30日未満の期間で拘置されます。同じ「こうりゅう」でも勾留は強制処分の一種で、被疑者や被告人を拘置するものであり刑罰ではありません。科料(刑法17条)は1000円以上1万円未満の財産刑です。法的には正しい表現ではありませんが「1万円未満の罰金」と考えればよいでしょう。
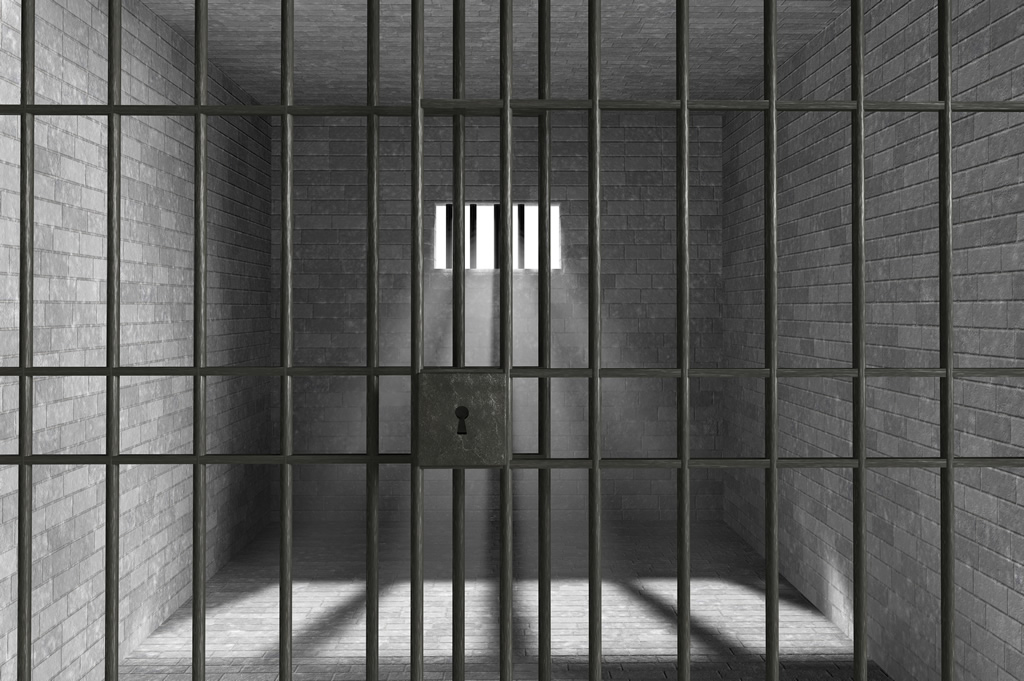
こちらも読まれています
暴行罪は親告罪でない
親告罪とは被害者からの告訴がないと起訴できない犯罪のことです。暴行罪は親告罪ではないので、被害者が告訴しなかったとしても、暴行事件として立件されてしまう可能性があります。
被害者が被害届や告訴状を出されていなければ、暴行罪で立件されることはほとんどありません。被害届を出された場合は、示談が成立しているか否かで立件されるかがポイントになってきます。
現行犯逮捕だった場合暴行罪として立件される可能性が高くなります。
暴行しても罰せられない場合
暴行罪で問題になるのは違法性阻却事由の有無です。「相手が殴ってきたから殴り返したのだから、正当防衛だ」といったセリフをテレビドラマなどで耳にしたことがあるかもしれませんが、正当防衛(刑法36条1項)は違法性阻却事由の代表例です。
違法性阻却事由とは?
違法性阻却事由とは、構成要件(犯罪として法律上規定された行為の類型)に該当する行為について違法性を失わせる特別な理由、根拠のことです。相手を殴ることは暴行罪にあたる行為であるのは間違いありませんが、相手が何の理由もなく急に殴りかかってきて、自分の身体を守るためにやむなく相手を殴ったのであれば、違法性はなく犯罪は成立しないと判断されるわけです。
正当防衛の成立要件
正当防衛が成立する要件としては①急迫、不正の侵害の存在、②自己又は他人の権利を防衛するため、③やむを得ずにした行為、であることです。「切羽詰まった状況だったので、我が身や別の人を守るために仕方なくやったんです」という場合に当てはまるかどうかと考えてよいでしょう。防衛に名を借りての積極的な攻撃や、相手の攻撃に対し不相当に過剰な暴行をした場合等には、正当防衛は成立しません
喧嘩と正当防衛
双方が攻撃する喧嘩について正当防衛は成立するのでしょうか。たとえば素手で殴り合っているのに途中から相手がナイフを出して攻撃してきた時や、一方が攻撃の意思を捨て攻撃をやめているのに、なお、攻撃をやめないためやむなく反撃した場合等で正当防衛が成立する余地はあります。つまり事件を全般的に観察した場合、個々の行為がどのようであるかについて検討するようになっていると言ってよいでしょう。
身柄拘束された本人と外部との連絡
暴行罪で逮捕された被疑者は、電話やメール等で外部と連絡を取ることはできません。また、家族との接見(面会)が認められない場合があります。ただし、弁護士との接見については認められます。
家族との接見、逮捕直後は原則不可
家族との接見は逮捕から勾留されるまでの間は、原則として認められません。接見できるのは勾留されてからです。検察官が被疑者を受け取ってから留置の必要があると思料する時に裁判所に勾留請求し、認められれば被疑者は勾留されます。勾留決定がされた後、家族は接見できますが逃亡や罪証を隠滅する可能性があると考えられるときは、接見禁止にすることができます。なお、弁護士は勾留時はもちろん勾留前も接見できます。
弁護人の接見は憲法上認められた権利
刑事事件において、被疑者や被告人が弁護人の弁護を受けることができる、弁護人依頼権は憲法34条前段で保障されている重要な権利です。逮捕された被疑者にとって、唯一の味方とも言えるのが弁護士です。被疑者や被告人は弁護人や弁護人になろうとする者と、立会人がいないくても接見でき、または書類や物の授受をすることができます(39条1項)。
特に重要な初回の接見
弁護人(になろうとする者)との接見の中でも、特に初回の接見は弁護人の選任を目的としたり、取調べにあたり助言を得られる重要な最初の機会で重要です。そして接見指定(39条3項)と呼ばれる、捜査機関による接見の日時、場所の指定について捜査に著しく支障が生じないかを検討した上で、比較的短時間であっても、時間を指定した上で即時または近接した時点での接見を認めるようにすべきとしています。このように弁護士との接見については捜査機関も十分に配慮せざるを得ないシステムになっています。
暴行罪で逮捕された後の流れ
暴行事件に限らず、逮捕され裁判が行われるまでの手続きは刑事訴訟法に規定されています。その手続きの中で釈放されたり、不起訴になったり、起訴されても保釈になったり、様々な状況が起こり得ます。ここではその流れを見てみましょう。
逮捕
逮捕は被疑者を強制的に身柄拘束する処分で、法定された短時間の留置を伴います。逮捕と一口に言ってもいくつかの種類があります。
逮捕には4種類、暴行罪で緊急逮捕はできない
逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、準現行犯逮捕、緊急逮捕の4種類があります。事前に令状請求して逮捕するのが通常逮捕、令状請求する時間がなく逮捕後に令状請求しなければならないのが緊急逮捕で、(準)現行犯逮捕では令状は不要です。
通常逮捕、緊急逮捕の逮捕権者は検察官、検察事務官または司法警察職員とされています。司法警察職員とは巡査を含む警察官という理解でいいでしょう。現行犯逮捕、準現行犯逮捕は官憲だけでなく私人も可能です。
暴行罪は最長で懲役2年ですから、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪の場合に可能な緊急逮捕の対象ではありません。
逮捕後の司法警察員の手続き
司法警察員は被疑者に対して、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければなりません。そして、留置の必要がないと思料する時は直ちに釈放し、留置の必要があると思料する時は身体の拘束から48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官に送致する手続きをとらなければなりません(203条1項)。
弁解の機会と取調
司法警察員は弁解を聞いて留置の必要性を判断しなければなりません。つまり釈放する権限を司法警察員が有しているわけです。もっとも弁解は弁解録取書にまとめられ、裁判で自己に不利な証拠となる可能性があります。弁解の機会に続いて取調が行われることが多いですが、その際には司法警察職員は被疑者に自己の意思に反して供述する必要がないことを告げる必要があります。
被疑者が外国籍だったら
被疑者が外国人の場合、自国の領事機関に通報することを要請するか確認し、領事官との面談や交通ができたり、弁護人の斡旋を依頼できたりすることを説明しなければなりません。領事官が自国民に関する任務遂行のために認められた権利を実現するためです(領事関係に関するウィーン条約36条1項)。もっとも同条約に加盟していない国の国民については必要ないと考えることは可能でしょう。主要国ではイスラエル、台湾(中華民国)、エチオピアなどが非加盟です(平成27年1月1日時点、国際条約集2015年版=有斐閣より)。
微罪処分とは?
微罪処分とは、軽微な事件について検察官が司法警察員に対して送致義務を免除するものです。司法警察員は本来、事件を速やかに検察官へ送致しなければなりません(全件送致主義の原則=246条)が、その例外である検察官指定事件(同条但し書き)の一つが微罪処分です。犯罪事実が極めて軽微で、かつ、検察官から装置の手続きの必要がないと予め指定されたものです(犯罪捜査規範198条)。
これは検察官が有する起訴猶予とする権利を、司法警察員に委ねたとするのが一般的な解釈です。平成27年の刑法犯のうち微罪処分で処理された者は7万1496人で、全検挙人員23万9355人に占める割合は29.9%とおよそ3割です(平成28年犯罪白書より)。微罪処分の基準は非公表ですが、暴行罪で微罪処分になる例は少なくないようです。
送検
逮捕され、司法警察員に留置の必要があると判断されたら被疑者は検察官に送致されます。
送検の意味
送検は日常生活ではよく聞く言葉ですが、刑事訴訟法には「送検」という言葉は出てきません。検察官に送致(203条1項後段)と表現されます。これは被疑者の身柄を検察官に送ることではなく、事件そのものを検察官に送ることを指します。つまり書類及び証拠物とともに被疑者の身柄を送致することで、それにより事件が検察官の扱いになることを意味します。
タイムリミット48時間
検察官送致には時間制限があり、被疑者の身柄拘束から48時間以内に書類及び証拠物とともに送致の手続きをしなければなりません(203条1項後段)。手続きをすれば良く、被疑者の身柄が実際に検察に到着するのは身柄拘束から48時間を過ぎていても問題ありません。
検察官送致された時の収容施設
被疑者がどこで収容されるかは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に定められています。逮捕された場合は通常、警察の留置施設に収容されます。検察官送致を受け勾留される者は拘置所などの刑事施設に収容されますが、留置施設に収容される場合もあります。いわゆる代用監獄の問題です。この点、実務では勾留決定があった場合でも警察の留置施設にそのまま置かれることが多いようです。
勾留
検察官は送致された被疑者を受け取った時、留置の必要があると考えた場合は、裁判官に被疑者の勾留を請求します。裁判官が勾留決定をすれば、被疑者は勾留されます。
送致を受けた検察官の手続き
検察官は送致された被疑者を受け取った時は、弁解の機会を与え、留置の必要がないと判断すれば直ちに釈放することになります(205条1項前段)。逆に留置の必要があると考えた場合は、受け取った時から24時間以内、かつ、被疑者が身体を拘束されて(原則として逮捕の時)から72時間以内に裁判官に勾留を請求しなければなりません。
裁判官による勾留決定
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対して被疑事件を告げ、勾留質問を行います(207条1項が準用する61条)。勾留の理由がある場合には速やかに勾留状を発しなければならず、勾留の理由がない時には釈放を命じなければなりません。また、必要があれば事実の取り調べをすることができます。
勾留期間と延長
勾留期間は10日です。勾留請求の日から10日以内に公訴を提起しない場合には直ちに被疑者を釈放しなければなりません。初日は時間にかかわりなく1日として計算されます。また、やむを得ない事由がある時は、10日を超えない範囲で期間の延長が認められます。合計で10日を超えないのであれば、延長の回数に制限はありません。
起訴
起訴は、検察官が裁判所に実体的審理と有罪判決を求める意思表示です。勾留延長される場合を除き、勾留請求の日から10日以内に起訴するか、しないかが決定されます。
検察官による起訴
起訴は検察官が行い、その権限は検察官のみが行使できるものです(247条)。これを起訴独占主義と言います。また、たとえ犯罪の証明が十分であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により起訴しないこともできます(248条)。これを起訴便宜主義と呼びます。つまり起訴するかしないか、検察官が一切の権限を有しているわけです。
起訴された場合の被疑者の勾留
起訴された被疑者は被告人となります。被疑者の段階で勾留されていて被告人になった後も勾留する場合には、検察官が起訴状を提出すると自動的に勾留が継続されます。被告人の拘禁場所は刑事施設ですから、通常は起訴されると拘置所に移送になります。しかし、現実の運用は拘置所の混雑などでスムーズにはいかないようです。その場合はしばらく留置場に勾留されることもあるようです。
被告人になったことによる効果
被疑者が被告人になることで、捜査機関による接見指定はできなくなります。これは接見指定が「公訴の提起前に限り」行えると規定されているためです。もっとも被告人が余罪について起訴前勾留されている時は指定が可能です。
公判
検察官による起訴があると、公判が開かれることになります。
裁判所の手続き
裁判所は公訴の提起があった時は、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければなりません(271条1項)。裁判長は公判期日を定め(273条1項)、検察官、弁護人に通知します。
弁護人選任権等の告知
裁判所は公訴の提起があったときは、遅滞なく被告人に弁護人を選任できる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任できない時は弁護人の選任を請求できる旨を知らせなければなりません(272条1項)。弁護人の選任の告知は逮捕時(203条1項)、勾留質問時(207条2項)にもされますが、ここでも行われます。このように何度も告知を義務付けるのは、憲法37条3項で保障された弁護人選任権を実質的に保障する意図であるとともに、刑事事件における被疑者・被告人の権利の保護のために弁護人の果たす役割の大きさを示すものと言えます。
公判手続きは大きく分けて4つ
公判手続きは、冒頭手続き-証拠調べ-弁論-判決という流れになります。冒頭手続は、人定質問(刑事訴訟規則196条)-検察官による起訴状の朗読(291条1項)-裁判長による権利告知(291条4項前段)-被告人及び弁護人が事件について陳述(罪状認否等、291条4項後段)という順番で行われます。裁判長による権利告知とは、終始沈黙し、または個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨、陳述がされた場合、自己に不利益な証拠ともなりうること等を告げます。
暴行罪では簡裁での審理も多い
暴行罪では簡易裁判所で公判請求されることが多くあります。これは選択刑として罰金が定められている罪の訴訟(裁判所法33条1項2号)にあたるためです。簡易裁判所では原則として禁錮以上の刑を科すことができません(同2項)。つまり、暴行罪で簡易裁判所に起訴された時は検察官の求刑は罰金刑しかないということになります。
簡易裁判所で起訴なら略式命令の可能性
暴行罪で簡裁に起訴された場合、検察官が公判手続きの必要がないと思料すれば、略式手続の請求ができます。予め被疑者の同意を得た上で請求し、簡易裁判所が公判手続によらずに書面審理だけで刑罰を言い渡せます(461条以下)。簡裁だけの制度で100万円以下の罰金又は科料を科すことができます。被疑者にとっても罰金刑しかありませんし、早期に事件から解放されるというメリットがあります。平成27年の検察庁終局処理人員を見ると暴行罪で公判請求をしたのは774人に対し、略式命令請求したのは3530人と4.56倍に及びます。(平成28年版犯罪白書より)。
暴行事件における示談交渉のポイント
暴行の容疑で逮捕、勾留された場合であっても、すべてが起訴されるわけではありません。嫌疑が不十分だった場合はもちろんですが、嫌疑がはっきりしていても総合的な判断で検察官が起訴しないこともあります(起訴猶予=248条)。起訴猶予となるか否かは、被害者との示談が成立しているかが大きなポイントを占めます。
暴行罪での示談のポイント
示談とは、加害者と被害者同士が裁判によらず話し合いで解決することです。暴行事件の場合、加害者が被害者にお金を支払う代わりに、被害者に被害届を出すことを留まってもらったり、もし既に出してしまった後ならば、取り下げてもらったりします。
暴行罪では財産上の損害はないのが普通です。しかし精神的な損害に対する慰謝料は支払うべきです。その上で強い反省の念を示すことが被害者の感情を和らげることになります。
被害者への謝罪が重要
示談を成立させるためには被害者への謝罪は前提になります。平成12年に新設された被害者等の意見の陳述制度により、被害者が公判で被害に関する心情その他の意見の陳述ができるようになりました。被害者感情は量刑判断において大きなウエートを占め、被害者への謝罪は重要な要素となります。謝罪がなければ示談は成立しないでしょう。
身柄拘束からの解放の取り組み
依頼を受けた弁護人としては、身柄を拘束された被疑者・被告人を一刻も早く自由の身にすることを目指します。自由の身になると一口に言っても、一連の手続きの中で様々な方法が考えられます。
検察官に送致されずに釈放
逮捕後、自由の身になる最初のチャンスは検察官への送致がされずに釈放されるときです。司法警察員は留置の必要がないと判断すれば直ちに釈放しなければなりません。釈放に向けてすべきことは犯罪の嫌疑が薄いこと、定まった住所や定職があり逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅ができないように現場付近に行かないことを約束するなどなので、自分は留置の必要性がないことを司法警察員に理解させることが大切です。
検察官送致後、留置の必要性がないと判断され釈放
被疑者が検察官に送致された後、検察官が留置の必要性がないと考えれば直ちに釈放されます(205条1項)。どのような場合に留置の必要性がないと判断されるかは、定まった住所がある、罪証隠滅ができないように関係者と接触しない、現場に近づかないことが約束されている、定職があり、身元を保証する者がいて逃亡のおそれがないなどが考えられます。
裁判官が勾留請求を却下して釈放
検察官から勾留請求が出されても、裁判官が勾留の理由がないと認める時は直ちに被疑者の釈放を命じなければなりません(207条5項)。そのため、勾留の理由がないことを裁判官に働きかけます。実際には検察官の勾留請求から、裁判官の勾留決定までは時間も少ないことから、同時期に働きかける場合が多いようです。なお、裁判官のした勾留決定に対しては準抗告が可能です。
起訴後勾留に対して保釈申請をする
起訴された場合は、保釈(88条以下)を請求します。保釈とは保釈保証金を納付して勾留の執行を停止し、拘束を解く制度です。起訴前勾留にはこの制度は適用されません。
保釈には必要的保釈と裁量的保釈の規定があり、過去に重罪で有罪判決を受けた、常習犯である、罪証を隠滅する疑いがある、被害者や証人、その親族などに危害を加えたり畏怖させたりする疑いがある、氏名又は住居が分からないに該当しない場合には必要的に保釈されることになります。仮にいずれかに該当する場合でも裁判所が適当と認めれば保釈されることはあります(90条)。
暴行罪で弁護士に依頼する場合の費用相場
弁護人に事件の担当を依頼する場合費用がかかります。示談する場合も金銭が必要になりますし、示談をする弁護人への費用も必要になります。
示談金
示談金は決まっているわけではないので、被害者に連絡を取り話し合いによって決まります。どのような暴行だったか、被害者の感情がどの程度かなどの被害の程度にもよりますが、一般的に示談金は10万円~30万円となることが多いようです。
慰謝料は示談金の一部
そのほかに暴行における被害者の恐怖心や屈辱感など、精神的損害を金銭で賠償する必要があります。その意味から慰謝料は示談金の一部であると言えます。
弁護士費用
示談をするには弁護士の力が必要です。加害者(被疑者)の親族が被害者と示談交渉をしようと思っても、被害者は自分の住所など連絡先を知られたくないと考える場合が多いでしょうから、交渉のテーブルにつくことさえ困難な状況が予想されます。そこで、連絡先を教えるのは、弁護士だけにするという条件で被害者の連絡先を教えてもらうなどの交渉が必要になります。示談は加害者本人がするのは難しく、弁護士に依頼するのが近道です。

こちらも読まれています
相談料
弁護士への相談料は、最近は初回無料としていることが多いようです。2回目以降は30分5000円程度が相場と言えます。
接見費用
被疑者・被告人との接見の場合、弁護士は事務所から勾留場所まで行く必要があります。また、身柄拘束を解くためには、司法警察員、検察官、裁判官の手続きに時間制限がある以上、迅速に行う必要があります。そのため費用としても勾留場所との距離にもよりますが、1回3万円前後はかかるのが普通です。事件解決のために何度も接見しなければならない場合は、その分接見費用も嵩むことになります。
着手金
弁護士が事件を担当する場合、依頼人は着手金を支払うことになります。刑事事件では自白している事件であれば事実関係を争うことがありませんが、否認事件では不起訴や無罪判決を取る必要があり、事実関係からして争うことになります。そのため、否認事件は一般的には高くなります。弁護士にもよりますが、通常の自白事件なら20〜30万円程度、否認事件なら30〜50万円程度でしょう。
自白事件の成功報酬
自白事件であっても弁護士の活動によって起訴猶予、略式命令(恐喝罪は懲役刑のみなので略式命令になることはありません)、執行猶予付き判決、保釈許可決定、勾留に対する準抗告が認められるなどで被疑者・被告人にとって利益になることがあります。その場合には成功報酬を支払うことになります。事件や弁護士にもよりますが起訴猶予や微罪処分が10〜30万円程度、それ以外は20万円以下が相場と言えるのではないでしょうか。示談が成功した場合や、求刑より言い渡された刑が軽い場合にも成功報酬は必要となるのが普通です。執行猶予については平成28年6月から始まった刑の一部執行猶予制度も成功報酬が必要と考えた方がいいでしょう。
否認事件の成功報酬
否認事件では無罪判決を得ることが可能です。その場合には事実関係を争い、時間と手間をかけて争いますから、当然、成功報酬は高く設定されます。30〜50万円程度は必要でしょう。もちろん自白事件でも無罪判決の可能性はあります(ウソの自白をした場合等)し、自白事件の方が無罪判決の獲得は難しいですから、少なくとも否認事件での無罪判決と同程度の成功報酬は必要になります。なお、否認事件でも不起訴、執行猶予付き判決などでの成功報酬は必要になると考えるべきでしょう。
実費
弁護士が活動にあたって実際に経費としてかけた分は依頼人に請求されます。接見するための交通費や、通常の通信費などです。
日当
出頭したり、出張したりした際の日当が必要になります。概ね1回で3万円前後でしょう。また着手金を支払わずに、実際にかかった日数、時間によって支払額を決定する「タイムチャージ」という方式で支払う方法もあります。着手金で一律に支払うのではなく、かかった時間だけ支払うというものですが、大きな事件になると日数がかかり着手金方式より多く支払わなければならないということも考えられます。
刑事事件は時間が勝負!
刑事事件は警察-検察-裁判所と時間をかけずに手続きが進んでいきます。それに対して不服の申し立てをしなければ、起訴-有罪へと近づいていくと言っても過言ではありません。早期の対策こそが重要です。
暴行罪で弁護士に依頼するメリット
刑事事件では弁護士がつくことで様々なメリットがあります。
示談交渉による問題解決
身柄の拘束を解くため、あるいは量刑判断などで示談が成立しているかどうかは大きなポイントになります。
示談で起訴を免れる場合も
刑法、刑事訴訟法、刑事訴訟規則には「示談」という単語はありません。そもそも刑事上の責任は個人間の交渉で排除できませんから、当事者の合意で有罪を無罪にすることはできません。あくまでも示談の結果によって訴訟法上の効果が出たり、裁判所の量刑判断に影響が出たりするだけです。しかし、検察官が起訴するかどうかの判断において示談が成立していれば被害者がもう処罰を望んでおらず、損害の賠償も済んでいると判断しますから、公判請求の必要は無いとして起訴猶予にする可能性はあります。
示談で量刑判断も変わる
起訴された場合でも、裁判所は量刑判断においては情状面を考慮しますから、示談の成否は大きく影響します。示談を拒否して厳しい処罰感情を明らかにすれば、厳しい量刑が出やすいでしょう。逆に示談が成立していれば被害者は厳しい処分は望んでいないと判断され、厳しくない量刑となる可能性はあります。
外部への連絡・説明
逮捕され、身柄を拘束されている被疑者は外部との連絡を取る手段を持っていません。そこで弁護士が重要な役割を果たすことになります。
外部連絡は弁護士のみ可能
逮捕されると被疑者は外部と電話やメールなど、一切の連絡手段を使うことができなくなります。家族についても、勾留されるまでは原則として接見できません。そのような状況で被疑者と連絡を取れるのは弁護士だけです。被疑者の状態を家族や会社に性格に伝えることができ、外部との唯一の窓口として機能します。
手続きの見通しなど説明が可能
家族や会社の関係者が突然の逮捕で、どのような手続きが進むのかも分からない状況の中、弁護士は刑事訴訟法、刑事訴訟規則に基づく手続きの流れを熟知していますから、その後のことを予測することができます。身柄の拘束を解くためにどのタイミングで何をすればいいか、家族や会社はどう協力すべきか、適切にアドバイスをして被疑者とその関係者のために力になることができます。
処罰の軽減、回避につながる弁護活動
弁護士は身柄の拘束を早く解くこと、処罰を軽減、回避するための活動を行います。
示談交渉
弁護士が行う活動で最も重要なのが示談交渉でしょう。恐喝罪であれば被害者に謝罪し、損害を賠償することで被害者感情をやわらげ、起訴猶予や即決裁判で執行猶予付き判決を受け事件を終結させることで被疑者の期待に応えることができます。仮に起訴されても示談が成立していれば量刑面での減軽や、実刑判決のところが執行猶予付きになることも期待できます。
早期の依頼で解放へ様々な活動が可能
弁護士は司法警察員に検察官送致をしないよう働きかけたり、送致されても検察官に勾留請求をしないように働きかけたりすることが期待できます。勾留されても準抗告したり、起訴されても保釈を申請したり、身柄の拘束からの解放に全力を尽くすでしょう。それによって処罰の回避や、自由の身になることなどが期待されます。
暴行罪は自分だけでなく家族や身近な人が巻き込まれやすい事件です。刑事事件における弁護士の果たす役割は非常に大きいので、もし逮捕されたら、速やかに刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することが大切です。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

傷害罪で逮捕されたら弁護士に相談、傷害事件の示談交渉のポイントと慰謝料の相場
この記事で分かること 傷害事件で身近な人が逮捕された場合傷害罪と暴行罪、定義の違いは?...
-

「迷惑防止条例」とは?~痴漢などの犯罪に刑罰を与える各地の条例~
この記事で分かること 「迷惑防止条例」とは?東京都の「迷惑防止条例」による痴漢の規定「...
-

性犯罪で最も重い「強制性交等罪」(1)~「強姦罪」から改正~
この記事で分かること 「強姦罪」から「強制性交等罪」へ性犯罪の厳罰化が進む「非親告罪」...
-

この記事で分かること 強盗罪の定義とは?強盗罪は非常に重い刑罰が科せられる強盗が絡む他...
-

盗撮で逮捕されたら弁護士に相談!知るべき10のポイントと慰謝料相場を解説
この記事で分かること まず始めに、盗撮はどんな罪で逮捕されるのか盗撮で逮捕された場合に...
-

この記事で分かること 盗撮とは?事件になる典型的なケース盗撮行為で受ける刑罰公共の場所...
-

この記事で分かること 盗撮で逮捕されるときに適用される法令は2つある軽犯罪法と迷惑防止...
-

この記事で分かること 盗撮の構成要件とはどういう意味?軽犯罪法で規制される盗撮の構成要...
-

この記事で分かること 盗撮に関する刑罰・刑期・懲役についての規定盗撮で逮捕された場合は...