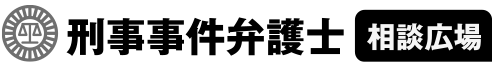傷害罪で逮捕されたら弁護士に相談、傷害事件の示談交渉のポイントと慰謝料の相場
- 2025年1月20日
- 24,108 view
- 犯罪の種類
- 刑事事件弁護士相談広場

暴力事件を起こして相手を怪我させれば逮捕され、傷害罪で罰せられる可能性があります。傷害罪は罰金刑だけでなく、最高で懲役15年まである重罪です。もし、自分や家族が逮捕されたら、弁護士の助けを借りることが大切です。
傷害事件で身近な人が逮捕された場合
警察沙汰とは無縁と思える人でも、会社の行き帰りに喧嘩に巻き込まれて傷害罪で逮捕!ということもあるかもしれません。「傷害罪=他人を傷つける=重罪」というイメージの連鎖で家族はパニックに陥ることもあるでしょう。傷害罪とはどういう罪で、逮捕された場合どのような状況になるのでしょうか。
傷害事件とは?
傷害事件とは傷害罪(刑法204条)が適用される事件のことを言います。傷害罪成立の要件とはどのようなものでしょうか?
傷害はケガだけではない
傷害罪の要件は①人の身体を、②傷害したこと、です。傷害したと言えるかどうかは、身体の生理機能や健康状態に障害を与えたかで決まるのが一般的な理解です。「血が出た」「あざになった」「歯が折れた」などは当然ですが、疲労感や目眩、嘔吐、うつ病、外傷後ストレス障害(PTSD)など、精神的な苦痛を与えられたことによる悪影響も傷害とされています。
どんな小さなケガでも傷害?
「身体の生理機能の障害または健康状態の不良な変更」という障害の定義からすれば、わずかな傷でも傷害罪と言えそうです。しかし、そうだとすると暴行を受けた場合のほとんど傷害罪になってしまいます。名古屋高金沢支判昭和40年10月14日では、次のような3要件を満たす場合は、傷害ではなく暴行とするとしています。
- 日常生活に支障をきたさないこと
- 傷害として意識されないか、日常生活上看過される程度であること
- 医療行為を特別に必要としないこと
接触なき傷害、暴行なき傷害
殴ったり蹴ったりしてケガをさせたというのが一般的な傷害罪のパターンでしょう。しかし、耳の近くでメガホンを向けて大声で話して相手の耳の感覚をおかしくさせたりする「接触なき傷害」もあります。また、隣家に向けてラジオや目覚まし時計のアラーム音を1年以上鳴らし続け隣人を慢性頭痛症等にした「騒音おばさん」事件のような「暴行なき傷害」もあり、ともに特異な例と言えるでしょう。
傷害事件の法定刑
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。つまり有罪の場合、罰金1万円から懲役15年まで、判決が出される可能性があります。傷害の結果、相手が死亡した場合は傷害致死罪(刑法205条)となり、3年以上の有期懲役となります。
傷害罪と暴行罪、定義の違いは?
刑法では傷害罪と暴行罪は別々に規定されています。両罪はどこが違うのでしょうか。
暴行の定義
刑法での「暴行」は「有形力の不法な行使」と説明されるのが一般的です。「有形力の不法な行使」とは、殴る蹴るといった直接的な暴力です。犯罪により暴行の程度は区別され、たとえば強姦罪などで用いられる「暴行」は「人の反抗を抑圧する、もしくは著しく困難にするに足りる有形力の行使」とかなり強い程度での暴行を指します。なお暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、拘留もしくは科料です。
暴行罪の延長上にある傷害罪
暴行罪の条文は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」となっています。簡単に言えば、AがBを殴ったところAは怪我するまでには至らなければ暴行罪、Aが骨折するなどの怪我を負えば障害罪になるというわけです。
傷害事件で身柄拘束された本人と外部との連絡
逮捕された被疑者は電話やメール等で外部と連絡を取ることはできません。また、家族との接見(面会)も認められない場合があります。ただし、弁護士との接見については認められます。
家族との接見、逮捕直後は原則不可
家族との面会(接見)は逮捕から勾留されるまでの間は、原則として認められません。接見できるのは勾留されてからです。検察官が被疑者を受け取ってから留置の必要があるとしたときは裁判所に勾留請求し、認められれば勾留されます。勾留決定がされた後、家族と接見できますが、逃亡や証拠を隠滅する可能性があるときは接見禁止にされる場合があります。なお、弁護士とは勾留時はもちろん勾留前も接見できます。
弁護人の接見は憲法上認められた権利
弁護人依頼権は憲法34条前段で保障されている重要な権利です。逮捕された被疑者にとって、唯一の味方とも言えるのが弁護士です。弁護士とは(弁護士になろうとする者も含む)とは、立会人がいなくても接見でき、書類や物の授受もできます。(39条1項)
特に重要な初回の接見
弁護人(になろうとする者)の接見の中でも、特に初回の接見については弁護人の選任を目的としたり、取調べにあたり助言を得たりする最初の機会ですので重要です。捜査機関においても、弁護士との接見については十分に配慮するシステムになっています。
傷害事件、逮捕からの流れ
傷害事件に限らず、逮捕されればその手続きの中で釈放されたり、不起訴になったり、起訴されても保釈になったり、様々な状況が起こり得ますが、通常の逮捕から判決までの流れを見ていきましょう。
逮捕
逮捕は被疑者を強制的に身柄拘束する処分で、法で定められた短時間の留置を伴います。逮捕と一口に言ってもいくつかの種類があります。
逮捕には4種類
逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、準現行犯逮捕、緊急逮捕の4種類があります。(準現行犯逮捕と現行犯逮捕を一つにして3種類と考えることもあります。)
- 通常逮捕:事前に令状請求する逮捕。
- 通緊急逮捕:令状請求する時間がなく逮捕後に令状請求しなければならない逮捕。
- 通準現行犯逮捕:令状は不要。
- 現行犯逮捕:令状は不要。
通常逮捕、緊急逮捕の逮捕権者は検察官や検察事務官または司法警察職員(警察官)とされています。一方現行犯逮捕及び準現行犯逮捕では、警察官だけでなく個人も可能です。(213条)。
傷害事件の逮捕後の動き
逮捕されると、被疑者は司法警察員から犯罪事実の要旨と弁護士を選任することができる旨が告げられます。もし留置の必要がないと判断(思料)されれば直ちに釈放されますが、置の必要があれば、拘束から48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官に送致する手続きがとられてしまいます。
弁解の機会と取調
被疑者を釈放する権限は法警察員が有しています。被疑者は弁解の機会を与えられ、続いて取調が行われますが、その際に司法警察職員から自己の意思に反して供述する必要がないこと、つまり黙秘権について告げられます。(198条2項)。
傷害事件の被疑者が外国籍だったら
被疑者が外国人の場合、自国の領事に通報することを要請するかを確認されます。領事館との面談ができたり、弁護人の斡旋を依頼できたりすることが説明されます。
微罪処分
微罪処分とは、軽微な事件について検察官が司法警察員に対して送致義務を免除するものです。司法警察員は本来、事件を速やかに検察官へ送致しなければなりませんが、その例外である検察官指定事件の一つが微罪処分です。微罪処分とは犯罪事実が極めて軽微で、かつ、検察官から送致の手続きの必要がないと指定されたもので、その割合は全検挙人員のおよそ3割です(平成28年犯罪白書より)。
送検
逮捕され、司法警察員に留置の必要があると判断されたら被疑者は検察官に送致されます。
送検の意味
送検は被疑者の身柄を検察官に送ることではなく、事件そのものを検察官に送ることを指します。つまり書類及び証拠物とともに被疑者の身柄を送致することで、それにより事件が検察官の扱いになることを意味します。
タイムリミット48時間
検察官送致には時間制限があり、被疑者の身柄拘束から48時間以内に書類及び証拠物とともに送致の手続きがされます。
検察官送致された時の収容施設
逮捕された場合は通常、警察の留置施設に収容されます。検察官送致を受け勾留される者は拘置所などの刑事施設に収容されますが、留置施設に収容される場合もあります。いわゆる代用監獄ですが、勾留決定があった場合でも警察の留置施設にそのまま置かれることが多いようです。
勾留
被疑者に留置の必要があると考えた場合、検察官は裁判官に被疑者の勾留を請求します。裁判官が勾留決定をすれば、被疑者は勾留されます。
送致された後は?
検察官は送致された被疑者を受け取った時、弁解の機会を与え留置の必要がないと判断すれば直ちに釈放することになります(205条1項前段)。逆に留置の必要があると考えた場合は、受け取った時から24時間以内、かつ、被疑者が身体を拘束されて(通常は逮捕の時)から72時間以内に裁判官に勾留を請求しなければなりません
裁判官による勾留決定
勾留請求を受けた裁判官により、勾留するかしないかが決定されます。被疑者に対して勾留する必要があるかどうか判断するために、被疑者に勾留質問を行います。勾留の理由がある場合には速やかに勾留状を発され、勾留の理由がない時には釈放されることになります。また、必要があれば事実の取り調べが行われます。
勾留期間と延長
勾留期間は10日です。勾留請求の日から10日以内に公訴を提起しない場合には直ちに被疑者は釈放されます。初日は時間にかかわりなく1日として計算されます。また、やむを得ない事由がある時は、10日を超えない範囲で期間の延長がされます。合計で10日を超えなければ、延長の回数に制限はありません。
起訴
起訴は、検察官が裁判所に実体的審理と有罪判決を求める意思表示です。勾留延長される場合を除き、勾留請求の日から10日以内に起訴するかしないかが決定されます。
検察官による起訴
起訴は検察官が行い、その権限は検察官のみが行使できます。(247条)。これを起訴独占主義と言います。また、たとえ犯罪の証明が十分でも、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により起訴しない場合もあります(248条)。
起訴された場合の被疑者の勾留
起訴された「被疑者」は「被告人」となります。被疑者の段階で勾留されていて被告人になった後も勾留される場合、検察官が起訴状を提出すると自動的に勾留が継続されます。被告人は起訴されると拘置所に移送になります。しかし、現実の運用は拘置所の混雑などでスムーズにはいかず、しばらく留置場に勾留されることもあるようです。
公判
検察官によって起訴になると、公判が開かれることになります。
裁判所の手続き
裁判所は公訴の提起があった時は、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達します。裁判長は公判期日を定め、検察官、弁護人に通知します。
弁護人選任権等の告知
公訴の提起があったとき、被告人は弁護士が選任できること、経済的に選任ができないときは選任の請求ができることが伝えられます。これは逮捕時、勾留質問時にもされますが、ここでも行われます。
公判手続きは大きく分けて4つ
公判手続きは、冒頭手続き→証拠調べ→弁論→判決という流れになります。
冒頭手続は、認定質問→検察官による起訴状の朗読→裁判長による権利告知→被告人及び弁護人が事件について陳述という順番で行われます。裁判長による権利告知とは、終始沈黙したり、または個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨、陳述がされた場合、自己に不利益な証拠ともなりうること等を告げることです。
傷害事件における示談交渉のポイント
傷害の容疑で逮捕、勾留された場合であっても、全件が起訴されるわけではありません。嫌疑が不十分だった場合はもちろんですが、嫌疑がはっきりしていても総合的な判断で検察官が起訴しないこともあります。起訴猶予となる場合、あるいは微罪処分となる場合、被害者との示談が成立しているかが大きなポイントを占めます。
被害者への謝罪が示談の基本
示談については刑事訴訟法、刑事訴訟規則、犯罪捜査規則等に規定がありません。しかし、司法警察員による微罪処分、検察官による起訴、起訴猶予を決定する場合において示談の成否が重要な役割を果たします。
示談の法的性質
刑事裁判は犯罪を犯した者に対して国家刑罰権を実現する裁判ですから、示談によって刑罰権を消滅させることはできません。しかし、強姦罪等の親告罪は示談が成立して告訴を取り下げることになれば検察は公訴提起ができなくなります。また、示談の成立により被害者感情が和らいだり、被疑者・被告人の反省、生じた損害の金銭的な回復などから微罪処分、起訴猶予等になる可能性もありますし、有罪判決でも情状酌量が期待できます。
被害者への謝罪が重要
示談を成立させるためには被害者への謝罪は前提になります。平成12年に新設された被害者等の意見の陳述(292条の2)制度により被害者が公判で被害に関する心情その他の意見の陳述ができるようになりましたが、被害者感情は量刑判断において大きなウエイトを占めます。仮に傷害致死事件であれば、被害者の親族等は被害者参加制度(316条の33以下)にも参加できます。このように被害者感情に法が配慮している中、示談が成立するということは被害者感情が宥和していることを示します。そのためにも被害者への謝罪は重要な要素となります。謝罪がなければ示談は成立しないでしょう。
傷害罪での示談のポイント
傷害罪では相手が傷害を負うわけですから、その被害に対して治療にかかった費用等を負担するのはもちろん、精神的な損害に対する慰謝料なども支払うべきです。その上で深い反省の念を示すことが被害者の感情を和らげることになります。
身柄解放への取り組み
依頼を受けた弁護人としては、身柄を拘束された被疑者・被告人を一刻も早く自由の身にすることを目指します。自由の身になると一口に言っても、一連の手続きの中で様々な方法が考えられます。
検察官に送致されずに釈放
逮捕後、自由の身になる最初のチャンスは検察官への送致がされずに釈放されるパターンです。司法警察員が留置の必要がないとすれば直ちに釈放されます。釈放に向けてすべきことは、犯罪の嫌疑が薄いこと、定まった住所や定職があり逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅ができないように現場付近に行かないことを約束するなどして、留置の必要性がないことを司法警察員に示すことでしょう。
検察官送致後、留置の必要性がないと判断され釈放
被疑者が検察官に送致された後、検察官が留置の必要性がないと考えれば直ちに釈放されます。留置の必要がないとされるのは、定まった住所がある、罪証隠滅ができないように関係者と接触しない、現場に近づかないことが約束されている、定職があり、身元を保証する者がいて逃亡のおそれがないなどが考えられます。
裁判官が勾留請求を却下して釈放
検察官から勾留請求が出されても、裁判官が勾留の理由がないと認めれば、直ちに被疑者は釈放されます。そのため、勾留の理由がないことを裁判官に働きかける必要があります。実際には検察官の勾留請求から、裁判官の勾留決定までは時間も少ないことから、同時期に働きかけることになる場合が多いようです。
裁判官の勾留決定に対して準抗告する
裁判官のした勾留決定に対しては準抗告が可能です。ただし、勾留の裁判で犯罪の嫌疑がないことを理由に準抗告することはできません。そのようなことは本案で争うべきだからです。「私は無実だから」ということを主張するだけで準抗告が認められることはありません。
起訴後勾留に対して保釈申請をする
起訴された場合は、保釈を請求できます。保釈とは保釈保証金を納付して勾留の執行を停止し、拘束を解く制度です。起訴前勾留にはこの制度は適用されません。
保釈には必要的保釈と裁量的保釈の規定があります。必要的保釈の場合除外事由に該当しなければ裁判所は保釈しなければなりません。傷害罪であれば、過去に重罪で有罪判決を受けた、常習犯である、罪証を隠滅する疑いがある、被害者や証人、その親族などに危害を加えたり畏怖させたりする疑いがある、氏名又は住居が分からないに該当しない場合には必要的に保釈されることになります。仮にいずれかに該当する場合でも裁判所が適当と認めれば保釈されることはあります。
傷害事件の弁護活動にかかる弁護士費用相場
弁護人が事件を担当することになると、解決のための費用がかかります。示談には金銭が必要になりますし、示談をする弁護士の費用も必要になります。

こちらも読まれています
示談金
示談には金銭が必要です。窃盗などの財産犯であれば、被害者の損害を金銭によって原状回復させるのと同様の効果が望めます。傷害罪では治療費などの負担とは別に、慰謝料を含めて損害に対する金銭的賠償をすることになります。
生じた損害は示談金で賠償を
傷害罪における示談金としては、まず、治療にかかった費用は実費として支払うべきです。また、暴行時に他の被害が出ることも考えられます。たとえば顔を殴って怪我をさせた際に眼鏡も損壊させた場合などです。このようなケースでは眼鏡を壊した器物損壊罪(刑法261条)は傷害罪に吸収される(吸収一罪)と考えるのが一般的であり、傷害罪だけで処罰されます。しかし、実際には被告人の行為で傷害以外の損害が生じているわけですから、その部分の賠償もしなければ被害者の感情に配慮しているとは言えませんし、示談も成立しないでしょう。
慰謝料は示談金の一部
実費以外にも慰謝料が必要です。負わせた怪我の痛みは金銭によってなくなるわけではありませんが、怪我という身体への損害、それによって受けた精神的損害を金銭で賠償する必要があります。その意味から慰謝料は示談金の一部であると言えます。
慰謝料の相場は?
被疑者・被告人にすれば慰謝料の相場があれば知りたいことでしょう。しかし、傷害事件と一口に言っても程度は様々です。もう少しで死に至るような重大な障害から、2週間程度で完治する創傷でも一律に傷害罪です(あまりに軽度であれば暴行罪にとどまることはあります)。また、被害者感情にしても、被害者に何の落ち度もないのに一方的に暴行を受けた場合と、被害者による挑発のような行為があった場合では状況は違ってきます。そうした事情を総合的に判断して、被害者が被疑者・被告人の処罰を望まないというレベルの金額が相場と言えるかもしれません。
弁護士費用
示談をするには弁護士の力が必要です。被疑者の親族が被害者と示談交渉をしようと思っても、被害者は自分の住所など連絡先を知られたくないと考える場合が多いでしょうから交渉のテーブルにつくことさえ困難な状況が予想されます。そうなると弁護士に依頼するのが示談を成立させるには早道と言えそうです。
相談料
弁護士への相談料は、最近は初回無料としていることが多いようです。2回目以降は1回5000円程度が相場と言えます。
接見費用
被疑者・被告人との接見の場合、勾留場所まで行く必要があります。交通費は別として、勾留場所との距離にもよりますが1回3万円前後はかかるのが通常です。
着手金
弁護士が事件を担当する場合、依頼人は着手金を支払うことになります。刑事事件では自白している事件であれば事実関係を争うことがありませんが、罪を認めない否認事件では不起訴や無罪判決を目指すことになり、事実関係からして争うことになります。そのため、否認事件は一般的には高くなります。弁護士にもよりますが、通常の自白事件なら20〜30万円程度、否認事件なら30〜50万円程度でしょう。
自白事件の成功報酬
自白事件であっても弁護士の活動によって起訴猶予、略式命令、執行猶予付き判決、保釈許可決定、勾留に対する準抗告が認められるなどで被疑者・被告人にとって利益になることがあります。その場合には成功報酬を支払うことになります。事件や弁護士にもよりますが起訴猶予や微罪事件が10〜30万円程度、それ以外は20万円以下が相場と言えるのではないでしょうか。
示談が成功した場合や、求刑より言い渡された刑が軽い場合にも成功報酬は必要となるのが普通です。執行猶予については平成28年6月から始まった刑の一部執行猶予制度(懲役や禁錮刑を一定の期間受刑し、残りの刑期を執行猶予とする制度)も成功報酬が必要と考えた方がいいでしょう。
否認事件の成功報酬
否認事件では無罪判決を得ることが可能です。その場合には事実関係を争い、時間と手間をかけて争いますから、当然、成功報酬は高く設定されます。30〜50万円程度は必要でしょう。もちろん自白事件でも無罪判決の可能性はあります(ウソの自白をした場合等)し、自白事件の方が無罪判決の獲得は難しいですから、少なくとも否認事件での無罪判決と同程度の成功報酬は必要になります。なお、否認事件でも不起訴、執行猶予付き判決などでの成功報酬は必要になると考えるべきでしょう。
実費
弁護士が活動にあたって実際に経費としてかけた分は依頼人に請求されます。接見するための交通費や、通常の通信費などです。
日当
出頭したり、出張したりした際の日当が必要になります。概ね1回で3万円前後でしょう。また着手金を支払わずに、実際にかかった日数、時間によって支払額を決定する「タイムチャージ」という方式で支払う方法もあります。着手金で一律に支払うのではなく、かかった時間だけ支払うというものですが、大きな事件になると日数がかかり着手金方式より多く支払わなければならないということも考えられます。
傷害事件で弁護士に依頼するメリット
傷害事件では弁護士がつくことで様々なメリットがあります。
示談交渉による問題解決
身柄の拘束を解くため、あるいは量刑判断などで示談が成立しているかどうかは大きなポイントになります。
示談で起訴を免れる場合も
刑事上の責任は個人間の交渉で排除できませんから、当事者の合意で有罪を無罪にすることはできません。あくまでも示談の結果によって訴訟法上の効果が出たり、裁判所の量刑判断に影響が出るだけです。しかし、検察官が起訴するかどうかの判断において示談が成立していれば被害者がもう処罰を望んでおらず、損害の賠償も済んでいると判断しますから、公判請求の必要は無いとして起訴猶予にする可能性はあります。その意味で示談が成立しているかどうかは被疑者にとって大きな違いがあります。
示談で量刑判断も変わる
起訴された場合でも、裁判所は量刑判断においては情状面を考慮しますので、示談の成否は大きく影響します。示談を拒否して厳しい処罰感情を明らかにすれば、厳しい量刑が出やすいでしょう。逆に示談が成立していれば被害者は厳しい処分は望んでいないと判断され、厳しくない量刑となる可能性はあります。
外部への連絡・説明
逮捕され、身柄を拘束されている被疑者は外部との連絡を取る手段を持っていません。そこで弁護士が重要な役割を果たすことになります。
外部連絡は弁護士のみ可能
逮捕されると被疑者は外部と電話やメールなど、一切の連絡手段を使うことができなくなります。家族についても、勾留されるまでは原則として接見できません。そのような状況で被疑者と連絡を取れるのは弁護士だけです。被疑者の状態を家族や会社に性格に伝えることができ、外部との唯一の窓口として機能します。
手続きの見通しなど説明が可能
家族や会社の関係者が突然の逮捕で、どのような手続きが進むのかも分からない状況の中、弁護士は刑事訴訟法、刑事訴訟規則に基づく手続きの流れを熟知していますから、その後のことを予測することができます。身柄の拘束を解くためにどのタイミングで何をすればいいか、家族や会社はどう協力すべきか、適切にアドバイスをして被疑者とその関係者のために力になることができます。
処罰の軽減、回避につながる弁護活動
弁護士は身柄の拘束を早く解くこと、処罰を軽減したり回避するための活動を行います。
示談交渉
弁護士が行う活動で最も重要なのが示談交渉でしょう。被害者に謝罪し、損害を賠償することで被害者感情をやわらげ、起訴猶予や略式命令等で事件を終結させることで被疑者の期待に応えることができます。仮に起訴されても示談が成立していれば実刑判決のところが執行猶予付判決に、懲役刑が罰金刑にといった減軽が期待できます。
微罪処分なども
逮捕直後に依頼をする場合、弁護士自ら司法警察員に検察官送致をせずに微罪処分とすることを働きかけ、送致されても検察官に勾留請求をしないように働きかけることが期待できます
刑事事件では被疑者は外部との連絡を断たれ、身柄拘束からの解放のための活動や外部との連絡ができるのは弁護士だけです。特に逮捕後、72時間で手続きは大きく進みますから、迅速な対応が必要となります。家族や友人が逮捕された時には、すぐに弁護士に相談、依頼をすべきでしょう。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

「迷惑防止条例」とは?~痴漢などの犯罪に刑罰を与える各地の条例~
この記事で分かること 「迷惑防止条例」とは?東京都の「迷惑防止条例」による痴漢の規定「...
-

性犯罪で最も重い「強制性交等罪」(1)~「強姦罪」から改正~
この記事で分かること 「強姦罪」から「強制性交等罪」へ性犯罪の厳罰化が進む「非親告罪」...
-

この記事で分かること 強盗罪の定義とは?強盗罪は非常に重い刑罰が科せられる強盗が絡む他...
-

覚せい剤、大麻、薬物犯罪で逮捕されたら?弁護士の費用相場についても解説
この記事で分かること 覚せい剤・大麻などの薬物犯罪で身近な人が逮捕された場合逮捕される...
-

未成年犯罪は弁護士へすぐ相談!子どもの人生・将来を救う弁護活動と少年法のポイント
この記事で分かること 少年事件で身近な人が逮捕された場合少年事件の逮捕からの流れ少年事...
-

暴行罪で逮捕されたら弁護士に相談!示談交渉のポイントと弁護士費用相場
この記事で分かること 暴行事件で身近な人が逮捕された場合暴行罪で逮捕された後の流れ暴行...
-

万引き、窃盗で捕まったら弁護士は必要?示談交渉のポイントと示談金の相場
この記事で分かること 万引き・窃盗で身近な人が逮捕された場合窃盗罪、どこから着手か万引...
-

援助交際、児童買春で捕まったら弁護士に相談!示談交渉のポイントと慰謝料の相場
この記事で分かること 援助交際、児童買春で身近な人が逮捕された場合援助交際、児童買春な...