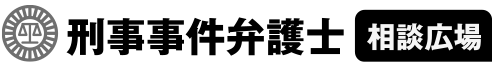留置場(留置所)の生活の実態!食事や生活のパターンから裏技差し入れまで解説!
- 2025年1月20日
- 473,330 view
- 刑事事件の基礎知識
- 刑事事件弁護士相談広場
-
- 相談料
- 初回無料
※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。
-
- 土日
対応 - 可能
- 土日
-
- 夜間
対応 - 可能
- 夜間
-
- 夜間
対応 - 全国対応
- 夜間

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません
今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります!
留置場(留置所)での生活は?

刑事事件の被疑者として逮捕された時、たいていの場合は警察に連行され、写真撮影や指紋採取をされた後に最初の取調べを受け、留置場で身柄の拘束を受けることになります。
留置場(留置所)とは各都道府県の警察に設置されている留置施設のことで、以下の記事で詳しく解説していますので詳細を知らない方は合わせて目を通しておいて下さい。

こちらも読まれています
留置場は世間一般ではブタ箱とも呼ばれるためにイメージは悪いのですが、近年は被疑者や被告人の人権に対する配慮や、過去の警察による違法な取調べ問題を払拭するために、さまざまな取り組みが行われているようです。
そのため、身柄の拘束を受け移動の自由は制限されて決して快適とは言えないものの、健康状態にも気を遣われるために、収容される人がきちんと生活ができるように整えられた施設となっています。なお留置場とは、俗にトラ箱と呼ばれる警察の保護室、管轄が法務省である拘置所とは違いますので、混同して間違わないようにしましょう。
保護室は留置場と同じく警察の施設ですが、泥酔者などを保護して一晩寝かせておくような場所で、拘置所とは法務省の管轄となり、原則として勾留が認められた被疑者や検察によって起訴された被告人が送られる場所です。

こちらも読まれています
定められた通りの生活
刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった人は、逮捕の有効期限である警察での48時間と、検察に送られてからの24時間、合計72時間は留置場で過ごすことになります。
しかし現実的には、勾留が決定されたら送られるべき拘置所の数が不足しているなどの理由から、勾留期間の10日間と勾留延長期間の10日間、合わせて20日間も留置場で収容されたままになるケースがほとんどです。その結果、留置場では23日間の長期にわたる生活が続くと考えてよいでしょう。そして留置場では、定められた通りの時間に合わせた生活となります。
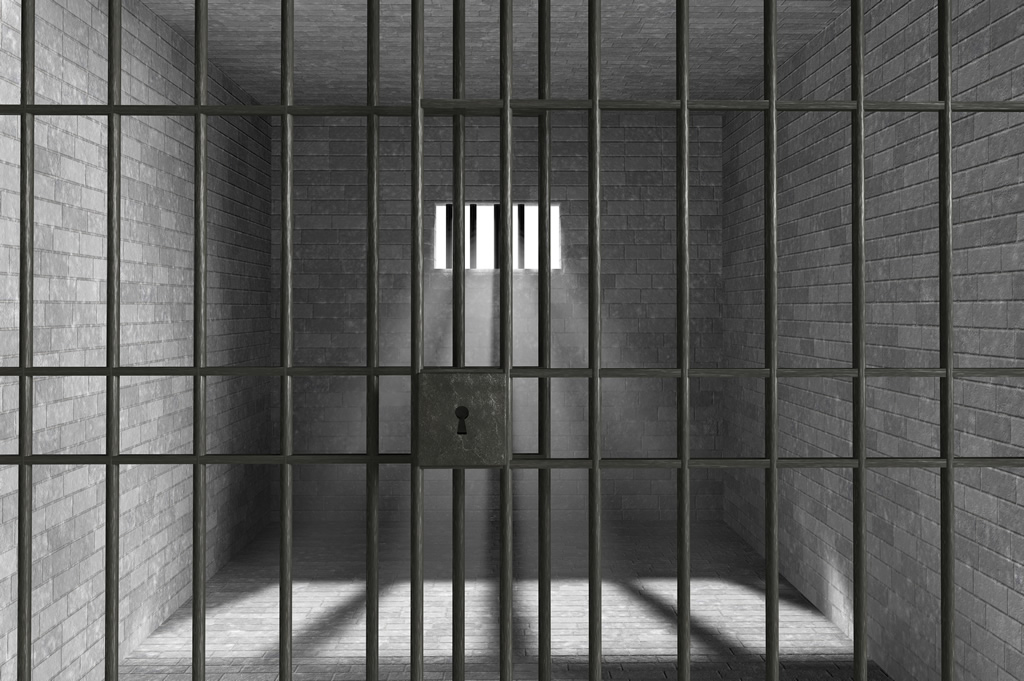
こちらも読まれています
都道府県や留置場によって違いがあるようですが、基本的には7時に起床し、洗面、点呼を終えて8時に朝食、12時に昼食、13時に運動、18時に夕食と、決められている時間通りの行動をし、夜は21時に就寝するという、ある意味規則正しい生活を送ることになります。
食事は朝、昼、夜の3回ありますが、入浴は冬であれば週に1度、夏は週に2度と、きれい好きな人には少し辛い環境かもしれません。そして夜の就寝時間が早い割には、病院のように消灯することはなく、灯りは点いたままになりますので、神経質な人は眠れないこともあるといいます。しかし案外、規則正しい生活に慣れてしまって、健康になって留置場を出る、というケースも少なくないようです。
留置場(留置所)での食事事情
刑事事件の犯人が食べされられる、いわゆる臭いメシというのは、刑務所や拘置所で食べる食事のことを指し、留置場で食べる食事ではありません。
とは言え、逮捕されて連行されてしまったからには、ある程度の覚悟を持っているでしょうし、家族や友人・知人が逮捕されてしまった場合には、きちんと食事を与えられているのか心配になることでしょう。
しかし、留置場に身柄を拘束されている段階ではまだ被疑者、あるいは被告人という立場であり、裁判などで有罪と決まったわけではないので、留置場での食事は臭いメシと揶揄されるようなものではないのです。
近年では刑務所や拘置所の食事事情も改善され、決して臭いわけではないと思いますが、刑に服している時の食事の味は、決して美味しいものではないのでしょう。
警察署に調理施設はない
留置場で出される食事は、多くの場合は警察署の近くの弁当屋、あるいはパン屋などから調達しているようで、予算は地域や警察署によって差があるようですが、1食あたり300円~400円くらいだと言われています。
外注の食事ということは、当然調理されてから時間が経っているため、コンビニエンスストアの弁当のように電子レンジで温めることもありませんから、出される食事はどこの留置場でも冷めていることが多いのです。
一方、拘置所や刑務所では、所内で食事が調理されるため温かいものが食べられます。しかし留置場でも、地域よってはインスタントのみそ汁がつくこともありますので、常に冷たい食事ばかりとは限らず、警察庁が作成した「警察の留置業務」というパンフレットによると、「国民生活の実情等を勘案して十分なものであるように、資格のある栄養士が定期的に栄養のバランスをチェックしています」だそうです。
もっとも予算が限られているという理由もあり、イメージとしてはコンビニエンスストアの、のり弁当をさらに貧弱にしたような弁当を想像すれば間違いないでしょう。しかも留置場は基本的に起訴されるまで被疑者を拘束する場所という原則があるため、収容している人の長期滞在を前提にしていないので、メニューが豊富にあるとは言えない状況です。
同じメニューが一週間のサイクルで繰り返されることがあるのですが、多くの被疑者は勾留期間を含めた最長23日間で釈放されますので、気がつかない人もいるかもしれません。しかし再逮捕などの諸事情で1カ月以上にわたり留置場に身柄が拘束されていると、繰り返されるワンパターンのメニューに嫌気がさすこともあるでしょう。

こちらも読まれています
食事の欲求を満たす裏技がある?
留置場で提供される三度の食事は、基本的にすべて無料です。収容されている人の食事代は、留置場内の電気や水道といった光熱費と共に警察署の運営費用として計上されているのです。
つまりは税金で賄われているわけですが、被疑者や被告人の身柄を拘束しておくのはあくまでも警察や検察の都合であり、好き好んで留置場に入っているわけではありませんので、食事代を請求しないのは当然のことでしょう。
ただし、留置場の食事メニューは貧弱な上、量が物足りない人もいるでしょうし、好きな時に好きなだけいろんな食事をしていた人には不満が残ります。そういう人には「自弁」というシステムがあります。
これは、自分でお金を支払って別メニューの弁当を買えるというものです。どういう注文ができるのか、どのようなメニューがあるのかは留置場を管轄する警察署によって違いますが、日替わり弁当やカレーライスなどはどこの警察署に定番としてあるはずです。1食あたりの単価は400円~500円ほどで、前日に留置場内の警察官が注文を取るシステムが多いようです。
食事を注文することができると言われても、逮捕直後に食事に不満があることを示すのは気が引けてしまう人もいるかもしれませんが、留置場内では何の楽しみもなく、食事くらいは遠慮せずに頼んでみるのもよいでしょう。
基本的に「自弁」は昼食だけで頼めるのですが、他にも週に1回100円でお菓子が買えたり、夕食時にパックのジュースやコーヒーが買えたりするなど、警察署ごとに食事以外の「自弁」制度もあるようです。しかしこのような「自弁」は、平日のみ可能で土日は休みという警察署がほとんどです。
また「自弁」を頼んでも、通常提供される昼食がなくなるわけではなく、2食分を食べることになるケースもあります。食べきれない場合は残しても構いませんが、もったいないからといって同じ部屋にいる他の人に食べ物を分けることは禁止されています。
これはシャリあげと呼ばれる、弱い人から食べ物を取り上げてしまういじめ行為と区別ができなくなるからで、留置場に限らず、刑事施設内で収容者同士の食べ物のやりとりは禁止事項となっています。
留置場(留置所)でもお金は必要
留置場内には、自分の財布や現金の持込みはできません。被疑者や被告人が留置場に入る際、靴や留置場内で着ることができない衣類などと一緒に警察に預けることになります。留置場の部屋には衣類以外は持ち込むことができず、就寝時には係員に預けなければいけません。
これらのルールは施設によって違いがありますが、不便な生活を強いられることは間違いありません。携帯電話やスマートフォンなどは証拠品として押収されていることが多く、財布も預けることになりますが、その際に持っていた現金は領置金と呼ばれ、そこから自分で注文する「自弁」の代金は差し引かれるシステムとなっています。
お金はいくら必要か?
「自弁」だけではなく、留置場内では歯磨きや歯ブラシなどのアメニティグッズを買う必要があり、また切手や便箋も買うことが可能ですが、これらの代金はすべて領置金から差し引かれます。
もし家族や友人・知人が逮捕されて留置場に収容されてしまった場合、現金を差し入れすると大変喜ばれるでしょう。
もっとも最長の23日間の勾留期間に必要なお金は、毎日「自弁」を食べても1万円~2万円程度で、他の切手などの買い物をしたとしても領置金は3万円もあれば十分と考えられます。
もうひとつの大事な物「ノート」
留置場では外部と連絡を取る手段が限られるため、切手や便箋、封筒を買う人が多いのですが、日々の日記を書くノートも買うべきだということを覚えておきましょう。
普段日記を書く習慣がなくても、必ずノートを買って、その日に何があったのか、取調べでは何を聞かれたのか、どう答えたのかを、すべて書き記しておくことをお勧めします。
後の裁判においては、当初の取調べの記録である供述調書が重要視されますが、こちらが何をどう答えたのかを弁護士と共有する手段は、口述あるいはこのノートしかありませんので、裁判対策を立てるうえで記録を残しておくことは非常に重要なのです。
それこそ何を食べたのかを記しておいても良いので、毎日何をしたのかをノートに、あるいは便箋に残しておきましょう。
留置場(留置所)には弁護士を通じて差し入れをしよう
留置場での食事やお金の事情は以上の通りですが、逮捕された直後の被疑者は、なかなかここまで気が回りません。
逮捕されてしまったことのショックと、気が動転してしまうことにより、知識として知っていてもなかなか実行に移すことが難しいと思われます。そして家族や友人・知人が面会しようとしても、なかなか許可は出してくれません。
そういう時には、原則としていつでも被疑者と面会ができる弁護士を通じて、伝言や差し入れをお願いするようにしましょう。家族や友人・知人が気にかけてくれているという事実だけで、被疑者は心強いものです。
-
- 相談料
- 初回無料
※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。
-
- 土日
対応 - 可能
- 土日
-
- 夜間
対応 - 可能
- 夜間
-
- 夜間
対応 - 全国対応
- 夜間

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません
今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります!
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

この記事で分かること 留置場(留置所)に入るまでの手続き被疑者が拒否できること、できな...
-

留置場(留置所)とは?施設の詳細から期間、保護室との違いまで徹底解説!
この記事で分かること 留置場(留置所)とは?留置場(留置所)の施設はどのようなもの?留...
-

この記事で分かること 受刑者の自由を制限する「自由刑」「懲役」「禁錮」「拘留」の違い「...
-

この記事で分かること 労役場における「労役場留置」とは?「労役場留置」日当の計算方法は...
-

この記事で分かること 「労役場留置」とは「労役場留置」という刑罰はない?罰金刑や科料に...
-

この記事で分かること 逮捕による身柄拘束は必ずしも必要ではない!身柄の拘束を伴わない「...
-

この記事で分かること 拘置支所とは?拘置所と拘置支所との違いは?拘置支所と刑務所の違い...
-

この記事で分かること 拘置所とは?拘置所はいつも満員?拘置所に移送されない他の理由弁護...
-

この記事で分かること 逮捕後、取調べの前に行われる手続き写真撮影・指紋採取は強制科学的...
-

弁解録取書と身上調書とは?逮捕後、警察の捜査官が作成する書類
この記事で分かること 被疑者の逮捕後に作成される書類とは?逮捕後に作成される書類「弁解...