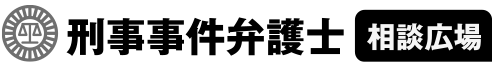執行猶予とは?認められる条件や前科の有無について分かりやすく解説!
- 2025年1月20日
- 274,643 view
- 刑事事件の基礎知識
- 刑事事件弁護士相談広場
-
- 相談料
- 初回無料
※ご本人様・ご家族以外の方、被害者の方は60分1.1万円(税込)となります。
-
- 土日
対応 - 可能
- 土日
-
- 夜間
対応 - 可能
- 夜間
-
- 夜間
対応 - 全国対応
- 夜間

※ご相談の内容は弁護士法の守秘義務に基づき、決して口外されません
今すぐ相談可能な弁護士事務所へと繋がります!
執行猶予とは?
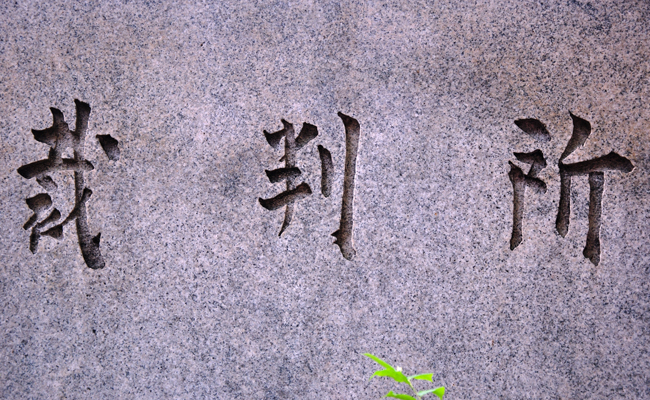
執行猶予とは、文字通り刑の執行に対し一定期間の猶予を与える事を指します。
たとえば『懲役1年 執行猶予2年』という判決を言い渡された場合。2年間一切の罪を犯すことなく過ごした場合、刑罰権が無効となり懲役に行く必要がなくなります。
この場合は収監されることなく社会に復帰ができますが、前科はつきますし、期間中にまた罪を犯せば取り消されてしまいます。
また執行猶予は『前科がなく』、『3年以下の懲役または禁固、または50万以下の罰金刑』の時に言い渡されるので、過去に前科があったり罪の内容が重い場合は執行猶予が言い渡されない場合もあります。
「執行猶予」の意味(意義)は?
刑事事件で被疑者として逮捕されてしまった場合、途中に微罪処分や不起訴処分、あるいは略式処分といった手続きの終わり方ではなく、検察によって起訴されてしまうと判決が下されるまで事件は終わりません。
刑事事件の裁判の判決は、まず無罪か有罪かが裁判官から言い渡されますが、無罪の場合、被告人は無罪と明確に宣告されます。
それに対して有罪判決の場合は、「被告人を○年の懲役に処する」などと、いきなり刑罰が言い渡されます。
こうして裁判所で下される判決が刑事事件の最終結論になりますが、判決に不服がある場合には控訴や上告ができますが、その場合にも最終的には裁判官が判決を下して全てが決められます。
この際、言い渡された判決に、「執行猶予」が付けられることがあります。
ニュースでもよく聞くため、言葉だけは知っている方も多いと思いますが、「執行猶予」にはさまざまな条件や守らなければならないことがあり、刑事裁判の当事者となってしまい、判決を下された場合には、注意しておかなければならないことが多いのです。
本項では、「執行猶予」について説明します。
「執行猶予」は裁判の判決と同時に言い渡される
「執行猶予」は、刑事事件裁判の判決言い渡しの際に、刑罰の言い渡しと同時に裁判官から言い渡されます。
これは刑事訴訟法第233条に規定されています。
刑事訴訟法
第三百三十三条 被告事件について犯罪の証明があつたときは、第三百三十四条の場合を除いては、判決で刑の言渡をしなければならない。
○2 刑の執行猶予は、刑の言渡しと同時に、判決でその言渡しをしなければならない。猶予の期間中保護観察に付する場合も、同様とする
「執行猶予」はあくまでも有罪判決に付けられるものであり、刑務所には入らなくて済みますが、前科となるものです。
「執行猶予」はなぜ付けられるのか?
ニュースなどで伝えられる「執行猶予」という言葉のイメージには、犯罪の内容が軽かったからとか、初犯で深く反省しているから、情状酌量によって刑が軽くなった、というものがあるかもしれませんが、これらの要素があるにせよ、「執行猶予」の意義はこういうものではありません。
「執行猶予」の制度が初めて日本に採り入れられたのは1905(明治38)年ですが、その昔は刑罰には、見せしめや、被害者と相応の苦痛を与えるという考え方が強かったのです。
しかし一方で、比較的軽い犯罪に対して実刑を与えることは、犯人が過ちを十分に反省し、更生したうえで社会の役に立つ機会を奪っているのではないかという考え方が主流となってきました。
いわゆる刑務所帰りでは世間の目も厳しく、せっかく刑期を終えて出所してきても、一般的な社会生活を営むのは難しいのが現実で、自暴自棄になる人もいるかもしれません。
そのため、有罪判決を受けても一定期間何事もなく過ごせば、刑の執行から免れるという「執行猶予」付きの判決が増えていったのです。

こちらも読まれています
執行猶予は前科になる
執行猶予がつくと、実際に刑務所に行く必要がなくなるので、喜ぶ方が多いです。確かに、実刑になるより執行猶予がついた方が、被告人にとって好ましいことは明らかです。実刑とは、執行猶予がつかずに実際に刑務所に行って服役しなければならないことです。
ただ、執行猶予は「有罪判決」であり、「無罪」になったのとは異なります。最初にチラッと触れた通り執行猶予も「前科」となります。そこで、執行猶予判決を受けた場合にも、検察庁の犯罪歴データベースに登録されてしまいますし、その記録は本人が戸籍から抹消されるまで一生残ります。
次に何か犯罪行為を行ったときや疑われたときには、前科照会をされて「過去に執行猶予判決を受けた人」であると判明してしまいます。一般的に、1度目は執行猶予がついても2度目の猶予が認められないことが多いので、2回目に犯罪行為に及んだら、今度は執行猶予がつかずに実刑になってしまう可能性が高まります。
「懲役〇年執行猶予△年」の意味
執行猶予判決を受けるときには、判決で「懲役〇年執行猶予△年」などと言い渡されます。一般の方にはわかりにくい表現なので、簡単にその意味を説明します。「懲役〇年執行猶予△年」という場合、〇年は本来受けるべき懲役の年数、△年は刑の執行を猶予される年数となります。
例として「懲役3年執行猶予5年」のケースを考えてみましょう。この場合、刑罰としては「懲役3年」です。そこで、執行猶予がつかなければ、3年間刑務所に行って労働をしなければなりません。ところが「執行猶予5年」がついているので、5年間執行を猶予されます。そこで、判決後5年間犯罪行為をしなければ、3年の懲役刑はなかったことになり、最終的に刑務所に行かなくても済みます。
この読み方は「禁固」の場合も同じで「禁固〇年執行猶予△年」であれば、本来なら〇年刑務所で拘束されないといけないところ、△年まじめに暮らしていたら禁固刑を受けずに済むようになります。
「執行猶予」は刑法25条~27条に規定
刑事事件の裁判で下される有罪判決が、懲役や禁錮といった自由刑、あるいは罰金刑であった場合、裁判官が「被告人を懲役○年に処す」と言った後、「ただし、刑の執行を○年猶予する」と付け加えれば、被告人は「執行猶予」という処分になります。
「執行猶予」とは、判決は有罪となりますが、刑罰が即座に執行されずに、一定期間刑の執行が猶予される措置です。
なお、法律上は罰金刑でも「執行猶予」が付けられますが、実際にはほぼありません。
「執行猶予」の法的根拠は刑法に定められている
なお、「執行猶予」は刑法の第25条から27条にわたって定められていますので、ここにまとめて紹介しておきます。
なお、刑法27条に定められている(刑の一部の執行猶予)は、2016(平成28)年の改正によって新たに追加されたものです。
刑法について過去に学んだことがある方も、この際、確認しておくことをお勧めします。
(刑の全部の執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の全部の執行猶予中の保護観察)
第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
2 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
3 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)
第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
(刑の一部の執行猶予)
第二十七条の二 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、一年以上五年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
三 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前項の規定によりその一部の執行を猶予された刑については、そのうち執行が猶予されなかった部分の期間を執行し、当該部分の期間の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から、その猶予の期間を起算する。
3 前項の規定にかかわらず、その刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時において他に執行すべき懲役又は禁錮があるときは、第一項の規定による猶予の期間は、その執行すべき懲役若しくは禁錮の執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から起算する。
「執行猶予」が付けられる条件
上記の刑法第25条に定められているように、「執行猶予」は3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時、1年以上5年以下の「執行猶予」期間が付けられることがあります。
一般的な言葉の解釈では、「猶予」とは当面の間それを行わなくてもよいということですが、この場合は、猶予期間が経過したら刑罰が執行されるわけではありません。
この「執行猶予」期間中に、新たに刑事事件を引き起こしたりせず、平穏な社会生活を送っていれば、刑罰の執行どころか、言い渡された刑罰そのものが消滅するという制度なのです。
つまり、裁判で懲役や禁錮といった有罪判決を言い渡されても、「執行猶予」が付けば、刑務所に入れられることなく一般社会に戻れるのです。
形式上では、判決で言い渡された「執行猶予」の期間中に、他の罪を犯して逮捕されることがなければ、無罪判決と同じく何の刑罰も科せられなくなります。
執行猶予の最長期間はどれくらい?
執行猶予の最長期間は基本的には5年と言われています。
これは2018年11月に行われた元モーニング娘の吉澤ひとみさんの裁判での出来事が有名で、飲酒運転によって懲役2年、執行猶予5年の判決が下されました。
一般的には懲役刑の2倍の期間が執行猶予となるのですが、それを上回り、なおかつ最長期間である5年が言い渡された事からもその罪の大きさが分かります。
このケースでは高濃度のアルコールが検出された他、被害者の顔に消えない傷跡が残るほどの事故だった事が最長の執行猶予5年という判決に至った要因のようです。
執行猶予がつくケースと期間
では先程軽く触れましたが、執行猶予がつくのは具体的にどのようなケースで、どのくらいの「期間」になるのかについても押さえておきましょう。
執行猶予がつく犯罪の種類
まず、執行猶予がつく犯罪は、以下のように決められています。
- 3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑
執行猶予というと、「懲役刑」のイメージが強いのですが、実際には禁固刑や罰金刑でも執行猶予がつけられる可能性があります。ただし、実際には罰金刑で執行猶予がつけられることはほとんどありません。罰金刑の執行を猶予したとしても、本人が「罰金を払いたくないから罪を犯さないようにしよう」という抑止が働きにくいからです。また、罰金刑は本人の身柄拘束をせず、社会復帰を困難にする事情にもつながりにくいので、あえて猶予をつけて被告人にチャンスを与える必要がありません。
これに対し、禁固刑では、懲役刑と同様に執行猶予がつくケースが多いです。
執行猶予がつく犯罪の重さ
執行猶予をつけられるのは「3年以下」の懲役または禁固、「50万円以下」の罰金刑です。それを超える場合、執行猶予がつかず必ず実刑となります。
というのも、一定以上の重い犯罪の場合、本人を処罰する必要性が高いですし、更生させるためにも実刑を適用させる必要があります。また重大犯罪を犯しても執行猶予がつくということになると、社会において犯罪が横行してしまう可能性がありますし、国民の処罰感情の問題もあります。
たとえば殺人罪や強盗罪、放火罪や強制性交等罪などの重大な犯罪を犯した場合には、執行猶予はつかないと考えましょう。
執行猶予がつく期間
執行猶予がつく場合、期間が1年~5年となっています。執行猶予期間を1年より短くしたり5年を超えたりすることは認められません。ただ、1年~5年の間であれば、裁判所が自由に定めることができます。刑事事件を担当した裁判官の裁量によって、判決時に期間が決められます。
執行猶予期間の相場としては、もともとの刑期より長くなり、~2倍程度になることが多いです。たとえば、懲役1年6か月の場合、執行猶予が2~3年程度となります(もちろん、例外はあります)。執行猶予期間がもともとの刑期より短くなるケースはほとんどありません。
前科との関係
被告人に前科があると、執行猶予がつかない可能性が高くなります。執行猶予をつけられるのは、以下のようなケースに限られるからです。
- 以前に禁錮以上の刑に処せられていない
以前に一度も禁固刑や懲役刑を科されたことのない人であれば、執行猶予がつく可能性があります。罰金刑を受けていても大丈夫です。
- 以前に禁錮以上の刑に処せられたけれども、執行を終了した日や執行が免除された日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない
以前に禁固刑や懲役刑を受けているけれど、実刑になって刑期を終えた日や、執行猶予がついて猶予期間が終了した日から5年以内に禁固刑や懲役刑を受けていない人です。
- 以前に禁錮以上の刑で執行猶予判決を受けた人が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受けて、特に情状酌量すべき場合
以前に禁固刑や懲役刑で執行猶予判決を受けた人が、新たに1年以下の懲役や禁固刑に該当する罪を犯した場合で、特に情状酌量すべきケースでも、新たに執行猶予判決を受けられる可能性があります。ただし、保護観察がつけられた場合において、その期間内に罪を犯した場合には執行猶予がつきません。
「執行猶予」の実際の取り扱われ方
平成28年版犯罪白書によると、地方裁判所で行われた通常第一審における有期刑(懲役・禁錮)の科刑総数は51,658件で、うち30,974件の判決に「執行猶予」が付いています。
割合で見ると、約60%の判決に「執行猶予」が付けられていることになり、比較的高い割合であることが言えますが、総数が減少傾向にあるなかで、この割合はここ数年ほぼ横ばいとなっています。
刑事事件の被告人となってしまい裁判に臨むにおいて、量刑が3年以下の懲役に満たないと見越される時には、弁護士に相談して、何としても「執行猶予」付きの判決が下るようにするべきでしょう。
「執行猶予」は取り消されることがある
上記の刑法第26条、第26条2項、3項に定められているように「執行猶予」は取り消されることがあります。
「執行猶予」の期間中に、何らかの事件を起こして刑罰を受けた場合、この「執行猶予」は取り消されて、ただちに刑務所に収容されることがあります。
そして「執行猶予」中に起こした事件の判決は、「執行猶予」が付かない厳しい実刑判決となることが多いとされています。
あくまでも事件の内容や裁判所の判断によりますが、せっかく得た「執行猶予」を失うことのないよう、社会生活を送ることが必要となります。
交通事故には特に注意が必要

普通に社会生活を送っている多くの人は、警察の厄介になることなど、一生のうちで何回もあることではありません。
一般人の感覚でいえば、一度刑事事件を起こして1年から5年の間で言い渡された「執行猶予」期間は、もちろん事件については反省しているはずですから、無事に過ごせると考えがちです。
しかし、交通違反も刑事事件になるということを忘れてはいけません。
交通違反が行政罰、いわゆる青キップ程度であれば問題はないかもしれませんが、赤キップを切られるようなものは、刑事事件となり、「執行猶予」が取り消しになる可能性が出てきます。
実際には、余程悪質な違反でない限り、交通違反で即「執行猶予」取り消しになることは珍しいようですが、「執行猶予」期間中の人には、免許証を持っていても一切運転をしないという人も実在します。
また犯罪の中には、痴漢や薬物使用など常習性の高いものもあり、これらの犯罪は「執行猶予」期間中でも、再び同じ罪を犯す者が少なくありません。
「執行猶予」期間中に再び刑事事件を引き起こして逮捕され、起訴後に裁判となった場合、無罪になることはまずありません。
それどころか、「執行猶予」中の刑罰も加えられ、厳しい実刑判決となることが予想されます。
もともと「執行猶予」という制度は、罪を犯したからといって、すぐに刑務所へ入れて刑罰を科すのではなく、社会の中での更正を期待して自由を与える措置です。
せっかくの「執行猶予」を無駄にしないように、法律の専門家である弁護士とよく相談しながら、生活を送ることが必要となります。

こちらも読まれています
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

少年法改正|成年年齢引き下げにあわせ18歳・19歳は「特定少年」に
この記事で分かること 少年法とは少年法が改正される理由改正少年法で18歳・19歳の犯罪...
-

取り調べの流れとは?警察の取り調べはどのような感じで行われる?
この記事で分かること 刑事事件の取調べの前に刑事事件の取調べの雰囲気は?刑事事件の取調...
-

この記事で分かること 勾留前に裁判所で行う手続き~「勾留質問」とは国選弁護人の申請がで...
-

この記事で分かること 逮捕の期限は72時間検察が行う勾留とは勾留の期限は原則20日間 ...
-

不起訴とは?不起訴処分には種類があり前科はつかないが前歴が付く場合も
この記事で分かること 不起訴とは?不起訴処分の種類 不起訴処分の理由は、通知されない ...
-

仮釈放とは?仮釈放が認められる条件や満期釈放との違いについて解説
この記事で分かること 仮釈放とは仮釈放と釈放・保釈・執行猶予の違い仮釈放が認められるた...
-

この記事で分かること 勾留中に行われる「引き当たり」とは「引き当たり」はどのように行わ...
-

この記事で分かること 検事による取調べ、「検事調べ」とは「検事調べ」はどのように行われ...
-

この記事で分かること 逮捕と勾留の満期は23日間勾留決定までの流れ不起訴が決定されれば...
-

この記事で分かること 拘禁刑とは拘禁刑を新設する目的拘禁刑の新設でなにが変わる?「応報...