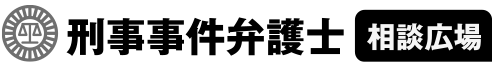刑事事件裁判の流れと登場人物について解説
- 2025年1月20日
- 37,630 view
- 10分でわかる刑事手続き
- 刑事事件弁護士相談広場

刑事裁判とは
刑事裁判とは、犯罪を犯した疑いのある人について、本当に犯罪行為をしたかどうかを審理し、有罪であれば刑罰を適用するための裁判です。審理の結果、犯罪行為をしていないことが明らかになれば無罪判決が下ります。
刑事裁判の登場人物
刑事裁判の登場人物は、「検察官」と「被告人」「弁護人」「裁判官」です。検察官が被告人を追及し、弁護人が被告人を擁護し、裁判官がそれらのやり取りを見て最終的な判断を下す、という構図です。
刑事裁判で決定すべき事項
刑事裁判で決める内容は「有罪か無罪か」「有罪ならどのような刑罰がふさわしいか」という問題です。損害賠償金などの金銭支払いや私的な権利義務の存否などについては判断しません。そういった事項を決定するのは民事裁判です。
刑事裁判と被害者
刑事裁判において、「被害者」は主要な登場人物ではありません。証人として登場することはあっても、当事者扱いではありません。ただし今は「被害者参加制度」が作られたため、一定の重大犯罪の刑事裁判では、被害者が検察官側の当事者に近いかたちで刑事裁判に参加できます。参加した被害者には、被告人に対する処分について意見を述べたり被告人や証人に尋問をしたりする権利が認められています。
刑事裁判と民事裁判との違い
刑事裁判と民事裁判の区別がわからない方もおられるので、ご説明します。民事裁判は、民間人同士の「権利義務」の存否や内容を決定する裁判です。たとえば「貸したお金を返してほしい」、「損害賠償金を支払ってほしい」、「賃貸物件から退去してほしい」などの請求は民事裁判で行います。刑事事件の被害者が加害者に慰謝料請求するときにも民事裁判を起こします。
民事裁判の登場人物は「原告」「被告」「裁判官」です。検察官のような国家権力は関与せず、民間人同士の争いとなります。刑事事件のように、検察官が一方的に被告人を追及し、被告人側が防御に徹する、という構図ではありません。原告が敗訴することもありますし、被告が原告を訴え返す「反訴」という手続きも認められています。
刑事裁判の種類によって流れが異なる
実は刑事裁判には、いくつかの種類があってそれぞれによって流れが異なります。
通常の刑事裁判
通常の刑事裁判は、原則的な刑事裁判です。たとえば交通事故の過失運転致死傷罪や暴行・傷害罪、強制わいせつ罪や覚せい剤取締法違反など、各種の犯罪で起訴されたときに適用されます。件数的にも非常に多数です。
裁判員裁判
裁判員裁判は、比較的最近になって導入された刑事裁判のかたちで、殺人や放火などの一定の重大犯罪に適用されるものです。国民から選ばれた「裁判員」が刑事裁判に参加して、検察官や弁護側による主張や立証内容を見聞きし、最終的に評議をして被告人を有罪にすべきか、またどのような罪を適用すべきかを判断します。
略式裁判
略式裁判は、100万円以下の罰金刑か科料の刑罰が適用される刑事事件において、書類上だけで簡易に行う刑事裁判です。科料とは10000円未満の金銭支払いの刑罰です。書類上のみの審理なので、被告人が裁判所に出廷する必要はありません。被告人の自宅に罰金の納付書が送られてくるので、支払をすれば刑を終えたことになります。
略式裁判が行われるには、被告人が罪を認めており、なおかつ被告人が略式裁判に同意した場合のみです。
以下で、上記のそれぞれの刑事裁判について、流れを詳しく説明していきます。
一般的な刑事裁判の流れ
一般的な刑事裁判の流れは、以下の通りです。
- 人定質問
- 起訴状朗読
- 黙秘権告知
- 罪状認否
- 冒頭陳述
- 検察官立証
- 弁護側立証
- 証人尋問
- 被告人質問
- 論告と弁論
- 判決言い渡し
- 控訴
以下でそれぞれのステップをみていきましょう。
被告人の在廷義務について
刑事裁判では、何度も「期日」が開廷されます。そして、その期日には必ず被告人が出廷しなければなりません。被告人が来なければ期日を開くことはできません。被告人が拘置所などに身柄拘束されていたら、被告人は強制的に裁判所に連れてこられますが、保釈されている場合や在宅の場合には、被告人が自ら裁判所に出廷しなければなりません。
もし来なかったら期日が開催されませんし、被告人が来ない日が続いたら、「勾引」という方法で無理矢理裁判所に連れてこられます。保釈されている場合には、保釈決定が取り消されて身柄拘束を受ける可能性があります。
「忘れていた」では済まされないので、被告人の立場になったら必ず定められた時間に裁判所に行きましょう。
刑事裁判の流れ
1. 人定質問
第一回期日に刑事裁判の開かれる法廷に行くと、まずは「人定質問(じんていしつもん)」という手続きから始まります。
人定質問とは、本当にそこにいるのが被告人本人かどうかを確認する手続きです。刑事裁判では有罪判決を下して刑罰を与える可能性もあるものですから、もし人違いだったら大変な人権侵害です。そこで、まずは間違いではないか確認します。
人定質問では、裁判官から被告人に対し、氏名や職業、生年月日などを聞かれます。たいていは被告人が答えてスムーズに終わります。
2. 起訴状朗読
次に検察官が「起訴状」を読み上げます。起訴状には、被告人が犯したと疑われている犯罪事実が端的に書かれています。たとえば「被告人は平成〇年〇月〇日午後〇〇頃、〇〇宅に忍び込み、現金〇〇万円を窃取してものである」などです。このように起訴状を読み上げることを「起訴状朗読(きそじょうろうどく)」と言います。
3. 黙秘権告知
検察官は起訴状を読み上げると、被告人に対して「黙秘権」を告知します。黙秘権とは、被告人が何も言わずに黙っていても良い権利です。黙秘権は権利なので、黙っていることによって不利益に評価されることはありません。
4. 罪状認否
その上で、被告人に対して「罪を認めるかどうか」尋ねます。被告人が認めている場合「やりました」「その通りです」などと答えます。ときには「やったのはやったけれど、〇〇の部分は少し違います」などと認否する被告人もいます。
否認している事件では「違います」「やってません」などと答えます。また被告人には黙秘権があるので、黙って答えなくてもかまいません。被告人が黙っていて弁護人が「黙秘権を行使します」などと言うケースもあります。
このように、被告人が罪を認めるかどうか答える手続きを「罪状認否(ざいじょうにんぴ)」と言います。
5. 冒頭陳述
被告人が罪を認めても認めなくても、検察官は「冒頭陳述」を行います。冒頭陳述とは、この事件について検察官が考えるストーリーです。起訴状に書かれた犯罪事実は、犯罪に関してごく簡単に書かれたものです。冒頭陳述の場合、被告人の生い立ちから前科、犯罪に至る経緯、動機、犯行の様子などが長々と書かれています。検察官が裁判官に対し「このような人がこういった経緯で犯罪行為を行いました」とわかりやすく報告するための手続きです。
一般的な認めの刑事事件において弁護側が冒頭陳述を行うことは少ないですが、否認事件の場合、弁護側も冒頭陳述を行うことがあります。その場合には、弁護側が考えるストーリーを時系列でまとめて冒頭陳述で明らかにします。
6. 検察官立証
次に検察官側が立証を行います。警察や検察の各種の供述調書や実況見分調書、被害届やその他の資料を提出します。
7. 弁護側立証
弁護人側も、提出すべき証拠があれば提出します。
8. 証人尋問
立証の一方法として、尋問も重要です。尋問を行うときには、まずは検察官側や弁護側の証人で、罪を犯したかどうかに関わる事実を証言する人を取り調べます。被害者が尋問を受けるときには、この段階で検察側証人として登場します。
証人尋問の際には、まずは証人申請した側から主尋問があり、次に相手方から反対尋問があり、最終的に裁判官から質問が行われる流れとなります。
罪体に関する証人の取り調べが終わったら、情状証人の取り調べがあります。情状証人は、罪を犯したかどうかではなく、被告人が有罪であることを前提として、罪を軽くすべき事情があることを証言する人です。
9. 被告人質問
最後に被告人質問が行われます。被告人質問では、罪体に関する質問と情状に関する質問の両方が行われます。
10. 論告と弁論
このようにしてすべての主張と証拠の取り調べが終了したら、検察側の論告と弁護側の弁論が行われます。論告とは、被告人の罪を暴き、いかに被告人が悪質であるかを述べて厳罰を適用すべきとする検察側の意見です。最終的に、求めるべき刑罰も明らかにされます。
一方弁論は、弁護側が述べる意見であり、被告人には汲むべき事情があるのでできるだけ刑罰を軽くすべき、あるいは罪を犯していないので無罪とすべき、と主張するものです。
論告と弁論が終わったら、刑事裁判は結審して判決言い渡し日が指定されます。
11. 判決言い渡し
判決言い渡し日には、必ず被告人は出廷しなければなりません。民事裁判の判決のように、誰も出席しないで裁判官が結論だけ述べる、という簡単な手続きではありません。
被告人が出席すると、裁判官から被告人に対して直接判決が告げられ、その後理由の要旨が述べられます。裁判官が「なぜその刑罰を適用したのか」を説明して、被告人に今後どのようになってほしいのか、どのようなことに気をつけてほしいかなどの希望を告げるケースも多々あります。
12. 控訴
一審判決を受けた場合、不服があれば控訴することも可能です。控訴した場合には高等裁判所に審理が移行します。控訴しなければ1審判決が確定します。
期間
通常の刑事裁判にかかる期間は、認めの事件か否認事件かで大きく異なります。認めの場合、起訴されてから2~3か月で終わることが多いです。一方否認事件の場合には半年~1年以上かかるケースも珍しくありません。
裁判員裁判の流れ
次に裁判員裁判の手続きの流れを簡単にみていきましょう。
- 公判前整理手続き
- 公判
- 評議
- 判決
- 控訴
裁判員裁判の流れについて
1. 公判前整理手続き
裁判員裁判の事件では、裁判が始まる前に「公判前整理手続き」という手続きが開かれます。これは、裁判官と検察官、弁護人が集まって裁判の準備を行う手続きです。その事件における争点を明らかにして、検察官と弁護側がどのような証拠をもって立証するのかなどの予定を開示します。
このように、予想される争点と提出される証拠を明らかにしておくことにより、実際の公判の場で行う内容が明確になり、短期集中で終わらせることが可能となります。
公判前整理手続きには、被告人本人は参加する必要はありません。ただどのような形で争点整理や証拠開示が行われるかは、被告人にとって死活問題です。公判準備手続きに臨むにあたり、しっかり弁護人と相談し、状況の説明を受けながら不利にならないように進めてもらう必要があります。
2. 公判
裁判員裁判の公判には、検察官、被告人、弁護人、裁判官以外にも、国民から選ばれた裁判員が参加します。裁判官は3名、裁判員は6名です。公判が始まったら、通常の刑事裁判と同様に起訴状朗読や冒頭陳述などが行われます。
そして事前に公判前整理手続きで取り決めておいた通り、弁護側と検察側が主張と立証を行っていき、検察側と弁護側がそれぞれ論告求刑と弁論を行い、結審します。
裁判員裁判の公判は、基本的に「連日開廷」です。つまり毎日公判が開かれるということです。そして公判の回数は5~10日くらいです。このように、公判自身を短期集中化しているのが裁判員裁判の大きな特徴と言えるでしょう。
3. 評議
裁判所での審理が終了すると、裁判官と裁判員が「評議」を行います。これは、被告人に対する判決をどのようにすべきかについての話し合いです。ここで決めるのは、「被告人が犯罪を行ったか」と「もし有罪ならどのくらいの刑罰を適用するか」と言う2つの問題です。
犯罪行為を行ったかどうかについてまで、裁判員に決められてしまうので、被告人にとって裁判員の存在は非常に大きいと言えます。また裁判官は裁判員に対し、刑罰の相場などについて説明をしますが「〇〇にすべきだ」などと押しつけることはなく、あくまで裁判員の判断は自由です。
そこで、裁判員裁判以外の通常の量刑の相場より重い刑罰を適用される可能性もあります。もちろん、一般的な相場より軽くしてもらえる可能性もあります。
4. 判決
評議が終わると、裁判官が評議の結果にもとづいて判決書を作成します。そして評議から数日以内に判決言い渡し日が指定され、被告人や弁護人在廷のもとに、判決が言い渡されます。
5. 控訴
裁判員裁判に対しても、控訴することは可能です。控訴審では裁判員裁判制度が導入されていないので、職業裁判官のみが判断します。そこで裁判員裁判によって不合理な判決が出てしまった場合、控訴審によって判決を変更してもらえる可能性も十分にあります。
期間
裁判員裁判の期間は、公判のみであれば非常に短く、だいたい1週間程度です。しかし公判前整理手続きの段階が非常に長いです。最低でも4か月、重大事件や無罪首長の事件では1年以上かかることも珍しくありません。
略式裁判の流れ
最後に、略式裁判の手続きの流れを簡単にご紹介します。
- 起訴
- 判決
- 罰金の納付
在廷義務がない
略式裁判の場合、「法定における審理」が開かれません。書面上のみで審理が進みます。そこで、被告人は裁判所に行って在廷する必要がありません。在宅事件の場合なら、そのまま自宅で過ごしていれば勝手に審理が行われて判決が下されます。
また、通常裁判の場合には被告人には必ず弁護人がつきますが、略式裁判の場合には弁護人はつきません。特に弁護活動として行うことがないためです。
略式裁判の流れについて
1. 起訴
略式裁判では、起訴されると起訴状と証拠書類が裁判所に送られます。ただ、被告人には特に影響がありません。
2. 判決
略式裁判でも、判決は出ます。だいたい起訴されたときに検察官が定めた通りの罰金刑か科料の刑です。
3. 罰金の納付
略式裁判の場合、罰金や科料の納付命令が出ます。在宅事件の場合には、自宅宛に起訴状と罰金の納付書が送られてくるので、速やかに支払いを済ませれば、刑罰を終えたことになります。身柄事件の場合には、釈放されるときに罰金の支払いを行います。
支払をしなかったら検察庁から督促が来て、最終的に「労役場」に連れて行かれて強制労働をさせられます。
期間
略式裁判にかかる期間は、1か月未満であることが多いです。
刑事裁判を有利に進めるために
刑事裁判の被告人となったら略式裁判にならない限り、弁護人によるサポートが非常に重要です。どのような弁護活動を展開してもらうかにより、最終的な結論(判決)が大きく変わってくる可能性もあります。刑事裁判で有利な結果を獲得するには、刑事弁護を得意とする弁護士に依頼することが何より重要です。
交通事故、痴漢、喧嘩や傷害、薬物犯罪など、生きていればいろいろな犯罪に巻き込まれる可能性があるものです。困ったときにはすぐに弁護士に相談し、あなたやあなたのご家族を守ってもらいましょう。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

警察からの呼び出しに応じないとどうなる?参考人として逮捕される?
この記事で分かること 警察からの呼び出しに応じると逮捕される?警察からの呼び出しの理由...
-

この記事で分かること そもそも「事件」とは?「刑事事件」と「民事事件」の違いは?「民事...
-

この記事で分かること 刑の確定は14日後どこの刑務所に収監されるのか?未決勾留があった...
-

この記事で分かること 取調べのルール~現在の取調室事情~留置場の監督は別部署が行う取調...
-

この記事で分かること 逮捕された被疑者が求めるべきは「不起訴処分」「不起訴処分」を得る...
-

逮捕後の流れを簡単に解説|逮捕されて送検から起訴されるまでに何が起こる?
この記事で分かること 刑事事件で逮捕されるとどうなる?1分で分かる!刑事事件で逮捕され...
-

この記事で分かること 現代は真面目に暮らしている人間でも逮捕される危険は潜んでいる!家...
-

警察に捕まったらスマホ(携帯電話)はどうなる?逮捕の連絡は家族や友人・知人に行く?
この記事で分かること 警察に捕まったらスマホ(携帯)はどうなる?家族や友人・知人の逮捕...
-

逮捕された友人知人がどこの警察署に捕まってるか調べる方法はある?
この記事で分かること 逮捕された家族や友人、知人はどこにいる?逮捕された被疑者には、い...
-

この記事で分かること 逮捕後の身柄拘束を解く方法は?「勾留取消請求」とは?「勾留執行停...