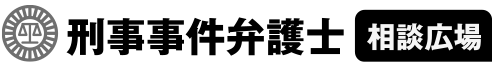刑事事件とは?民事事件との違いについても解説
- 2025年1月20日
- 95,615 view
- 10分でわかる刑事手続き
- 刑事事件弁護士相談広場

事件には大きく分けて「刑事事件」と「民事事件」があり、それぞれ法律や手続きも違います。一方で、交通事故のようにこれら両方の事件で裁判が起こされることもあります。これらの違いを知ったうえで、被疑者は弁護士の力を借りて戦うべきだと言えます。
そもそも「事件」とは?
一般的に「事件」と呼ばれるものには、暴力沙汰や交通事故などに代表されるように、争いや犯罪、騒ぎ、事故など、人々の関心を引くさまざまなものがありますが、法令用語としての「事件」は事柄や案件のことで、官公庁における手続きのことを指します。
事柄と案件という2つの言葉から「事件」と呼ばれるものになり、本来ならば犯罪などに限定されることはないのですが、現在では主に社会的なトラブルや騒ぎになるようなものが「事件」であると理解されています。
実際、手続き上の事柄を「事件」と呼ぶ時、「事件」には、「刑事事件」、「民事事件」、「行政事件」、「犯則事件」、「非訟事件」、「届出事件」など、多くの「事件」があるのです。また、離婚や相続などにおける家庭内のトラブルは「家事事件」と呼ばれ、裁判などの手続き上では、「民事事件」の一種となります。
本項では、一般市民が遭遇する可能性があるトラブルの中で、裁判にまで発展することが考えられる「刑事事件」と「民事事件」について取り上げます。
「刑事事件」と「民事事件」の違いは?
「事件」の中でも「刑事事件」と「民事事件」は一般市民にとって、あまり遭いたくはありませんが、いざ巻き込まれた時のために、解決方法や特徴などの知識を持っておくべきものです。
「刑事事件」と「民事事件」の違いは、裁判において争う当事者の違いによって区別するのが分かりやすいとされます。
「刑事事件」の裁判における構図は、国家権力(警察官や検察官)と被疑者(被告人)の争いとなり、「民事事件」においては、私人(個人あるいは法人を問わず)と私人の争いとなります。
また「刑事事件」における犯罪行為は、殺人、傷害、窃盗、痴漢などであり、そこに警察や検察といった捜査機関が介入し、捜査を行ったうえで、刑罰を科すかどうかの判断を下す裁判が行われるのです。
一方の「民事事件」における犯罪行為は、貸したお金を返してもらえない、交通事故に遭って加害者に損害賠償請求を行いたい、会社から不当に解雇を言い渡された、不倫相手に対して慰謝料を請求したいなど、私人間のトラブルや諍いに関して、権利を主張する側が原告となり提訴し、裁判が行われるものです。
「刑事事件」と「民事事件」に共通していることは、事件の解決や決着を図るためには、最終的に裁判所の審判を仰ぐことになる可能性があるということです。
裁判に至る前に事件が解決することもあり得るという点も同じですが、基本的な考え方や手続きの方法は大きく違いますので、それぞれの手続きについては後述します。
「刑事事件」と「民事事件」、裁判所は同じ
一方で、「刑事事件」と「民事事件」の裁判の当事者は違いますが、裁判は同じ裁判所で行われます。
裁判所で扱われる代表的な「事件」には、「民事事件」、「行政事件」、「刑事事件」、「家事事件」、「少年事件」、「医療観察事件」などがあります。
「刑事事件」においては、事件の捜査を行ったうえで逮捕状を取り、被疑者を逮捕した警察や検察という国家機関が訴えを起こし、罪を犯してしまって逮捕された被疑者が被告人となります。
「民事事件」では、訴えを起こす原告と訴えられた被告に立場は分かれますが、双方ともに私人であって、事情によっては逆に訴えを起こすこともできるのです。
そして、「刑事事件」における被疑者と、「民事事件」における被害者は、立場の違いはありますが、多くの場合には弁護士の力を借りて、同じ法廷で戦うことになるのです。
「民事事件」は私人対私人のいさかい
本サイトで紹介するのは「刑事事件」ですが、双方の特長を比べた方が理解しやすいと思われますので、まず「民事事件」から紹介します。
「民事事件」とは、基本的は私人同士の揉め事で、前述の通り、お金のトラブルが中心となります。代表的なものは、離婚や遺産相続における資産やお金のやり取り、あるいは交通事故の損害賠償をいくら支払うか、といったものです。
また、訴訟を起こしたり、起こされたりするのは、必ずしも個人ではなく、法人の場合もあるのが特徴的です。
アパートやマンションの家賃滞納で管理会社が住人を訴えるのも「民事事件」となり、広義の解釈では、国を相手に損害賠償を訴える国家賠償裁判も民事事件の一種です。
「民事事件」は、主に「民法」と「民事訴訟法」に基づく
私人同士の紛争である「民事事件」において、どちらの言い分が正しいのか、どちらにどのくらいの責任があるのかを裁判所が判断する場が「民事裁判」となります。
「民事事件」は、六法の中では主に「民法」と「民事訴訟法」に定められたルールによって手続きが進められます。
「民法」とは、公権力を持たない私人間の関係を規定する私法において基本となる法律で、人間社会の中で他人に対する権利と義務に関する一定のルールを定めたものです。
「民事訴訟法」とは、民事訴訟の手続きを定めている法律ですが、実質的には民事訴訟制度を規定する「裁判所法」、「弁護士法」、「人事訴訟法」、「行政事件訴訟法」、「破産法」など多くの法律の総体を意味しています。
六法とは?
六法とは日本においては「憲法」、「民法」、「商法」、「刑法」、「民事訴訟法」および「刑事訴訟法」という、主要な6つの法典を指します。これらを含むさまざまな法令が収録された「六法全書」という言葉も一般的に知られているところです。
「民事事件」においては以上のようなさまざまな法律が絡んできます。
私人同士の法廷での戦いにはなり、自分だけで訴訟を行う本人訴訟という方法もありますが、当事者となってしまった場合には、多くの法律を理解している専門家である弁護士の力を借りることが必要となってくるでしょう。
「刑事事件」では国家が個人を弾劾する
以上に説明した「民事事件」に比べて、「刑事事件」は個人が犯した罪を国家が弾劾するものとなります。
傷害や窃盗、痴漢などの犯罪行為を行ったとされる被疑者に対して、警察や検察といった国の捜査機関が捜査を行い、裁判にかけて刑罰を求める手続きです。
日本の法律においては、「刑事事件」の被害者が加害者である被疑者に対して制裁を加えること、いわゆる自力救済は禁じられていますので、被害者に代わって国家権力が加害者の責任を追及するものとなります。
刑罰を科すためには原則として裁判を起こすことが必要となり、その刑事裁判を提訴できるのは検察官のみとなります。
「刑事事件」に該当する罪とは?
個人のどのような行為が「刑事事件」になるかということは、基本的に「刑法」に定められていますが、その他にも刑事罰が設けられている法律や条例が多くあり、それらに違反した場合も「刑事事件」の対象となります。
まず警察庁統計の分類による、「刑法」に定められた刑法犯には、以下のようなものがあります。
| 凶悪犯 | 殺人、強盗、放火、強姦 |
|---|---|
| 粗暴犯 | 暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合 |
| 窃盗犯 | 窃盗 |
| 知能犯 | 詐欺、占有離脱物横領を除く横領、偽造、涜職、背任 |
| 風俗犯 | 賭博、わいせつ |
| その他 | 公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、器物損壊など |
一方、刑法犯以外の罪は特別法犯と呼ばれ、道路交通法違反、覚せい剤取締法違反、売春防止法違反などが該当します。
そして条例の違反に関しては、冤罪事件が多発して問題になっている迷惑防止条例がよく知られているところです。
「刑事事件」は主に、「刑法」と「刑事訴訟法」に基づく
以上のような、日本において犯罪と定められている罪を犯してしまった者や、犯した疑いのある者に対して、有罪なのか無罪なのかという判断と、有罪ならばどのような刑罰を与えるかという事を決める手続きが「刑事事件」になります。
「刑事事件」六法の中の「刑法」と「刑事訴訟法」に定められたルールに基づいて手続きが進められます。
「刑法」とは、刑罰と刑罰が科せられるべき犯罪を規定した法律で、「刑事訴訟法」とは、刑事訴訟の手続きを定めている法律となります。
「民事事件」と「刑事事件」は別。2度訴えられる事も!
以上のように「刑事事件」と「民事事件」は、たとえ同じ事件であっても、根拠になる法律や手続きはまったく別物なのです。
警察に逮捕されるような事件は、ほぼ「刑事事件」となりますが、その事件の被害者に「民事事件」として再び訴えられることもあります。
最も多いのは交通事故のケース
一般人で、「刑事事件」と「民事事件」の両方で訴えられるケースとして、可能性の高いのは交通事故です。
交通事故を起こしてしまって、被害者が負った経済的な補償を要求されるのは「民事事件」となります。
同時に、被害者が亡くなってしまったり、大怪我をしてしまったりした場合、業務上過失傷害、あるいは業務上過失致死といった「刑事事件」にもなります。
窃盗や詐欺のような犯罪とは違い、交通事故で起こしてしまった「刑事事件」の場合は、裁判となり判決が下されるまで長期にわたり留置場や拘置所といった刑事施設に身柄を拘束されることはあまりありません。
しかし「民事事件」としての被害者に対する損害賠償と、「刑事事件」として国家権力が科す刑事罰が同時に科せられることになります。
裁判で有罪が確定するまでは犯罪者ではない
以上のように、「刑事事件」は私人同士の権利、金銭や利害の争いではなく、この国の定めた掟に背いたかどうかを判断するもので、裁判で有罪判決が下されれば犯罪者となり、犯した罪に相応しい刑罰が科せられてしまいます。
しかし、一般的によく誤解されていますが、「刑事事件」によって裁かれることになった人は、裁判において有罪が確定するまではあくまでも、罪を犯したと疑われる被疑者であり、犯罪者ではありません。
逮捕された瞬間から犯罪者扱いをしてしまうのは、近代の司法の考え方に反するものです。
マスコミや一般人の穿った見方に負けないこと
「刑事事件」で警察に逮捕されてしまった人の多くが、実際には罪を犯しており、罪をそのまま認めているケースが多いために、マスコミによる報道を見た一般人も、なんとなく逮捕されただけで被疑者を犯罪者扱いしてしまう傾向にあります。
しかしこれは、身に覚えのない罪を着せられてしまうという冤罪を生んでしまう要因にもなっています。
現行犯など、明らかに罪を犯した場合はともかく、被疑者が犯行を否認している場合には、マスコミの論調を疑ってみる必要があります。
まったく身に覚えのない罪や、事実と違う内容で逮捕されてしまった場合には、弁護士の力を借りて徹底的に戦うべきです。
有罪率99%の裏側は、低い起訴率がある
よく、日本の警察は優秀で、有罪率が99%を超えるということを聞きますが、この有罪率というものは、起訴されて裁判になった事件しか数えられていません。
警察や検察がいくら有罪だと断定して逮捕したとしても、その後の調べで起訴しても勝てないという事件に関しては、不起訴処分といった決着になるケースが意外と多いのです。
確実に有罪となるものだけ起訴しているからこそ、有罪率が99%となり、無罪判決が出た場合には大きなニュースになるほど珍しいことなのです。
逮捕されてしまった場合、警察や検察の言いなりになるのではなく、少しでも納得いかないことがある場合には、弁護士を雇って戦うべきです。
犯してしまった罪を償うことと、警察や検察の間違った判断を追求することは別なのです。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

この記事で分かること 刑の確定は14日後どこの刑務所に収監されるのか?未決勾留があった...
-

この記事で分かること 取調べのルール~現在の取調室事情~留置場の監督は別部署が行う取調...
-

この記事で分かること 逮捕された被疑者が求めるべきは「不起訴処分」「不起訴処分」を得る...
-

この記事で分かること 刑事事件で加害者が被害者と示談するメリット被害者と示談交渉を行う...
-

自首すると刑が軽くなるって本当?自首と出頭の違いについても解説
この記事で分かること 自首とは自首と出頭の違い自首をするメリット自首をするとどれくらい...
-

警察からの呼び出しに応じないとどうなる?参考人として逮捕される?
この記事で分かること 警察からの呼び出しに応じると逮捕される?警察からの呼び出しの理由...
-

この記事で分かること 逮捕には原則がある再逮捕とは?再逮捕はどう行われる?再逮捕されて...
-

この記事で分かること 刑事裁判とは刑事裁判の種類によって流れが異なる一般的な刑事裁判の...
-

逮捕後の流れを簡単に解説|逮捕されて送検から起訴されるまでに何が起こる?
この記事で分かること 刑事事件で逮捕されるとどうなる?1分で分かる!刑事事件で逮捕され...
-

この記事で分かること 現代は真面目に暮らしている人間でも逮捕される危険は潜んでいる!家...