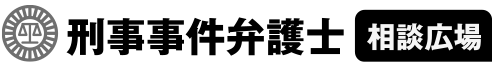覚せい剤、大麻、薬物犯罪で逮捕されたら?弁護士の費用相場についても解説
- 2025年1月20日
- 16,402 view
- 犯罪の種類
- 刑事事件弁護士相談広場

薬物に関する犯罪は日常のニュースでもよく耳にします。特に最近では覚せい剤所持、使用で元有名プロ野球選手や有名歌手が有罪判決を受け、大麻所持で女優が起訴されています。現代社会に深く根を張る薬物犯罪に対する規制の中身、そして捜査での特質などを明らかにして、逮捕時にどのようにすればいいのかを説明します。
覚せい剤・大麻などの薬物犯罪で身近な人が逮捕された場合
薬物犯罪の規制法としては、薬物四法と呼ばれる、覚せい剤、大麻、麻薬及び向精神薬の各取締法にあへん法があります。これに麻薬特例法を加えて薬物五法と呼ぶ時もあります。薬物犯罪とはどのようなものなのか見ていきましょう。
覚せい剤取締法
わが国の薬物犯罪で最も多いのが、覚せい剤です。平成27年の罪名別検察庁新規受理人員では覚せい剤取締法違反が1万7979人で大麻取締法(3383人)、麻薬取締法(1004人)、あへん法(6人)を加えた数字のおよそ4倍という圧倒的な数字です(平成28年版犯罪白書)。
覚せい剤使用の効果
主に白色の粉末や無色透明の結晶で、使用すると神経を興奮させ眠気や疲労感がなくなり、頭が冴えたような感じになります。効果が切れると脱力感、疲労感、倦怠感に襲われます。特に依存性が強く、使用を続けると幻覚や妄想が現れ錯乱状態になって発作的に他人に暴行したり、殺害したりするなどの危険があります(内閣府ホームページ参照)。
営利目的なら無期懲役も
覚せい剤に対する罰則は非常に重く、営利目的でみだりに輸出入した者は無期若しくは3年以上の懲役に処せられます(覚せい剤取締法41条2項)。
所持、使用では最長10年
覚せい剤所持、使用は10年以下の懲役に処せられます(同法41条の2第1項、41条の3第1項1号)。所持し、使用した場合は併合罪(刑法45条)となるため、最長で15年の懲役の可能性があります。
大麻取締法
大麻は覚せい剤に次いで検挙人数が多い事犯です。海外では一部解禁になっている国もありますが、日本では認められていません。
大麻の種類と使用方法
大麻には乾燥大麻(マリファナ)、大麻樹脂(ハシッシュ)、液体大麻(ハシッシュオイル)があります。通常は乾燥した大麻草の葉等をキセル、パイプ、水パイプ等を使用して吸煙します(内閣府ホームページより)。
大麻使用の効果
大麻を使用すると一般的には快活、陽気になり、よくしゃべるようになると言われますが、その一方で視覚、聴覚、味覚、触覚等の感覚が過敏になり、感情が不安定になったりします。興奮状態になって暴力や挑発的な行為をしたり、幻覚や妄想等に襲われたりすることがあります。また、何もやる気のない状態となる無動機症候群に陥ることもあります(内閣府ホームページより)。
大麻取締法違反の法定刑
非営利で所持した者は5年以下の懲役(大麻取締法24条の2第1項)です。営利目的での所持の場合は7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金が科されます(同2項)。使用について罰則はありません。同法24条の3第1項1号に使用についての罰則に関する規定がありますが、これは大麻の使用を認められた者の目的外使用を罰するものです。
麻薬及び向精神薬取締法
覚せい剤や大麻、あへん以外の薬物については、麻薬及び向精神薬取締法が規制しています。
対象となる薬物
わが国が結んだ禁止薬物の条約に基づいていますが、一般的なものとしてはヘロイン、モルヒネ、コカイン、MDMAなどです。
麻薬及び向精神薬取締法の法定刑
ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等の営利目的の輸出入の場合、無期若しくは3年以上の懲役(麻薬及び向精神薬取締法64条2項)となります。非営利目的の所持、使用(施用)は10年以下の懲役(同法64条の2第1項、64条の3第1項)です。ジアセチルモルヒネ以外の麻薬(モルヒネ、コカイン等)については所持、使用とも7年以下の懲役(同法66条1項、66条の2第1項)です。向精神薬の所持は3年以下の懲役(同法66条の4第1項)です。
あへん法
あへんは現在ではあまり使用されない麻薬です。刑法にあへんに関する規定があり(136条〜141条)、あへん法との関係が問題になります。また、シンナーについては毒物及び劇物取締法が規制しています。
あへん使用の効果
あへんには神経を抑制する作用があり、濫用すると強い陶酔感を覚えますが、精神的、身体的依存性を生じやすく、常用するようになると慢性中毒症状を起こし、脱力感、倦怠感を感じるようになり、やがては精神錯乱を伴う衰弱状態に至ります(内閣府ホームページより)。
あへん使用者の状況とあへん法の法定刑
平成27年の罪名別検察庁新規受理人員で、あへん法違反はわずかに6人でした。現代ではあまり問題になることが多くない事犯です。あへんの所持、使用は7年以下の懲役です(あへん法52条1項、9条、52条の2第1項)。
シンナーと危険ドラッグ
「シンナー遊び」や近年、若者の間で話題になることが多い脱法ドラッグ、脱法ハーブも処罰の対象となります。
シンナーと毒物及び劇物取締法
最後にシンナーに触れておきます。広い意味での薬物犯罪、あるいは薬物犯罪類似の犯罪と言えるでしょう。シンナーの吸引(いわゆるシンナー遊び)は2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科されます(毒物及び劇物取締法24条の3)。
脱法ドラッグ今は危険ドラッグ
以前は脱法ドラッグと呼ばれたものは現在、行政側から危険ドラッグと呼ばれ、医薬品医療機器等法(薬機法、以前の薬事法)の規制を受けます。具体的には厚労大臣が指定した「指定薬物」として、医療目的以外に所持、使用することが禁じられています(同法76条の4)。これに違反した場合は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、または併科されます(同法84条26号)。
危険ドラッグの検挙数急増
危険ドラッグの検挙者は近年急増しています。平成21年にはわずか9人だった薬機法(当時は薬事法)違反の検挙者が、平成26年に492人、平成27年には960人となっています(平成28年版犯罪白書)。
逮捕されると弁護士以外は連絡を取ることができません
逮捕された被疑者については、電話やメール等で外部と連絡を取ることはできません。また、家族との接見(面会)が認められない場合があります。ただし、弁護士との接見については認められます。
家族との接見、逮捕直後は原則不可
家族との接見は逮捕から勾留されるまでの間は、原則として認められません。接見できるのは勾留されてからです。もっとも実務では、担当の司法警察員が認めれば家族との接見を認めるようです。検察官が被疑者を受け取ってから留置の必要があると判断するとき、裁判所に勾留請求が出されます。認められれば被疑者は勾留されます。勾留決定がされた後、家族は接見できますが、もし逃亡し、又は罪証を隠滅すると疑われるときは接見禁止になります。なお、弁護士は勾留時はもちろん勾留前も接見できます。
弁護人の接見は憲法上認められた権利
弁護人依頼権は憲法34条前段で保障されている重要な権利です。逮捕された被疑者にとって、唯一の味方とも言えるのが弁護士です。弁護人や弁護人になろうとする者とは、立会人なくして接見し、または書類もしくは物の授受できます。(39条1項)。
特に重要な初回の接見
弁護人(になろうとする者)の接見の中でも、特に初回の接見については弁護人の選任を目的としたり、取調べにあたり助言を得たりする最初の機会ですので重要です。捜査機関においても、弁護士との接見については十分に配慮するシステムになっています。
薬物事件で逮捕された後の流れ
薬物事件に限らず、逮捕され裁判が行われるまでの手続きは刑事訴訟法に規定されています。その手続きの中で釈放されたり、不起訴になったり、起訴されても保釈になったり、様々な状況が起こり得ます。ここではその流れを見てみましょう。
逮捕
逮捕は被疑者を強制的に身柄拘束する処分で、法定された短時間の留置を伴います。逮捕と一口に言ってもいくつかの種類があります。
逮捕には4種類、シンナーで緊急逮捕はできない
逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、準現行犯逮捕、緊急逮捕の4種類があります。(準現行犯逮捕と現行犯逮捕を一つにして3種類と考えることもあります。)
- 通常逮捕:事前に令状請求する逮捕。
- 緊急逮捕:令状請求する時間がなく逮捕後に令状請求しなければならない逮捕。
- 準現行犯逮捕・現行犯逮捕:令状は不要。
通常逮捕、緊急逮捕の逮捕権者は検察官や検察事務官または司法警察職員(警察官)とされています。一方現行犯逮捕及び準現行犯逮捕では、警察官だけでなく個人も可能です。(213条)。
シンナー遊びについては最長で懲役2年ですから緊急逮捕の対象ではありません。それ以外の薬物犯罪についてはすべての種類の逮捕の可能性があります。
逮捕後の動き
逮捕されると、被疑者は司法警察員から犯罪事実の要旨と弁護士を選任することができる旨が告げられます。もし留置の必要がないと判断(思料)されれば直ちに釈放されますが、置の必要があれば、拘束から48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官に送致する手続きがとられてしまいます。
弁解の機会と取調
被疑者を釈放する権限は法警察員が有しています。被疑者は弁解の機会を与えられ、続いて取調が行われますが、その際に司法警察職員から自己の意思に反して供述する必要がないこと、つまり黙秘権について告げられます。(198条2項)。
被疑者が外国籍だったら
被疑者が外国人の場合、自国の領事に通報することを要請するかを確認されます。領事館との面談ができたり、弁護人の斡旋を依頼できたりすることが説明されます。
微罪処分
微罪処分とは、軽微な事件について検察官が司法警察員に対して送致義務を免除するものです。司法警察員は本来、事件を速やかに検察官へ送致しなければなりませんが、その例外である検察官指定事件の一つが微罪処分です。微罪処分とは犯罪事実が極めて軽微で、かつ、検察官から送致の手続きの必要がないと指定されたもので、その割合は全検挙人員のおよそ3割です(平成28年犯罪白書より)。
送検
逮捕され、司法警察員に留置の必要があると判断されたら被疑者は検察官に送致されます。
送検の意味
送検は被疑者の身柄を検察官に送ることではなく、事件そのものを検察官に送ることを指します。つまり書類及び証拠物とともに被疑者の身柄を送致することで、それにより事件が検察官の扱いになることを意味します。
タイムリミット48時間
検察官送致には時間制限があり、被疑者の身柄拘束から48時間以内に書類及び証拠物とともに送致の手続きがされます。
検察官送致された時の収容施設
逮捕された場合は通常、警察の留置施設に収容されます。検察官送致を受け勾留される者は拘置所などの刑事施設に収容されますが、留置施設に収容される場合もあります。いわゆる代用監獄ですが、勾留決定があった場合でも警察の留置施設にそのまま置かれることが多いようです。
勾留
被疑者に留置の必要があると考えた場合、検察官は裁判官に被疑者の勾留を請求します。裁判官が勾留決定をすれば、被疑者は勾留されます。
送致された後は?
検察官は送致された被疑者を受け取った時、弁解の機会を与え留置の必要がないと判断すれば直ちに釈放することになります(205条1項前段)。逆に留置の必要があると考えた場合は、受け取った時から24時間以内、かつ、被疑者が身体を拘束されて(通常は逮捕の時)から72時間以内に裁判官に勾留を請求しなければなりません
裁判官による勾留決定
勾留請求を受けた裁判官により、勾留するかしないかが決定されます。被疑者に対して勾留する必要があるかどうか判断するために、被疑者に勾留質問を行います。勾留の理由がある場合には速やかに勾留状を発され、勾留の理由がない時には釈放されることになります。また、必要があれば事実の取り調べが行われます。
勾留期間と延長
勾留期間は10日です。勾留請求の日から10日以内に公訴を提起しない場合には直ちに被疑者は釈放されます。初日は時間にかかわりなく1日として計算されます。また、やむを得ない事由がある時は、10日を超えない範囲で期間の延長がされます。合計で10日を超えなければ、延長の回数に制限はありません。
起訴
起訴は、検察官が裁判所に実体的審理と有罪判決を求める意思表示です。勾留延長される場合を除き、勾留請求の日から10日以内に起訴するかしないかが決定されます。
検察官による起訴
起訴は検察官が行い、その権限は検察官のみが行使できます。(247条)。これを起訴独占主義と言います。また、たとえ犯罪の証明が十分でも、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により起訴しない場合もあります(248条)。
起訴された場合の被疑者の勾留
起訴された「被疑者」は「被告人」となります。被疑者の段階で勾留されていて被告人になった後も勾留される場合、検察官が起訴状を提出すると自動的に勾留が継続されます。被告人は起訴されると拘置所に移送になります。しかし、現実の運用は拘置所の混雑などでスムーズにはいかず、しばらく留置場に勾留されることもあるようです。
公判
検察官によって起訴になると、公判が開かれることになります。
裁判所の手続き
裁判所は公訴の提起があった時は、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達します。裁判長は公判期日を定め、検察官、弁護人に通知します。
弁護人選任権等の告知
公訴の提起があったとき、被告人は弁護士が選任できること、経済的に選任ができないときは選任の請求ができることが伝えられます。これは逮捕時、勾留質問時にもされますが、ここでも行われます。
公判手続きは大きく分けて4つ
公判手続きは、冒頭手続き→証拠調べ→弁論→判決という流れになります。
冒頭手続は、認定質問→検察官による起訴状の朗読→裁判長による権利告知→被告人及び弁護人が事件について陳述という順番で行われます。裁判長による権利告知とは、終始沈黙したり、または個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨、陳述がされた場合、自己に不利益な証拠ともなりうること等を告げることです。
シンナーでは簡裁での審理も多い
シンナーに関する事件では簡裁に起訴されることが多いようです。これは選択刑として罰金が定められている罪の訴訟(裁判所法33条1項2号)にあたるためです。簡裁では原則として禁錮以上の刑を科すことができません(同2項)。そして、同項の例外規定にシンナーについての罪は含まれていませんから、毒物及び劇物取締法で簡裁に起訴された時は検察官の求刑は罰金刑しかありません。
簡裁で起訴なら略式命令の可能性
シンナーに関する事件で簡裁に起訴された場合、検察官が公判手続きの必要がないと判断すれば、略式手続の請求ができます。予め被疑者の同意を得た上で請求し、簡易裁判所が公判手続によらずに書面審理だけで刑罰を言い渡せます(461条以下)。(簡裁だけの制度で100万円以下の罰金又は科料を科すことができます。)被疑者にとっても罰金刑しかありませんし、早期に事件から解放されるというメリットがあります。平成27年の検察庁終局処理人員を見ると毒物及び劇物取締法で公判請求をしたのは175人に対し、略式命令請求したのは121人でした。(平成28年版犯罪白書より)。
薬物事件で弁護士にかかる費用相場
弁護人が事件を担当することになると、解決のための費用がかかります。示談交渉がないため、示談にかかる金銭は必要ありませんが、弁護士の費用は必要になります。
弁護士に依頼する初期費用
弁護士は被疑者、被告人の身柄の解放や、起訴猶予への働きかけ、公判が始まれば無罪や執行猶予付き判決等を目指して活動をします。そのためには費用が必要になります。 こちらも読まれています

相談料
弁護士への相談料は、最近は初回無料としていることが多いようです。2回目以降は1回5000円程度が相場と言えます。
接見費用
被疑者・被告人との接見の場合、事務所から勾留場所まで行く必要があります。また、身柄拘束を解くための行動は、司法警察員、検察官、裁判官の手続きに時間制限がある以上、迅速に行う必要があります。そのため費用としても勾留場所との距離にもよりますが1回3万円前後はかかるのが普通です。
着手金
弁護士が事件を担当する場合、依頼人は着手金を支払うことになります。刑事事件では自白している事件であれば事実関係を争うことがありませんが、否認事件では不起訴や無罪判決を取る必要があり、事実関係からして争うことになります。そのため、否認事件は一般的には高くなります。弁護士にもよりますが、通常の自白事件なら20〜30万円程度、否認事件なら30〜50万円程度でしょう。
弁護士に依頼する場合のその他の費用
自白事件の成功報酬
自白事件であっても弁護士の活動によって微罪処分、起訴猶予、略式命令、執行猶予付き判決、保釈許可決定、勾留に対する準抗告が認められるなどで被疑者・被告人にとって利益になることがあります。その場合には成功報酬を支払うことになります。事件や弁護士にもよりますが起訴猶予や微罪処分が10〜30万円程度、それ以外は20万円以下が相場と言えるのではないでしょうか。求刑より言い渡された刑が軽い場合にも成功報酬は必要となるのが普通です。執行猶予については平成28年6月から始まった刑の一部執行猶予制度も成功報酬が必要と考えた方がいいでしょう。
否認事件の成功報酬
否認事件では無罪判決を得ることが可能です。その場合には事実関係を争い、時間と手間をかけて争いますから、当然、成功報酬は高く設定されます。30〜50万円程度は必要でしょう。もちろん自白事件でも無罪判決の可能性はあります(ウソの自白をした場合等)し、自白事件の方が無罪判決の獲得は難しいですから、少なくとも否認事件での無罪判決と同程度の成功報酬は必要になります。なお、否認事件でも不起訴、執行猶予付き判決などでの成功報酬は必要になると考えるべきでしょう。
実費
弁護士が活動にあたって実際に経費としてかけた分は依頼人に請求されます。接見するための交通費や、通常の通信費などです。また、特に保釈や執行猶予付き判決を得るためには、しっかりとした身元引受人がいることが問われます。そうした手配をするために交通費、通信費は必要になるでしょう。
日当
出頭したり、出張したりした際の日当が必要になります。概ね1回で3万円前後でしょう。また着手金を支払わずに、実際にかかった日数、時間によって支払額を決定する「タイムチャージ」という方式で支払う方法もあります。着手金で一律に支払うのではなく、かかった時間だけ支払うというものですが、大きな事件になると日数がかかり着手金方式より多く支払わなければならないということも考えられます。
薬物犯罪で逮捕された場合は時間が勝負!
刑事事件は警察-検察-裁判所と時間をかけずに手続きが進んでいきます。それに対して不服の申し立てをしなければ、起訴-有罪へと近づいていくと言っても過言ではありません。早期の対策こそが重要です。
逮捕から72時間以内の弁護活動が重要な理由
通常の事件処理では逮捕から72時間以内に勾留請求がされます。そこに至る前に解放に向けて努力することが被疑者の身体の解放に向けては重要です。
72時間が持つ意味
逮捕から72時間以内に、司法警察員による検察官送致、検察官による勾留請求が行われます。既述したように、被疑者の身体の解放に向けてそれぞれの手続きの中で行うべきことは異なります。適切な時期に適切な方法で解放に向けて動かないと、手続きだけが進んでいき身体の拘束からの解放がそれだけ遅れます。勾留決定されてしまうと10日間、身柄の拘束が続くことになりますから、その前の逮捕から72時間以内に勾留決定されないようにすることが重要です。
勾留決定への準抗告の持つ危険性
逮捕から72時間を過ぎて勾留決定がされても、準抗告で争えます。準抗告に対する裁判をするのは原則として裁判官が所属する裁判所ですから、裁判資料は捜査機関から裁判所に送られてその間、事実上、捜査ができない状況になります。そのため、勾留の延長(208条2項)の理由とされやすいという指摘もあります。勾留の理由に疑問があれば準抗告して争うのも、最決平成26年11月17日のような例(前出の京都市内の地下鉄の事件)がありますから、ためらうべきではないと思われます。もっともその可能性が低い状況で準抗告をする時は、勾留の延長というリスクを計算しながら行うべきでしょう。そのように考えると、勾留決定の前の逮捕から72時間以内での活動の重要性があらためて感じられます。
最大23日間の拘束・・社会生活に大ダメージ
薬物犯罪で逮捕された場合、実際には少ないでしょうが、論理的には起訴されるまでに最大で23日間、拘束される可能性があります。半月以上、社会から隔絶されることでの影響は極めて大きいと言えるでしょう。
23日間の拘束の内訳
逮捕されると最大で23日間、身柄を拘束されるということは、様々な媒体で目にすることがあると思います。中途半端な数字ですが、どのような根拠で23日なのでしょうか。1月1日午前10時に逮捕された場合で考えてみましょう。
- 1月1日10:00逮捕
- 1月3日10:00司法警察員が48時間以内に検察官への送致の手続きを行う
- 1月4日10:00送致されてから24時間以内、身柄拘束から72時間以内に検察官が勾留請求
- 1月13日終了まで勾留は最大10日間、この日までに勾留期間延長の請求
- 1月14日00:00勾留期間延長開始
- 1月23日終了まで勾留の延長は最大10日間
このように1月1日の逮捕から1月23日が終わるまで23日間、身柄を拘束される可能性があります。起訴されれば、さらに勾留は続きます。
最大23日間の拘束による影響
ある日、突然逮捕され最終的に起訴されずに釈放されたとしても、23日間、身柄を拘束されることの影響は甚大でしょう。特に会社勤めをしている場合には会社に直接連絡できなければ、無断欠勤を23日間続けることになります。家族や弁護士を通じて会社に連絡したとしても、23日間、有給休暇をもらえる保証はありません。何より、会社としては犯罪を犯したかもしれない人を重用しにくいでしょう。推定無罪の原則があるとはいえ「何もないのに23日間も拘束されるだろうか」「また逮捕されて23日間、会社に出てこない可能性があるだろう」と会社が考えることは十分にあり得ます。その意味では、最大23日間の勾留によって、それまで築いてきた自身の社会的信用を根底から崩されかねません。
起訴された場合の有罪確率は99.9%
日本の司法では起訴された場合、ほとんどが有罪になっています。
無罪判決はわずかに70人
平成27年度に地裁で7万4111人、簡裁で7951人が判決を受けましたが、無罪判決は地裁70人、簡裁6人でした(平成27年度司法統計)。無罪判決以外はすべて有罪判決ではありませんが(公訴棄却、免訴、管轄違い等の判決もあり)、有罪確率は例年およそ99.9%です。米国では否認事件の無罪率は15%前後と言われますが、大きな違いがあります。
弁護士への迅速な依頼が問題解決のカギ
上記のように日本の司法制度では「起訴されたら、ほぼ間違いなく有罪」と言っていい状況です。前科をつけたくないと考えた場合、起訴されないように示談を成立させるなどの対策が重要になります。そのためには逮捕された場合にはすぐに弁護士を依頼し、身柄拘束からの解放や起訴されないための活動(示談等)を行うことが必要になるでしょう。
覚せい剤や大麻の薬物事件の特殊性
薬物事件は「被害者なき犯罪」と呼ばれますが、そのため検挙も難しいと言われます。また被害者がないため通常、刑事事件で行われる被害者との示談もありません。また薬物には中毒性があるため、再犯率が高いのも特徴です。そうした特性を見ていきましょう。
薬物犯罪の捜査における特質
薬物犯罪の摘発においては、犯罪の特質から通常の犯罪とは違った捜査手法や手続きが用いられることがあります。かなり捜査側の事情を優先させている点には注意が必要です。
おとり捜査
おとり捜査とは、捜査官やその協力者が身分を隠して対象者に犯罪を行うように働きかけ、対象者が犯罪を実行した時に検挙するものです。犯人に犯罪を犯す意思があり、その機会を提供するものであれば合法であることになっています。ただし、犯罪をする意思がないのに、そそのかされて、その気になって実行した場合には、そうした捜査方法は違法であると考えられています。
令状の呈示
薬物、ことに覚せい剤の所持については自宅の捜索を行われることがあります。その際には捜索差押許可状を呈示されます。しかし薬物犯罪の捜索の場合、警察が踏み込んで場合によっては相手の動きを制してから呈示されることも少なくないようです。こうした点が違法ではないかと問題になりますが、最高裁は適法としています。
強制採尿
覚せい剤事件では尿検査を拒否する被疑者に対して強制採尿をすることがあります。この場合は捜索差押令状と、令状の記載要件として、強制採尿は医師によって医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠とされています。その方法はゴム製導尿管(カテーテル)を尿道に挿入するというものですから、医師が行うべきなのは当然でしょう。
接見や勾留での問題点
薬物事件では弁護士以外の者の接見や、勾留について通常よりも厳しい条件となることが多いのが特徴です。
接見禁止の可能性
被疑者、被告人が弁護士と接見するのは憲法34条前段に由来する極めて重要な権利です。しかし、家族との接見についてはそのような権利としては認められていません。薬物事件では証拠隠滅などが比較的容易なため、家族との接見を許すと罪証隠滅の可能性があるとして接見を禁止される可能性が高いと言われています。
勾留の可能性が強い
薬物事件では勾留請求が認められることが多く、在宅での起訴ということは少ないと言われます。これは薬物、特に覚せい剤が組織的な犯行で行われることが多く、罪証隠滅等の可能性が高いと判断されることなどが原因となっているようです。
示談ができないことの影響
被害者のある犯罪、たとえば暴行罪(刑法208条)や強制わいせつ罪(刑法176条)などの場合は、被害者と示談が成立すれば被害者が処罰を望んでいないということで、起訴猶予になることも多くなります。しかし、薬物犯罪はそのような示談をすることができません。そういった点から起訴猶予にしてもらう材料が乏しいと言えるかもしれません。
身柄拘束からの解放の取り組み
依頼を受けた弁護人としては、身柄を拘束された被疑者・被告人を一刻も早く自由の身にすることを目指します。自由の身になると一口に言っても、一連の手続きの中で様々な方法が考えられます。ただし薬物事件では起訴されるまでの解放は難しいのが現状です。
検察官に送致されずに釈放
逮捕後、自由の身になる最初のチャンスは検察官への送致がされずに釈放されるパターンです。司法警察員は留置の必要がないと思料すれば直ちに釈放しなければなりません(203条1項)。そして留置の必要性について最高裁は「犯罪の嫌疑のほか、逃亡のおそれ又は罪証隠滅のおそれ等から成るものである」(最判平成8年3月8日)と判示しています。この時点で釈放に向けてすべきことは犯罪の嫌疑が薄いこと、定まった住所や定職があり逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅ができないように現場付近に行かないことを約束するなどして、留置の必要性がないことを司法警察員に理解させることでしょう。
検察官送致後、留置の必要性がないと判断され釈放
被疑者が検察官に送致された後、検察官が留置の必要性がないと考えれば直ちに釈放されます(205条1項)。どのような場合に留置の必要性がないと判断されるかは、勾留請求書に刑事訴訟法60条1項各号に定める事由の記載が求められている(刑事訴訟規則147条1項3号)ことから、定まった住所がある(1号)、罪証隠滅ができないように関係者と接触しない、現場に近づかないことが約束されている等(2号)、定職があり、身元を保証する者がいて逃亡のおそれがない(3号)など、同条各号にいずれも該当しない場合が考えられます。それが認められれば検察官としては勾留請求書に60条1項各号の事由が書けないことになります。
裁判官が勾留請求を却下して釈放
検察官から勾留請求が出されても、裁判官が勾留の理由がないと認める時は直ちに被疑者の釈放を命じなければなりません(207条5項)。そのため、勾留の理由がないことを裁判官に働きかけます。ここも60条1項各号に該当しないことを主張することになります。実際には検察官の勾留請求から、裁判官の勾留決定までは時間も少ないことから、同時期に働きかける場合が多いようです。
裁判官の勾留決定に対して準抗告する
裁判官のした勾留決定に対しては準抗告が可能です(429条1項2号)。理由として60条1項各号に該当しないことを主張します。なお、罪証隠滅、逃亡のおそれについては「相当な理由」が必要とされていますが、この点につき「相当の理由があるとき・・は罪証隠滅の単なる抽象的な可能性では足りず、罪証を隠滅することが、何らかの具体的な事実によって蓋然的に推測されうる場合でなければならないことが明らか」(大阪地判昭和38年4月27日)とされた例があります。その点から罪証隠滅のおそれが抽象的なものにすぎないと主張をすることは考えられます。なお、勾留の裁判で犯罪の嫌疑がないことを理由に準抗告することはできません(420条3項、429条2項)。そのようなことは本案で争うべきだからです。そのためこの段階で「私は無実だから」ということをいくら主張しても準抗告が認められることはありません。
安易な勾留決定に警鐘?最高裁決定
平成26年11月17日、最高裁は京都市内の地下鉄で女子中学生の体を触ったとして、迷惑行為防止条例違反で逮捕された会社員の勾留を認めた原決定を取り消しました。原決定は罪証隠滅の現実的可能性(60条1項2号)があると考えて、勾留請求を認めています。しかし、最高裁は「被疑者が被害少女に接触する可能性が高いことを示すような具体的な事情がうかがわれないことからすると、(勾留請求を却下した)原々審の上記判断が不合理であるとはいえないところ、原決定の説示をみても、被害少女に対する現実的な働きかけの可能性もあるというのみで、その可能性の程度について原々審と異なる判断をした理由がなんら示されていない」として原決定を取り消しました。この決定が実務にどの程度影響しているか一概には言えませんが、前出の「罪証隠滅の単なる抽象的な可能性では足りず」という判示が重く感じられます。こうした常識的な決定が出されるということは、弁護士がいかに適切な主張ができるかということの重要性が増したと言えるでしょう。
起訴後勾留に対して保釈申請をする
起訴された場合は、保釈(88条以下)を請求します。保釈とは保釈保証金を納付して勾留の執行を停止し、拘束を解く制度です。起訴前勾留にはこの制度は適用されません。保釈には必要的保釈(89条)と裁量的保釈(90条)の規定があります。必要的保釈は89条の除外事由に該当しなければ裁判所は保釈しなければなりません。薬物関連の事件であれば、1号指定の重罪の場合もありますが、単純な所持、使用であれば該当しません。過去に重罪で有罪判決を受けた(2号)、常習犯である(3号)、罪証を隠滅する疑いがある(4号)、被害者や証人、その親族などに危害を加えたり畏怖させたりする疑いがある(5号)、氏名又は住居が分からない(6号)に該当しない場合には必要的に保釈されることになります。仮にいずれかに該当する場合でも裁判所が適当と認めれば保釈されることはあります(90条)。
逮捕による薬物犯罪の人生への影響
刑事事件で逮捕されると、人生は大きく変わります。会社勤めをしていれば解雇の可能性が高くなりますし、その後の就職活動にも影響を与えるのは必至です。私生活でも結婚などで悪影響が出ても不思議はありません。
薬物事件の刑罰
既述したように、薬物関連の犯罪は最高で無期懲役まである厳しい刑罰が待っています。
覚せい剤に関する刑罰
薬物事件で特に事犯が多い覚せい剤については、刑罰も非常に重いものになっています。所持、使用は10年以下の懲役です(覚せい剤取締法41条の2第1項、41条の3第1項1号)。所持し、使用した場合は併合罪(刑法45条)となるため、最長で15年の懲役の可能性があります。もっとも初犯であれば執行猶予付きになる可能性は十分あります。
処断刑の決定方法
法定刑から刑が重くなったり、軽くなったり処断刑は、①再犯加重、②法律上の減軽、③併合罪の加重、④酌量減軽の順に従って罪が加重されたり、減軽されます。初犯で、心神耗弱などの減軽事由がなく、また、併合する犯罪でない場合は、④酌量減軽だけが問題になります。
酌量減軽の内容
酌量減軽は「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる」(刑法66条)というものです。犯人の年齢・境遇・前科、犯罪後の事情その他諸般が情状とされていますから、被害者との示談が成立しているか否かは大きな影響を与えると言えるでしょう。
逮捕による仕事への影響
逮捕されることで真っ先に影響が出るのは仕事です。特に出勤途中に逮捕された場合等、家族が逮捕の事実を知らない場合は深刻です。
逮捕で無断欠勤になる?
逮捕された場合、被疑者は電話やメール等、外部との連絡手段を失います。捜査員によっては電話で家族に逮捕の事実を知らせてくれる場合もあるようですが、そのようなことは義務とされているわけではありません。仮に共犯の存在が疑われる事件であれば、警察が家族に電話をすることで逮捕された事実を教えることになってしまい、共犯者による罪証隠滅や逃亡が行われかねませんから、連絡することはありません。そのため被疑者は会社にも家族にも連絡できない失踪と同様の状態になることもあり、勤め人にとって最もしてはいけない無断欠勤を余儀なくされる可能性があります。
身柄拘束が続いた場合
警察から連絡がない場合に家族が逮捕を知るのは、被疑者が弁護士と接見し、弁護士を通じて連絡を取ることによる場合が多いのではないでしょうか。それができなければ会社や家族にとって「失踪」と同様の状態が続くことになります。仮に弁護士から家族に連絡が入り、会社に伝えて有給休暇が認められれば少なくとも給与の面では損失はありませんが、それが認められる保証はありません。会社にすれば起訴され、その後も勾留が続く可能性を考えるでしょうし、有罪なら解雇もありうると考えるでしょう。そうした状況ですから被疑者は会社の戦力とみなされなくなる可能性を考えないといけません。
推定無罪の原則は会社に通用するとは限らない
刑事事件の大原則に「推定無罪の原則」があります。被疑者・被告人は無罪の可能性はあります。しかし、会社において同僚や上司が「実はこの人は犯罪を犯したのではないか」と考えることまで禁止できるわけではありません。いつ会社に戻ってくるのか分からない、有罪になれば解雇されるかもしれない等を考えれば、重要な仕事を頼まなくなるのが普通です。
家族への薬物事件の影響
被疑者の逮捕で精神的に大きなショックを受けるのは家族でしょう。身内が逮捕されるという事態は、配偶者、親兄弟、子供に与える影響は甚大です。
家族の行方が分からない
出勤途上に逮捕された場合など、家族は逮捕された事実を知ることができません。
失踪か、事故か、自殺か
家族にすれば、会社から「今日は家を出ましたか?出勤していませんが」という電話で父親(や息子等)が会社に行ってないことを知るという状況が起こり得ます。突然の出来事にパニックに陥るかもしれません。
弁護士からの連絡でまたパニック
そのうち警察か、もしくは接見した弁護士からの連絡で逮捕の事実を知ることになるでしょう。犯罪とは無縁の存在だった家族にとって「身内が犯罪者に」という思いから、またしてもパニックになると思われます。
ご近所に知られたくないが
家族が逮捕されたことは当然、付き合いのあるご近所には知られたくないでしょうが、バレてしまうことはありそうです。
報道で公になることも
家族にも逮捕の事実はなかなか分かりませんから、ご近所に知られることは少ないと思われますが、そうでもありません。薬物事件がメディアで報じられることは少なくありません。特に被害者、加害者が公務員や有名企業の社員であったりした場合にはテレビやネット、新聞などで事件として報じられる可能性が高く、そのような場合には、すぐに周囲に逮捕の事実を知られてしまいます。
事件で自宅を捜索される可能性も
また、報道がなくても、捜査機関は捜査のため必要があれば令状をとって家宅捜索をすることもあります(218条1項)。そうなれば大勢の捜査員が自宅に入ってくるためご近所の知るところになってしまいます。身内が逮捕された、自宅を捜索されたという事実をご近所に知られれば、家族としてはまともに外を歩くのも憚られる状況となるでしょう。
結婚・人間関係への薬物犯罪の影響
逮捕という前歴は結婚や、周囲の人間関係にも大きな影響を及ぼします。
結婚への影響
結婚(婚姻)は両性の合意のみに基づいて成立しますが(憲法24条1項)、親や周囲の意見も影響するでしょう。そうなると逮捕の影響は結婚にも及んでくるのは必至です。
当人でも、親でも逮捕は結婚に悪影響
婚姻当事者が「覚せい剤で逮捕された人とは結婚したくない」と思うことがあるかもしれません。それは当人の考えですから仕方がないことでしょう。しかし、それを知りながらも結婚したいと願った時に、その親が「逮捕歴のある人とは結婚してほしくない」と言い出すことは十分に考えられます。あるいは結婚相手の父親が薬物犯罪で逮捕歴があると知られた時に、「親同士も付き合いがあるから、結婚してほしくない。逮捕歴のある人の子も逮捕されるような性格かもしれないから、やめてほしい」と言われることもあり得ます。結婚は親を含めて一生の付き合いですから、慎重さを求めるのが普通の親の考えでしょう。その意味で逮捕が結婚に与える影響は小さくありません。
調べられ、知られてしまうことも
当人や親の逮捕歴は、そう簡単に他人に知られることはありません。前科前歴はみだりに公開されないという法律上の保護はあり、第三者が公的機関からそのような事実を知ることはほとんどあり得ません。しかし、今でも結婚前に相手の身上調査をする場合もあり、隠していた逮捕歴が明らかになってしまうことがあります。そのような調査の是非はともかく、そうした調査によってせっかくの結婚が破談になる可能性は否定できないでしょう。
前歴を隠していたことが離婚の原因となるか
仮に逮捕されたことを隠して結婚し、その後、発覚した場合は離婚の原因となるでしょうか。協議離婚(民法763条)は可能でしょう。裁判上の離婚の場合は、そのような前歴や、それを隠していたことが「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に相当するか否かという問題になります。一度だけの軽微な事件であれば離婚原因とするのは難しいかもしれませんが、可能性が全くないとは言えないでしょう。
人間関係への影響
逮捕歴は結婚だけでなく、人間関係にも影響を及ぼすことは考えられます。
友人との信頼関係
それまで親しかった人間が逮捕後、よそよそしくなることはあるかもしれません。スピード違反で反則金を支払ったレベルならよくある話と言えるでしょうが、身柄を拘束されるのであれば、遵法精神に欠ける人間とみなされることは覚悟しないといけないでしょう。しかも薬物犯罪であれば、常習性が疑われますから、なおさらでしょう。
その他の影響
逮捕によって人生に影響が出る場合は他にも考えられます。
就職への影響
以前は就職活動で履歴書を提出する際には「賞罰」という欄があり、前科前歴はそこに記すようになっていました。最近はプライバシーの保護を重視し、そのような欄がない履歴書が一般的です。しかし、金融機関などの職務によっては任意に前科前歴を聞いてくることがあると言われます。虚偽を述べれば後で内定取消しになるのは確実です。その意味では逮捕歴は就職活動に大きな影響を与えるでしょう。
旅行への影響
アメリカに旅行に行く場合、日本人は90日以内の観光であればビザは不要です。しかし、逮捕歴があると、査証免除プログラムを利用しての渡航はできなくなります。ビザを申請して、領事による面接を受けることを義務付けられます。
薬物犯罪の刑事事件で弁護士に依頼するメリット
刑事事件では弁護士がつくことで様々なメリットがあります。
外部への連絡・説明
逮捕され、身柄を拘束されている被疑者は外部との連絡を取る手段を持っていません。そこで弁護士が重要な役割を果たすことになります。
外部連絡は弁護士のみ可能
逮捕されると被疑者は外部と電話やメールなど、一切の連絡手段を使うことができなくなります。家族についても、勾留されるまでは原則として接見できません。そのような状況で被疑者と連絡を取れるのは弁護士だけです。被疑者の状態を家族や会社に性格に伝えることができ、外部との唯一の窓口になります。
勾留後も家族が接見できない場合も
薬物犯罪の場合、罪証隠滅等が疑われることなどから家族の接見が禁止される可能性があります。そうなると、勾留後も唯一の連絡窓口が弁護士となります。
手続きの見通しなど説明が可能
家族や会社の関係者が突然の逮捕で、どのような手続きが進むのかも分からない状況の中、弁護士は刑事訴訟法、刑事訴訟規則に基づく手続きの流れを熟知しています。身柄の拘束を解くためにどのタイミングで何をすればいいか、家族や会社はどう協力すべきか、適切にアドバイスをして被疑者とその関係者のために力になってくれます。
処罰の軽減、回避につながる弁護活動
弁護士は身柄の拘束を早く解くこと、処罰を軽減、回避するための活動を行います。
しっかりとした身元引受人を
弁護士が行う活動で最も重要なのが示談交渉でしょうが、薬物犯罪であれば示談交渉はありません。しかし、保釈や執行猶予付きの判決を得るために弁護士の活動が不可欠になります。保釈については薬物犯罪では罪証隠滅や再犯の危険を考慮するのは当然です。そこでしっかりとした身元引受人を置くことで、そのような行為に及ばないことを保証してもらうことは重要です。
更生への道筋をつける
薬物犯罪は常習性が高いことから、再犯率が高いのが特徴です。平成27年に覚せい剤取締法違反で検挙された1万903人のうち再犯者は7128人で、再犯率は実に65.4%です(平成28年版犯罪白書)。そのような特徴がありますから、再犯を防ぐために薬物を扱う組織と縁を切ること、薬物の常習性を断つための民間組織等でのリハビリをすることなどが重要になります。そのようなことで矯正施設(刑務所)での更生より、一般社会の中で更生できるということを裁判所にアピールすることにより、保釈や執行猶予付き判決を得やすくなるでしょう。
早期の依頼で解放へ様々な活動が可能
薬物犯罪の容疑で逮捕された直後に依頼を受けた場合、弁護士は司法警察員に検察官送致をしないよう働きかけたり、送致されても検察官に勾留請求をしないように働きかけたりすることが期待できます。勾留されても準抗告したり、起訴されても保釈を申請したり、身柄の拘束からの解放に全力を尽くすでしょう。それによって処罰の回避や、自由の身になることなどが期待されます。
薬物犯罪は証拠を隠したり、共犯者がいる可能性が高くまた常習性があるため、他の親告罪などと同じような流れにならない可能性が高くなります。特に薬物犯罪は外部との連絡を断たれ身柄拘束されますから、弁護士の役割は非常に大きなものになります。もし家族や友人が逮捕されたら、速やかに弁護士に依頼をしましょう。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

傷害罪で逮捕されたら弁護士に相談、傷害事件の示談交渉のポイントと慰謝料の相場
この記事で分かること 傷害事件で身近な人が逮捕された場合傷害罪と暴行罪、定義の違いは?...
-

「迷惑防止条例」とは?~痴漢などの犯罪に刑罰を与える各地の条例~
この記事で分かること 「迷惑防止条例」とは?東京都の「迷惑防止条例」による痴漢の規定「...
-

性犯罪で最も重い「強制性交等罪」(1)~「強姦罪」から改正~
この記事で分かること 「強姦罪」から「強制性交等罪」へ性犯罪の厳罰化が進む「非親告罪」...
-

この記事で分かること 強盗罪の定義とは?強盗罪は非常に重い刑罰が科せられる強盗が絡む他...
-

盗撮で逮捕されたら弁護士に相談!知るべき10のポイントと慰謝料相場を解説
この記事で分かること まず始めに、盗撮はどんな罪で逮捕されるのか盗撮で逮捕された場合に...
-

この記事で分かること 盗撮とは?事件になる典型的なケース盗撮行為で受ける刑罰公共の場所...
-

この記事で分かること 盗撮で逮捕されるときに適用される法令は2つある軽犯罪法と迷惑防止...
-

この記事で分かること 盗撮の構成要件とはどういう意味?軽犯罪法で規制される盗撮の構成要...
-

この記事で分かること 盗撮に関する刑罰・刑期・懲役についての規定盗撮で逮捕された場合は...