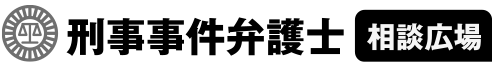未成年犯罪は弁護士へすぐ相談!子どもの人生・将来を救う弁護活動と少年法のポイント
- 2025年1月20日
- 12,909 view
- 犯罪の種類
- 刑事事件弁護士相談広場

少年事件は通常の成人の事件とは全く異なる手続きがとられます。刑事訴訟法が事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することを目的としている(刑事訴訟法、以下、刑訴法、1条)のに対して、少年法は少年の健全な育成という観点から、性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を講じること等を目的としています(少年法、以下、法令名なき時は同法、1条)。
少年事件で身近な人が逮捕された場合
少年事件と一口に言っても審判の対象となる少年を3種類規定しており、それぞれで手続きが異なります。まずは少年事件の基本的な部分から話を進めていきましょう。
少年事件とは
少年事件とは、家庭裁判所が扱う少年(20歳未満の者)が起こした事件です。近年、対象年齢を18歳に引き下げることを法務省が検討していることがニュースで伝わりましたが、実現までにはまだ時間がかかりそうです。少年法は審判の対象となる少年について①犯罪少年、②触法少年、③ぐ犯少年、の3種類に分類しています。ここでは主に犯罪少年について説明していきます。
3種類の少年
少年法の審判対象となる少年は①犯罪少年(罪を犯した少年)、②触法少年(14歳未満で刑罰法令に該当する行為をした少年)、③ぐ犯少年(保護者の正当な保護に服さない性壁があり、その性格や環境から将来、罪を犯し、または刑罰に触れる行為をするおそれのある少年)に分類されています。14歳未満は刑事未成年(刑法41条)のため刑罰を科されることはありませんし、ぐ犯は犯罪になりません。つまり、逮捕されるのは犯罪少年だけです。
少年事件の特殊性
少年の健全な育成という観点から少年法は構成されています。性格の矯正と環境調整に関する保護処分をすることで、健全な育成に寄与することが目的と言えるでしょう。その点が刑法を実現するための手続きを定めた刑事訴訟法とは根本的に違います。たとえば少年事件の審判は非公開とされ(22条2項)、公開すべきことを定めている(憲法37条1項)刑事事件の公判とは対象的です。逮捕後の手続きも捜査段階では大差はありませんが、それ以後は犯罪の嫌疑がある場合に全件が家裁送致になるなど、刑事事件とは異なります。
少年事件の検挙件数
少年による刑法犯等の検挙人員は平成27年で4万8680人、少年人口10万人あたり426.5人ですから、およそ0.43%ということになります(平成28年版犯罪白書、出典は警察庁の統計、触法少年の補導人員を含む)。
少年に対する処分の特例
少年事件の対象者が20歳未満ということで、少年法は特に処分において考慮されたものになっています。
18歳未満に死刑なし
罪を犯した時に18歳未満の者は死刑をもって処断すべき時は無期刑を科することになります(51条1項)。少年の可塑性(成長により性格が柔軟に変化すること)を考えての立法的措置です。このことは犯行時に18歳以上であれば死刑に処せられる可能性があることを示しています。実際に光市母子殺害事件の犯人は犯行時18歳1か月でしたが、最終的に死刑判決が確定しています。
懲役刑は不定期刑
少年(20歳未満の者)に対しては懲役刑を科す場合、不定期刑を言い渡します。これは短期と長期を定めるもので、たとえば10年以上15年以下といった言い渡しです。長期を定め、原則として長期の2分の1を下回らない範囲で短期を定めます。長期が10年未満の場合には、長期から5年を減じた期間を下回らない期間です。
無期刑と労役場留置
少年に対して無期刑をもって処断する時は、有期の懲役または禁錮を科すことができます。その場合、刑は10年以上20年以下で言い渡されます。また、少年に対する労役場留置は認められません(54条)。
身柄拘束された本人と外部との連絡
少年事件は概ね、成人と同じ捜査手続きを経ます。逮捕された被疑者については、電話やメール等で外部と連絡を取ることはできません。また、家族との接見(面会)が認められないのが原則です。ただし、弁護士との接見については認められます。
少年の勾留と勾留施設
少年も勾留されることがあり、その場合の要件は成人と同じです(刑訴法207条1項、60条1項)。ただし、勾留をするのはやむを得ない場合に限られます。また、勾留の場所については警察署の留置施設以外に少年鑑別所も可能です。家族との接見は逮捕の期間は、原則として認められません。接見できるのは勾留されてからです。なお、弁護士は勾留時はもちろん勾留前も接見できます。
弁護人の接見は憲法上認められた権利
弁護人依頼権は憲法34条前段で保障されている重要な権利です。逮捕された被疑者にとって、唯一の味方とも言えるのが弁護士です。弁護人や弁護人になろうとする者とは、立会人なくして接見し、または書類若しくは物の授受をすることができます(刑訴法39条1項)。
特に重要な初回の接見
弁護人(になろうとする者)の接見の中でも、特に初回の接見については弁護人の選任を目的としたり、取調べにあたり助言を得たりする最初の機会です。そして接見指定(刑訴法39条3項)と呼ばれる、捜査機関による接見の日時、場所の指定について捜査に顕著な支障が生じるのを避けられるかどうかを検討した上で、比較的短時間であっても、時間を指定した上で即時または近接した時点での接見を認めるようにすべきとしています。このように弁護士との接見については捜査機関も十分に配慮せざるを得ないシステムになっています。自らを法的に防御する能力が十分に備わっていない少年においては特にその点が意識されるべきです。
少年事件の逮捕からの流れ
逮捕され裁判が行われるまでの手続きは刑事訴訟法に規定されています。少年事件は捜査段階では成人事件とそれほど差異はありませんが全件家裁送致になるなど、その後の手続きは大きく異なります。
逮捕
逮捕は被疑者を強制的に身柄拘束する処分で、法定された短時間の留置を伴います。逮捕と一口に言ってもいくつかの種類があります。
逮捕には4種類
逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、準現行犯逮捕、緊急逮捕の4種類があります。事前に令状請求して逮捕するのが通常逮捕、令状請求する時間がなく逮捕後に令状請求しなければならないのが緊急逮捕で、(準)現行犯逮捕では令状は不要です。通常逮捕、緊急逮捕の逮捕権者は検察官、検察事務官または司法警察職員とされています。現行犯逮捕、準現行犯逮捕は官憲だけでなく私人も可能です(刑訴法213条)。
逮捕後の司法警察員の手続き
司法警察員(司法巡査を除く司法警察職員のこと、刑訴法39条3項)は被疑者に対して、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければなりません。そして、留置の必要がないと思料する時は直ちに釈放し、留置の必要があると思料する時は身体の拘束から48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官に送致する手続きをとらなければなりません(刑訴法203条1項)。
弁解の機会と取調
司法警察員は弁解を聞いて留置の必要性を判断しなければなりません。つまり釈放する権限を司法警察員が有しているわけです。もっとも弁解は弁解録取書にまとめられ、裁判で自己に不利な証拠となる可能性があります。弁解の機会に続いて取調が行われることが多いですが、その際には司法警察職員は被疑者に自己の意思に反して供述する必要がないことを告げる必要があります(刑訴法198条2項)。
送検
逮捕され、司法警察員に留置の必要があると判断されたら被疑者は検察官に送致されます。
送検の意味
送検とは、被疑者の身柄を検察官に送ることではなく、事件そのものを検察官に送ることを指します。つまり書類及び証拠物とともに被疑者の身柄を送致することで、それにより事件が検察官の扱いになることを意味します。
タイムリミット48時間
検察官送致には時間制限があり、被疑者の身柄拘束から48時間以内に書類及び証拠物とともに送致の手続きをしなければなりません(刑訴法203条1項後段)。手続きをすれば良く、被疑者の身柄が実際に検察に到着するのは身柄拘束から48時間を過ぎていても問題ありません。
司法警察員からの家裁送致
少年事件の場合、成人事件とは別のルートがあります。それが家裁送致です。捜査を遂げた結果、罰金以下の刑に当たる犯罪の嫌疑がある場合には、家裁に送致しなければなりません(41条)。実務では「直送」と呼ばれます。
簡易送致
極めて軽微な事件の時は、簡易送致が行われる場合があります。再犯のおそれがなく、刑事処分または保護処分の必要がなく、かつ、検察官又は家裁からあらかじめ指定されたものについては捜査報告書等を作成して、月に一回、一括して検察官又は家裁に送致するという制度です。イメージとしては成人事件の微罪処分に似ています。
勾留
検察官は送致された被疑者を受け取った時、留置の必要があると考えた場合は、裁判官に被疑者の勾留を請求します。裁判官が勾留決定をすれば、被疑者は勾留されます。
送致を受けた検察官の手続き
検察官は送致された被疑者を受け取った時は、弁解の機会を与え、留置の必要がないと判断すれば直ちに釈放することになります(205条1項前段)。逆に留置の必要があると考えた場合は、受け取った時から24時間以内、かつ、被疑者が身体を拘束されて(原則として逮捕の時)から72時間以内に裁判官に勾留を請求しなければなりません(同条1項後段、同条2項)。もっとも少年に対しては、やむを得ない場合にのみ勾留請求が認められます(43条3項)。
裁判官による勾留決定
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対して被疑事件を告げ、勾留質問を行います(207条1項が準用する61条)。勾留の理由がある場合には速やかに勾留状を発しなければならず、勾留の理由がない時には釈放を命じなければなりません。また、必要があれば事実の取り調べをすることができます。
勾留期間と延長
勾留期間は10日です。勾留請求の日から10日以内に公訴を提起しない場合には直ちに被疑者を釈放しなければなりません(208条1項)。初日は時間にかかわりなく1日として計算されます。また、やむを得ない事由がある時は、10日を超えない範囲で期間の延長が認められます(同条2項)。合計で10日を超えないのであれば、延長の回数に制限はありません。実務上、少年事件では勾留が満期になる前に家裁送致あるいは勾留に代えて観護措置決定がされる例が見受けられます。
勾留に代わる観護措置
少年事件では勾留に代わる観護措置の制度があります(43条1項)。
勾留に代わる観護措置
検察官は勾留の要件を満たすと判断した場合でも、この措置を請求ができます。その場合、基本的に勾留に関する規定が準用されます(刑事訴訟規則281条、282条)。身体を拘束する場合は少年鑑別所に送致され、当然に家裁送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされます(17条7項)。また勾留に代わる観護措置は10日間で延長の規定がありません(44条3項)。
身体の拘束がない勾留に代わる観護措置も
勾留に代わる観護措置においては、身体拘束のない家裁調査官による観護の方法も可能です(43条1項、17条1項1号)。これは少年を家庭などに置き、調査官が随時接触して観護目的を達成しようというものです。
家庭裁判所への送致
勾留もしくは勾留に代わる観護措置の間に、検察官は事件の捜査を進めます。犯罪が疑われる場合、家裁に事件を送致します。
全件送致主義
少年の被疑事件について犯罪の嫌疑がある場合、検察官はすべて家庭裁判所に事件を送致しなければなりません(41条、42条)。起訴するか否かを検察官の裁量に委ねる起訴便宜主義(刑訴法248条)の例外と言えるでしょう。
観護措置について検討
検察官から、もしくは司法警察員から事件の送致を受けた家裁では、裁判所に少年が到着してから24時間以内に観護措置をとるか否かを決定しなければなりません(17条2項後段)。観護措置は家裁が調査、審判を行うために少年の心情の安定、身柄の保全などの目的で暫定的に保護するための措置です。
観護措置決定手続き
観護措置は審判を行うために必要があるときにとられます(17条1項柱書き)。措置をとるに際しては人定質問や黙秘権の告知などに加え、措置が必要か否かを判断する上で必要な事項について審問、陳述を行い、決定されます。観護措置が取られないことになると、少年は釈放されますが、手続きは在宅のまま進められます。
家裁調査官による調査
事件の送致を受けた家裁では、調査官に命じて少年に関して様々な調査を行います。その結果を参考にして審判を行い、処遇についての決定をします。審判不開始の決定がされることもあります。
観護措置
家裁が観護措置決定をすると、在宅の場合を除き、少年は少年鑑別所に送られます。
観護措置の期間
観護措置の期間は2週間を超えることができません(17条3項)。しかし多くの場合、更新され、現実には4週間に及ぶ場合が多くなっているようです。更新は原則1回だけですが、死刑、懲役又は禁錮にあたる事件で非行事実の認定について証人尋問等を行うことを決定したものなどで、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがある場合には、更新はさらに2回可能です。
観護措置についての通知
家裁が観護措置をとった場合、速やかに保護者及び付添人(弁護士等)のうち、適当と思われる者に通知がされます(少年審判規則22条)。
少年鑑別所における面会
少年が少年鑑別所に送致された時、付添人、弁護人等は決められた時間内であれば立会人なしに少年と面会できます(少年鑑別所法81条本文カッコ書き)。保護者等の面会は、それが必要な者である場合は原則として認められますが、親ではなく職員が立ち会うことがあります(少年鑑別所法81条)。
審判開始決定と不開始決定
家裁送致を受けた少年について、家裁は審判を開始するか否かを決定します。
少年審判の対象
少年審判手続きの審理及び判断の対象は、非行事実と要保護性です。果たして非行事実があったのか、そして少年の性格や環境から、再び非行に走ることはないか等を判断します。矯正可能性や保護処分が最も適している手段かも判断すべきとする考えもあります。
家裁の決定
家裁は調査の結果、相当であると認める時は、審判を開始する旨の決定を行います(21条)。また、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認める時は審判を開始しない旨の決定をしなければなりません(19条1項)。審判の不開始決定がなされると少年にその旨が伝えられて事件が終了します。
少年審判での処分
少年審判が行われた場合、終局決定として4通り(審判不開始決定を含まず)、中間決定として試験観察の5通りの処分がなされます。
不処分
審判の結果、保護処分に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときはその旨の決定をしなければなりません(23条2項)。その場合、事件は終了します。
知事又は児童相談所長送致
家庭裁判所は調査の結果、児童福祉法の規定による措置を認めるとき、事件の権限を有する知事又は児童相談所長に送致しなければなりません(18条1項)。対象は18歳未満の児童です。児童福祉法の規定による措置で、具体的には訓戒又は誓約書の提出、児童福祉司もしくは児童委員等による指導、里親等への委託、児童養護施設や児童自立支援施設への入所措置などがとられます。犯罪傾向がそれほど進んでおらず、要保護性が強い少年の場合が相当すると言われます。
保護処分
保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設又は児童養護施設への送致、③少年院送致の3種類があります。①の保護観察は施設に収容せず、社会生活をしながら保護観察所の指導監督によって更生をはかります。遵守事項が守られない等の場合には少年院送致などの処分がされる場合もあります(26条の4)。②については施設に収容する処分ですが、開放施設です。実際に入所しているのは中学生が中心と言われています。それほど非行性が進んでいない児童が対象と言えます。③の少年院送致は、少年を強制的に収容する保護処分です。
試験観察(中間処分)
審判に付された少年の終局処分の前に行う中間処分です(25条)。家庭で遵守事項を守って生活をし、定期的に調査官と面会する在宅試験観察と、調査官による観察に、保護者以外の適当な施設や団体に少年を預けて補導委託先で指導を受ける補導委託があります。
逆送
家裁が刑事処分を相当と判断したとき等には検察官に送致され、刑事手続きに付されます(19条2項、20条)。実務では逆送と呼ばれます。逆送されるのは調査・審判時に本人が20歳以上であることが判明したときです。また、刑事処分が相当であると認めるとき、故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件で、その行為を行った時に16歳以上だったとき(20条2項)です。
起訴
家裁から逆送された場合、家裁の少年事件は終了し、事件は管轄地方裁判所に対応する検察官に送致されることになります。
検察官による起訴と少年法の制約
起訴は検察官が行い、その権限は検察官のみが行使できるものです(247条)。これを起訴独占主義と言います。また、たとえ犯罪の証明が十分であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により起訴しないこともできます。これを起訴便宜主義と呼びます。つまり起訴するかしないか、検察官が一切の権限を有しているわけです。しかし、少年事件からの逆送の場合、検察官は公訴提起に足りる犯罪の嫌疑があると思料する時は公訴提起をしなければなりません(45条5号)。
起訴便宜主義が一定の制約を受けているわけですが、家裁の刑事処分相当の判断に拘束されていると言えるかもしれません。しかし、調査・審判時に20歳以上と判明した時はそうした起訴強制は働かず起訴猶予になります。また、情状等で新たな事情を発見した場合等は起訴強制とはなりません。その際は家裁に事件を再送致しなければなりません(42条1項前段)。
起訴された場合の被疑者の勾留
起訴された被疑者は被告人となります。被疑者の段階で勾留されていて被告人になった後も勾留する場合には、検察官が起訴状を提出すると自動的に勾留が継続されます。被告人の拘禁場所は刑事施設ですから(刑事収容施設法3条3号)、通常は起訴されると拘置所に移送になります。しかし、現実の運用は拘置所の混雑などでスムーズにはいかないようです。その場合はしばらく留置場に勾留されることもあるようです。
被告人になったことによる効果
被疑者が被告人になることで、捜査機関による接見指定はできなくなります。これは接見指定が「公訴の提起前に限り」行えると規定されているためです(39条3項)。もっとも被告人が余罪について起訴前勾留されている時は指定が可能です。
公判
検察官による起訴があると、公判が開かれます。
裁判所の手続き
裁判所は公訴の提起があった時は、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければなりません(271条1項)。裁判長は公判期日を定め(273条1項)、検察官、弁護人に通知します(同条2項)。
弁護人選任権等の告知
裁判所は公訴の提起があったときは、遅滞なく被告人に弁護人を選任できる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任できない時は弁護人の選任を請求できる旨を知らせなければなりません(272条1項)。弁護人の選任の告知は逮捕時、勾留質問時にもされますが、ここでも行われます。このように何度も告知を義務付けるのは、憲法37条3項で保障された弁護人選任権を実質的に保障する意図であるとともに、刑事事件における被疑者・被告人の権利の保護のために弁護人の果たす役割の大きさを示すものと言えます。
公判手続きは大きく分けて4つ
公判手続きは、冒頭手続き-証拠調べ-弁論-判決という流れになります。冒頭手続は、人定質問(刑事訴訟規則196条)→検察官による起訴状の朗読→裁判長による権利告知→被告人及び弁護人が事件について陳述という順番で行われます。裁判長による権利告知とは、終始沈黙し、または個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨、陳述がされた場合、自己に不利益な証拠ともなりうること等を告げます。
少年事件における弁護活動のポイント
少年事件で逮捕された場合、逆送され刑事手続きに進んでからも示談を成立させるなどの弁護活動が考えられますが、少年事件の手続きの中での弁護活動が重要です。
逮捕直後の弁護活動
少年事件も成人事件と同様、逮捕直後から弁護士を依頼して、身柄の拘束からの解放のための活動をするのが効果的です。
逮捕直後に依頼、早期の接見が重要
身体を拘束されている被疑者又は被告人は、立会人がない状態で弁護人または弁護人となろうとする者と接見し、または書類もしくは物の授受をすることができます(39条1項)。法的な知識が十分ではない少年のために、一刻も早く弁護士が接見して、基本的な注意を与えるべきです。弁護士が自分の味方であることすら理解していないことも考えられます。通常、逮捕後は家族との接見は禁止されますが、弁護人や弁護人になろうとする者に対しては、接見を禁止することはできません。
その他の弁護活動
少年事件も捜査段階では成人事件と大差ありませんから、弁護活動のポイントも同様です。司法警察員に対しては検察官送致をしないように働きかけることが考えられます。検察官送致された場合も、少年はやむを得ない場合にのみ勾留請求が認められますから、そのような事情がないことや、少年の被る不利益を具体的に検察官や裁判官に訴えて勾留請求をしない、勾留決定をしないよう働きかけることで弁護活動ができます。
家裁送致後の弁護活動
捜査段階での弁護人選任の効力は、家裁送致時に失われます。そのため、家裁送致後は付添人として選任されないと弁護活動ができません。また、観護措置がとられると事実上2週間は身柄を拘束されることになり、職場や学校に長期間行けなくなってしまいます。そのため、弁護士としては観護措置が不要であることを家裁に対して主張することが考えられます。具体的には身柄確保の必要性がないこと、長期間登校できないことで被る損害が大きいことなどです。
付添人の役割
家裁送致された時に少年及び保護者は家裁の許可を得て付添人を選任できます(10条1項本文)。ただし弁護士を付添人に選任する場合には、家裁の許可は必要ありません。付添人は少年の権利を守る弁護人的性格と、少年保護事件の目的が適正に実現されるように、家庭裁判所に協力して援助します。
示談が重要なポイント
成人事件同様、少年事件でも示談が事件の早期の解決に重要な役割を果たします。
少年事件の示談の特性
少年は通常、示談を有効に成立させるだけの資金がありません。そのため保護者の協力を求める必要があります。特に示談が成立することによって、要保護性が解消される方向へ働く可能性があり、保護処分にも影響を与える可能性があります。
示談の法的性質
刑事裁判は犯罪を犯した者に対して国家刑罰権を実現する裁判ですから、当事者間の合意でその国家刑罰権を消滅させることはできません。示談にはそうした効力はないということです。しかし、強姦罪等の親告罪の場合、示談が成立して告訴を取り下げることになれば検察は公訴提起ができなくなります。また、示談の成立により被害者感情の宥和や、被疑者・被告人の反省、生じた損害の金銭的な回復などから起訴猶予等になる可能性もあります。かりに有罪判決でも情状面での酌量が期待できます。
被害者への謝罪が重要
示談を成立させるためには被害者への謝罪は前提になります。示談の目的が被害者感情を和らげるところにありますから、そのためには加害者の真摯な反省が必要です。その上で、損害が生じたらその補償をするとともに、慰謝料も支払って精神的な損害も賠償するのは当然です。
少年事件の弁護活動にかかる費用相場
弁護人が事件を担当することになると、解決のための費用がかかります。示談には金銭が必要になりますし、示談をする弁護士の費用も必要になります。
示談金
被害者のいる犯罪で示談をする場合には金銭が必要になります。被害者の財産上の損害を金銭によって原状回復させる必要があります。さらに慰謝料という形で精神的な損害についても賠償をすることになります。
生じた損害は示談金で賠償を
事件になったことで何らかの損害が発生した場合(アルバイトに遅刻し時給が少なくなった等)も、その賠償をすべきです。
慰謝料は示談金の一部
実費以外にも慰謝料が必要です。被害者の負った不快感、屈辱感、恐怖心など精神的損害を金銭で賠償する必要があります。その意味から慰謝料は示談金の一部であると言えます。
慰謝料の相場は?
被疑者・被告人にすれば慰謝料の相場があれば知りたいことでしょう。しかし、事件で被害者の受けた不快感、屈辱感、痛みは、その犯罪の態様、被害者の年齢、犯行時の状況等により、それぞれでしょう。そうした事情を総合的に判断して、被害者が被疑者・被告人の処罰を望まないというレベルの金額が相場と言えるかもしれません。
弁護士費用
示談をするには弁護士の力が必要です。被疑者の親族が被害者と示談交渉をしようと思っても、被害者は自分の住所など連絡先を知られたくないと考える場合が多いでしょうから、交渉のテーブルにつくことさえ困難な状況が予想されます。そうなると弁護士に依頼するのが示談を成立させるには早道と言えそうです。

こちらも読まれています
相談料
弁護士への相談料は、最近は初回無料としていることが多いようです。2回目以降は1回5000円程度が相場と言えます。
接見費用
被疑者・被告人との接見の場合、事務所から勾留場所、少年鑑別所まで行く必要があります。また、身柄拘束を解くための行動は、司法警察員、検察官、(家裁)裁判官の手続きに時間制限がある以上、迅速に行う必要があります。そのため費用としても勾留場所、少年鑑別所との距離にもよりますが1回3万円前後はかかるのが普通です。
着手金
弁護士が事件を担当する場合、依頼人は着手金を支払うことになります。既述したように少年事件では捜査段階での弁護人選任の効果が、家裁送致されると消滅し、新たに付添人として選任される必要があります。そのため通常、二度の着手金が必要になります。事件の重大さ、困難さ等によっても差異はありますが捜査段階の着手金で30万円〜40万円、審判段階でも若干低いぐらいが相場と言えるでしょう。捜査段階からの選任であれば審判段階での着手金を必要としない弁護士もいるようです。
自白事件の成功報酬
自白事件であっても弁護士の活動によって身柄の解放に成功したり、観護措置(少年鑑別所行き)を回避したり、審判での不処分などの場合は成功報酬が別途必要になります。事案の困難さや、処分によっても異なりますが、10〜30万円程度が相場でしょう。
否認事件の成功報酬
否認事件では家裁不送致、非行事実なしの不処分決定を目指すことになります。その場合には事実関係を争い、時間と手間をかけて争いますから、当然、成功報酬は高く設定されます。30〜50万円程度は必要でしょう。
逆送された場合
逆送された場合は通常の刑事事件と同じ手続きが進みますから、新たに着手金が必要になるのが普通です。また、接見などの費用、さらに成功報酬などが別途求められることになります。
実費
弁護士が活動にあたって実際に経費としてかけた分は依頼人に請求されます。接見するための交通費や、通常の通信費などです。
日当
出頭したり、出張したりした際の日当が必要になります。概ね1回で3万円前後でしょう。また着手金を支払わずに、実際にかかった日数、時間によって支払額を決定する「タイムチャージ」という方式で支払う方法もあります。着手金で一律に支払うのではなく、かかった時間だけ支払うというものですが、大きな事件になると日数がかかり、着手金方式より多く支払わなければならないということも考えられます。
少年事件は時間が勝負!
少年事件は警察-検察-家裁と時間をかけずに手続きが進んでいきます。早期の対策こそが重要です。
逮捕から72時間以内の弁護活動が重要な理由
通常の事件処理では逮捕から72時間以内に勾留請求、勾留に代わる観護措置の請求がされます。そこに至る前に解放に向けて努力することが被疑者の身体の解放に向けては重要です。
72時間が持つ意味
逮捕から72時間以内に、司法警察員による検察官送致、検察官による勾留請求もしくは勾留に代わる観護措置が行われます。既述したように、被疑者の身体の解放に向けてそれぞれの手続きの中で行うべきことは異なります。適切な時期に適切な方法で解放に向けて動かないと、手続きだけが進んでいき身体の拘束からの解放がそれだけ遅れます。勾留決定や勾留に変わる観護措置がされてしまうと10日間、身柄の拘束が続くことになりますから、その前の逮捕から72時間以内に勾留決定されないようにすることが重要です。また、少年事件では勾留満期前に家裁送致になることが多いことにも注意が必要です。
勾留決定、勾留に代わる観護措置への準抗告
逮捕から72時間を過ぎて勾留決定がされても、準抗告で争えます。勾留に代わる観護措置も準抗告で争えると考えられています。
観護措置が私生活に与えるダメージ
家裁送致されて観護措置になると、通常2週間は少年鑑別所に入ることになります。さらに延長される可能性もあります。
2週間以上の拘束による影響
観護措置になった場合、2週間から8週間は身柄を拘束されるのが普通です。その間は学校を休まなければなりません。事件で退学処分等の可能性はありますが、そのような処分がなかったとしても出席日数が不足するでしょうし、試験期間にかかれば受験できず、留年の可能性が出てしまいます。少年期における1年の遅れは、更生したとしてもずっと尾を引きます。それが少年保護の趣旨に沿うのか、難しい部分です。大学を卒業して就職活動をするにしても高校卒業に4年かかっている事情は当然、聞かれるでしょう。そのような意味で長期の身柄拘束によって、少年の将来を大きく制約することになりかねません。
弁護士への迅速な依頼が問題解決のカギ
観護措置の要否は家裁送致されてから24時間以内に判断されます(17条2項後段)。そのため家裁送致後数時間で判断されているのが実情です。弁護士による迅速な行動が観護措置を防ぐには必要ですから、その前提として依頼人による早期の、かつ、迅速な依頼が求められます。
少年事件による人生への影響
少年事件の処分によって、その後の人生は大きく変わります。
逮捕、観護措置、少年院送致による学校への影響
身柄の拘束等により真っ先に影響が出るのが、在籍している学校です。
逮捕の事実はすぐに学校へ?
少年事件の場合、通常、警察から学校に連絡が入ると考えた方がいいでしょう。それは各市町村の教育委員会が都道府県警察本部と「児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度」という協定を交わしている場合が多いためです。通常、協定には生徒の逮捕、ぐ犯事案等で警察署長が学校への連絡の必要性を認める事案では「学校に連絡する」という内容が盛り込まれています。また、家裁調査官が調査のために学校に連絡をして、それで事件が明らかになる場合もあります。
いきなり退学処分も
事件について学校が知った場合、学校としては退学処分にする場合もあります。特に私立高校の場合、学校のイメージを大きく損なうため、そうした処分について迅速に行われる傾向があります。仮に処分がなかったとしても、長期間の身柄拘束による出席日数不足、定期試験の受験ができないなどの影響は免れないでしょう。
少年事件の家族への影響
少年の逮捕で精神的に大きなショックを受けるのは家族でしょう。子供が犯罪を犯したことを、簡単に受け入れたくないのは親としては当然です。それ以外にも、ご近所付き合いにも影響が出るのは避けられません。
報道がきっかけで公になることも
子供が長期間、不在であればご近所もおかしいと思うでしょう。その前に事件が重大であれば報道で明らかになる可能性もあります。メディアは少年法61条の趣旨から実名報道することはほとんどありませんが、匿名で報じられてもネットが発達した現代ならメジャーな掲示板サイトなどでは人物の特定が直ちになされてしまいます。
事件で自宅を捜索される可能性も
報道がなくても、捜査機関は捜査のため必要があれば令状をとって家宅捜索をすることもあります(218条1項)。そうなれば大勢の捜査員が自宅に入ってくるためご近所の知るところになってしまいます。身内が逮捕された、自宅を捜索されたという事実をご近所に知られれば、家族としてはまともに外を歩くのも憚られる状況となるでしょう。
少年事件の結婚・人間関係への影響
逮捕という前歴、少年事件での処分歴は結婚や、周囲の人間関係にも大きな影響を及ぼします。
結婚への影響
結婚(婚姻)は両性の合意のみに基づいて成立しますが(憲法24条1項)、親や周囲の意見も影響するでしょう。そうなると少年事件の影響は少年の将来の結婚にも及んでくるのは必至です。
当人でも、親でも逮捕は結婚に悪影響
婚姻当事者が「少年院を出た人とは結婚したくない」と思うことがあるかもしれません。それは当人の考えですから仕方がないことでしょう。しかし、当人はそれを知りながらも結婚したいと願った時に、その親が「少年院にいた人とは結婚してほしくない」と言い出すことは十分に考えられます。結婚は親を含めて一生の付き合いですから、慎重さを求めるのが普通の親の考えでしょう。その意味で少年事件が将来の結婚に与える影響は小さくありません。
処分歴を調べられ、知られてしまうことも
当人の少年事件での処分歴は、そう簡単に他人に知られることはありません。前科前歴はみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益であると最高裁も判示しています(最判昭和56年4月14日)し、少年事件なら尚更です。そのため、第三者が公的機関からそのような事実を知ることはほとんどあり得ません。しかし、今でも結婚前に相手の身上調査をする場合もあり、民間の調査会社を使って近所の聞き込みをすることはあり、そのような場合に隠していた少年事件の履歴が明らかになってしまうことがあります。そのような調査の是非はともかく、そうした調査によってせっかくの結婚が破談になる可能性は否定できないでしょう。
前歴を隠していたことが離婚の原因となるか
仮に少年事件で処分されたことを隠して結婚し、その後、発覚した場合は離婚の原因となるでしょうか。協議離婚(民法763条)は可能でしょう。裁判上の離婚の場合は、そのような前歴や、それを隠していたことが「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に相当するか否かという問題になります。一度だけの軽微な事件であれば離婚原因とするのは難しいかもしれませんが、可能性が全くないとは言えないでしょう。
人間関係その他への影響
少年事件での処分は結婚だけでなく、人間関係にも影響を及ぼすことは考えられます。
友人との信頼関係
それまで親しかった友人が事件後、よそよそしくなることはあるかもしれません。スピード違反で反則金を支払ったレベルならよくある話と言えるでしょうが、身柄を拘束され、処分を受けるのであれば、少年とはいえ遵法精神に欠ける人間とみなされることは覚悟しないといけないでしょう。
就職への影響
以前は就職活動で履歴書を提出する際には「賞罰」という欄があり、前科前歴はそこに記すようになっていました。最近はプライバシーの保護を重視し、そのような欄がない履歴書が一般的です。しかし、金融機関など職務の遂行上、遵法精神のある職員を求めている業種では任意の形をとって、前科前歴を聞いてくることがあると言われます。虚偽を述べれば後で内定取消しになるのは確実です。その意味では少年事件の処分歴は就職活動に大きな影響を与えるでしょう。
旅行への影響
アメリカに旅行に行く場合、日本人は90日以内の観光であればビザは不要です。しかし、逮捕歴があると、査証免除プログラムを利用しての渡航はできなくなります。ビザを申請して、領事による面接を受けることを義務付けられます。
少年事件で弁護士に依頼するメリット
少年事件では弁護士がつくことで様々なメリットがあります。
示談交渉による問題解決
身柄の拘束を解くため、あるいは審判における決定で示談が成立しているかどうかは大きなポイントになります。
身体の拘束からの早期の解放
示談が成立していることにより、たとえば観護措置をしないように裁判官に働きかける場合にもプラス材料になるでしょう。また、家裁調査官の調査でも要保護性判断等で有利な材料となると思われ、その結果、審判不開始となる可能性も考えられます。
示談は審判における重要な考慮要素
被害者との示談が成立したからといって、家裁送致がされなくなるということはありません。しかし、審判において被害者との示談が成立していることは重要な要素となります。たとえば真摯な反省が感じられる謝罪文の送付があって被害者が宥恕の気持ちを強めたことが認められれば、要保護性という点では、その必要性は低いと判断される材料となる可能性はあります。
外部への連絡・説明
逮捕され、身柄を拘束されている被疑者の少年は外部との連絡を取る手段を持っていません。そこで弁護士が重要な役割を果たすことになります。
外部連絡は弁護士のみ可能
逮捕されると被疑者は外部と電話やメールなど、一切の連絡手段を使うことができなくなります。家族についても、勾留されるまでは原則として接見できません。そのような状況で被疑者と連絡を取れるのは弁護士だけです。被疑者の状態を家族や会社に性格に伝えることができ、外部との唯一の窓口として機能します。
手続きの見通しなど説明が可能
家族や会社の関係者が突然の逮捕で、どのような手続きが進むのかも分からない状況の中、弁護士は刑事訴訟法、刑事訴訟規則、少年法に基づく手続きの流れを熟知していますから、その後のことを予測することができます。身柄の拘束を解くためにどのタイミングで何をすればいいか、家族はどう協力すべきか、適切にアドバイスをして少年とその関係者のために力になることができます。
処罰の軽減、回避につながる弁護活動
弁護士は身柄の拘束を早く解くこと、処罰を軽減、回避するための活動を行います。
示談の重要性と効果
弁護士が行う活動で最も重要なのが示談交渉でしょう。被害者に真摯に謝罪し、経済的損害、精神的損害を賠償することで被害者感情をやわらげることが大事です。示談が成立することで、観護措置の回避、審判不開始決定、審判での不処分、少年院送致の回避などの効果が考えられます。
早期の依頼で解放へ様々な活動が可能
少年が逮捕された直後に依頼を受けた場合、弁護士は司法警察員に検察官送致をしないよう働きかけたり、送致されても検察官に勾留請求をしないように働きかけたりすることが期待できます。家裁送致されても示談を成立させることや、要保護性の消滅などを主張して観護措置を回避することや、審判で不処分を訴えるなどの活動が可能です。
以上のように少年事件における弁護士の果たす役割は非常に大きいものがあります。刑事事件では被疑者は外部との連絡を断たれ、身柄拘束のための活動や外部との連絡ができるのは弁護士だけです。特に逮捕後、72時間で手続きは大きく進みますから、迅速な対応が必要となります。自分の子供が逮捕された時には、すぐに弁護士に相談すべきでしょう。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

傷害罪で逮捕されたら弁護士に相談、傷害事件の示談交渉のポイントと慰謝料の相場
この記事で分かること 傷害事件で身近な人が逮捕された場合傷害罪と暴行罪、定義の違いは?...
-

「迷惑防止条例」とは?~痴漢などの犯罪に刑罰を与える各地の条例~
この記事で分かること 「迷惑防止条例」とは?東京都の「迷惑防止条例」による痴漢の規定「...
-

性犯罪で最も重い「強制性交等罪」(1)~「強姦罪」から改正~
この記事で分かること 「強姦罪」から「強制性交等罪」へ性犯罪の厳罰化が進む「非親告罪」...
-

この記事で分かること 強盗罪の定義とは?強盗罪は非常に重い刑罰が科せられる強盗が絡む他...
-

盗撮で逮捕されたら弁護士に相談!知るべき10のポイントと慰謝料相場を解説
この記事で分かること まず始めに、盗撮はどんな罪で逮捕されるのか盗撮で逮捕された場合に...
-

この記事で分かること 盗撮とは?事件になる典型的なケース盗撮行為で受ける刑罰公共の場所...
-

この記事で分かること 盗撮で逮捕されるときに適用される法令は2つある軽犯罪法と迷惑防止...
-

この記事で分かること 盗撮の構成要件とはどういう意味?軽犯罪法で規制される盗撮の構成要...
-

この記事で分かること 盗撮に関する刑罰・刑期・懲役についての規定盗撮で逮捕された場合は...