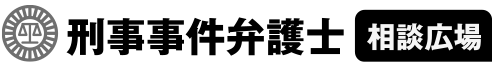万引き、窃盗で捕まったら弁護士は必要?示談交渉のポイントと示談金の相場
- 2025年1月20日
- 21,175 view
- 犯罪の種類
- 刑事事件弁護士相談広場

スーパーマーケットが、私服の警備員を雇って万引きの犯人をつかまえるドキュメンタリーがニュース番組で報じられます。万引きは私たちの日常生活のすぐ側で起きている犯罪と言えるでしょう。しかし、万引きは窃盗罪という犯罪です。逮捕されれば警察から検察へ送られ、裁判所で有罪判決を受けて場合によっては刑務所に入ることもあります。窃盗罪という古典的で一般的な犯罪について説明します。
万引き・窃盗で身近な人が逮捕された場合
刑法には「万引き」という言葉は出てきません。あくまでも窃盗罪(刑法235条)です。窃盗罪とはどういう罪で、逮捕された場合、被逮捕者はどのような状況になるのでしょうか。
窃盗罪とは?
極めて抽象的に表現すれば、窃盗罪は他人の物を盗む罪です。しかし、他人が預かっている自分の物を無断で持ち去ることや、相手を困らせる目的で持ち去ることが窃盗になるのか等、様々な問題があります。
窃盗罪の構成要件と法定刑
窃盗罪(刑法235条)の構成要件(犯罪として法律上規定された行為の類型)は①他人の、②財物を、③窃取したこと、④不法領得の意思の存在、です。そのため窃盗罪は「他人の占有する他人の財物を、占有者の意思に反して取得すること」と定義できます。そして自己の財物であっても他人が占有するとき等は、他人の財物とみなされるため(刑法242条)、窃盗罪が成立することになります。法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
「財物」とは?
窃盗罪の財物についてはいくつかの考え方がありますが、必ずしも有体物である必要はなく、管理可能性があれば足りるとするのが判例です。電気については条文(刑法245条)で財物とされていますし、ガスも財物とされています(大判明治37年4月28日)。
「窃取」とは?
窃取は一般的には「財物の占有者の意思に反し、自己の占有に移すこと」と定義されます。占有は財物に対する事実的支配と考えればいいでしょう。簡単にいえば、他人のものをその人の意思とは関係ないところで盗み、自分の占有物にするということです。
窃盗の手口は万引きが圧倒的多数
平成27年の窃盗罪による検挙件数は22万6001件でした。手口別にみると万引きが8万2257件と36.4%を占めて断然のトップです。2位の空き巣1万6638件(7.4%)を大きく上回っています(平成28年版犯罪白書)。
窃盗罪、どこから着手か
窃盗罪でどこから実行の着手があったのかが問題になることが多くあります。特に万引きと呼ばれるスーパーマーケット等での商品の窃取については、どこから犯罪が成立するかが検挙のポイントになります。実行の着手時期と既遂と未遂の分岐点を見てみましょう。
実行の着手はどこから
犯罪の実行に着手して遂げなかった者は未遂犯です(刑法43条参照)。つまり実行の着手が認められれば少なくとも未遂犯として処罰の対象となります。
実行の着手はどの時点で認められるのか
実行の着手の判断の仕方は様々な考え方がありますが、一般的には「構成要件の実現に至る現実的危険性を含む行為を開始した時点」と考えられています。犯罪として法律上規定された行為の類型が実現しそうになる、漠然とした危険性ではない現実的な危険性を含む行為の開始時点でしょう。噛み砕いて言えば「放っておけば、犯罪になってしまうのが確実な行為が始まった時」と考えればいいでしょう。
すりの実行の着手
ズボンの後ろのポケットから現金が出ているのを見て、その窃取を狙ってポケットの外側に触れた段階で窃盗の実行の着手が認められています(東京高判昭和31年10月24日)。現金がポケットから出ている所へポケットに手を触れるのですから、窃盗の実現に至る現実的危険性という点では実行の着手を認めるのが自然でしょう。もっとも相手が財布を持っているかどうか、ポケットの中にあるか等、衣服の外から確認して触る「あたり」と呼ばれる行為は実行の着手とは認めないのが一般的です。
侵入窃盗の実行の着手の例
他人の家屋に侵入して窃盗を行う場合について、侵入した段階で実行の着手と言って良さそうですが、実際は住居に侵入してから金目のものを盗もうとしてタンスに近づいた段階で実行の着手があったと判断されています(大判昭和9年10月19日)。一方、土蔵や家屋内にある「内蔵」と呼ばれる場所での窃盗については、そこへの侵入行為(鍵や壁の破壊行為等)を開始した時点で実行の着手を認めています(大阪高判昭和62年12月16日)。これは土蔵などが財物の保管のためだけに存在するからです。家屋に侵入してタンスの方に向かったこととの比較を考えれば判例の考えは当然でしょう。
スーパーマーケットでの窃盗
テレビ番組等でよくみるスーパーマーケットでの私服警備員による万引き犯に対するドキュメンタリーでは、警備員は必ず被疑者が店外に出た所で声をかけています。そのため、店外に出た時が窃盗罪成立の時と考えている人が多いのではないでしょうか。
既遂と未遂の分岐点
窃盗は「他人の占有を侵害して、財物を自己の占有に移した時」に既遂に達します。どのような状況で自己の占有に移したかは、たとえば商品の管理の状況、建物の様子、財物の性質、大きさ等によって異なるでしょう。一般的には商品が店舗内にあれば、店側の管理できる状態ですから占有は店にあると考えられます。そうであれば、店外に持ち出したところで店の占有が失われて万引きした者の占有に移転し、既遂に達するという考えは成立します。
レジ線を超えたら成立か
窃盗の既遂は店外に持ち出した時としても、スーパーマーケットでの窃盗の既遂時期が争われた事件では、レジの線を超えて持ち出したら既遂であるとの判断がされました(東京高判平成4年10月28日)。事案は買い物カゴに35点の商品を入れた被疑者が、レジを通らずにサッカー台の上に置き、店の備え付けの袋に入れたところで警備員に声をかけられたというものです。
レジ線の外側に出た段階で既遂とした理由を同判決は「買い物かごに商品を入れた犯人がレジを通過することなくその外側に出た時は、代金を支払ってレジの外側へ出た一般の買物客と外観上区別がつかなくなり、犯人が最終的に商品を取得する蓋然性が飛躍的に増大すると考えられるから」としています。もっともこれがレジの内外がはっきりしないような構造の店舗の場合にまで適用されるかは、微妙な部分があります。そうしたことを考えてテレビで見る私服警備員は、「大事をとって」被疑者が店舗の外に出た時に声をかけるという運用にしているものと思われます。
小物をポケットに入れた場合
レジ線を超えない場合でも既遂になる場合があります。商品を買い物カゴに入れずに直接、ポケットや持っているカバンの中に入れた時です。古い判例ですが、店頭にあった靴下一足を懐に入れた時に既遂に達するとしています。「店頭にある靴下を手にし、これを懐中に収めたる行為は、財物を自己の事実上の支配内に移したるものなる・・その行為は窃盗の既遂罪を構成するものとす」(大判大正12年4月7日)。現代のスーパーマーケットの売り場においても同じでしょう。
テレビをトイレに隠した場合
大型店で液晶テレビを売り場から持ち出し、男子トイレの洗面台の下の収納に隠したという事件がありました。この事件ではテレビを収納棚に隠した時点で窃盗が既遂に達すると判断されました。「被告人は、本件テレビをトイレの収納棚に隠し入れた時点で、被害者である本件店舗関係者が把握困難な場所に本件テレビを移動させたのであり・・これを店外に運び出すことが十分可能な状態に置いたのであるから、本件テレビを被害者の支配内から自己の支配内に移したということができ、本件窃盗を既遂と認めた原判決は正当」(東京高判平成21年12月22日)という理由でした。
「払えばいいんでしょ!」は通用するのか
既遂との関係を考える時に、テレビで万引き犯が逮捕された時によく言うセリフに「払うわよ」、「払えばいいんでしょ」というのがあります。これは法律の世界では通用しません(一般の世界でも通用しないでしょうが)。窃盗が既遂に達した場合とは、犯罪(構成要件に該当する違法で有責な行為)が成立しているわけです。代金(相当額)を支払うことによって成立した犯罪が不成立にはなることはありません。そもそも店側にそうした代金相当額の受領義務はありません。仮に当事者間で代金相当額の支払いがあった場合、民事上、不法行為責任を追及しないことの合意が生じるかもしれませんが、刑事上の責任はそれとは別次元の問題です。
身柄拘束された本人と外部との連絡
逮捕された被疑者については、電話やメール等で外部と連絡を取ることはできません。また、家族との接見(面会)が認められない場合があります。ただし、弁護士との接見については認められます。
家族との接見、逮捕直後は原則不可
家族との接見は逮捕から勾留されるまでの間は、原則として認められません。接見できるのは勾留されてからです。もっとも実務では、担当の司法警察員が認めれば家族との接見を認める運用をしているようです。そして検察官が被疑者を受け取ってから留置の必要があると思料する時に裁判所に勾留請求し、認められれば被疑者は勾留されます。勾留決定がされた後、家族は接見できますが逃亡し、又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、接見禁止にすることができます(刑事訴訟法、以下法令名なきときは同法、207条1項が準用する81条)。なお、弁護士は勾留時はもちろん勾留前も接見できます。
弁護人の接見は憲法上認められた権利
弁護人依頼権は憲法34条前段で保障されている重要な権利です。逮捕された被疑者にとって、唯一の味方とも言えるのが弁護士です。弁護人や弁護人になろうとする者とは、立会人なくして接見し、または書類若しくは物の授受をすることができます(39条1項)。
万引き・窃盗事件の逮捕からの流れ
窃盗事件に限らず、逮捕され裁判が行われるまでの手続きは刑事訴訟法に規定されています。その手続きの中で釈放されたり、不起訴になったり、起訴されても保釈になったり、様々な状況が起こり得ます。ここではその流れを見てみましょう。
逮捕
逮捕は被疑者を強制的に身柄拘束する処分で、法定された短時間の留置を伴います。逮捕と一口に言ってもいくつかの種類があります。
窃盗罪は4種類すべての逮捕の対象
逮捕には通常逮捕、現行犯逮捕、準現行犯逮捕、緊急逮捕の4種類があります。事前に令状請求して逮捕するのが通常逮捕、令状請求する時間がなく逮捕後に令状請求しなければならないのが緊急逮捕で、(準)現行犯逮捕では令状は不要です。通常逮捕、緊急逮捕の逮捕権者は検察官、検察事務官または司法警察職員とされています。司法警察職員とは巡査を含む警察官という理解でいいでしょう。現行犯逮捕、準現行犯逮捕は官憲だけでなく私人も可能です(213条)。窃盗罪は4種類すべての逮捕の対象の犯罪です。
逮捕後の司法警察員の手続き
司法警察員は被疑者に対して、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与えなければなりません。そして、留置の必要がないと思料する時は直ちに釈放し、留置の必要があると思料する時は身体の拘束から48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官に送致する手続きをとらなければなりません(203条1項)。
弁解の機会と取調べ
司法警察員は弁解を聞いて留置の必要性を判断しなければなりません。つまり釈放する権限を司法警察員が有しているわけです。もっとも弁解は弁解録取書にまとめられ、裁判で自己に不利な証拠となる可能性があります(322条1項)。弁解の機会に続いて取調が行われることが多いですが、その際には司法警察職員は被疑者に自己の意思に反して供述する必要がないことを告げる必要があります。
被疑者が外国籍だったら
被疑者が外国人の場合、自国の領事機関に通報することを要請するか確認し、領事官との面談や交通ができたり、弁護人の斡旋を依頼できたりすることを説明しなければなりません。領事官が自国民に関する任務遂行のために認められた権利を実現するためです(領事関係に関するウィーン条約36条1項)。もっとも同条約に加盟していない国の国民については必要ないと考えることは可能でしょう。主要国ではイスラエル、台湾(中華民国)、エチオピアなどが非加盟です(平成27年1月1日時点、国際条約集2015年版=有斐閣より)。
微罪処分とは?窃盗の微罪処分率は高い
微罪処分とは、軽微な事件について検察官が司法警察員に対して送致義務を免除するものです。司法警察員は本来、事件を速やかに検察官へ送致しなければなりません(全件送致主義の原則=246条)が、その例外である検察官指定事件(同条但し書き)の一つが微罪処分です。犯罪事実が極めて軽微で、かつ、検察官から装置の手続きの必要がないと予め指定されたものです。これは検察官が有する起訴猶予とする権利を、司法警察員に委ねたとするのが一般的な解釈です。
送検
逮捕され、司法警察員に留置の必要があると判断されたら被疑者は検察官に送致されます。
送検の意味
送検は日常生活ではよく聞く言葉ですが、刑事訴訟法には「送検」という言葉は出てきません。検察官に送致(203条1項後段)と表現されます。これは被疑者の身柄を検察官に送ることではなく、事件そのものを検察官に送ることを指します。つまり書類及び証拠物とともに被疑者の身柄を送致することで、それにより事件が検察官の扱いになることを意味します。
タイムリミット48時間
検察官送致には時間制限があり、被疑者の身柄拘束から48時間以内に書類及び証拠物とともに送致の手続きをしなければなりません(203条1項後段)。手続きをすれば良く、被疑者の身柄が実際に検察に到着するのは身柄拘束から48時間を過ぎていても問題ありません。
検察官送致された時の収容施設
被疑者がどこで収容されるかは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に定められています。逮捕された場合は通常、警察の留置施設に収容されます(同14条2項)。検察官送致を受け勾留される者は拘置所などの刑事施設に収容されますが(同3条3号)、留置施設に収容される場合もあります。
勾留
検察官は送致された被疑者を受け取った時、留置の必要があると考えた場合は、裁判官に被疑者の勾留を請求します。裁判官が勾留決定をすれば、被疑者は勾留されます。
送致を受けた検察官の手続き
検察官は送致された被疑者を受け取った時は、弁解の機会を与え、留置の必要がないと判断すれば直ちに釈放することになります(205条1項前段)。逆に留置の必要があると考えた場合は、受け取った時から24時間以内、かつ、被疑者が身体を拘束されて(原則として逮捕の時)から72時間以内に裁判官に勾留を請求しなければなりません。
裁判官による勾留決定
勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対して被疑事件を告げ、勾留質問を行います(207条1項が準用する61条)。勾留の理由がある場合には速やかに勾留状を発しなければならず、勾留の理由がない時には釈放を命じなければなりません。また、必要があれば事実の取り調べをすることができます。
勾留期間と延長
勾留期間は10日です。勾留請求の日から10日以内に公訴を提起しない場合には直ちに被疑者を釈放しなければなりません。初日は時間にかかわりなく1日として計算されます。また、やむを得ない事由がある時は、10日を超えない範囲で期間の延長が認められます(同条2項)。合計で10日を超えないのであれば、延長の回数に制限はありません。
起訴
起訴は、検察官が裁判所に実体的審理と有罪判決を求める意思表示です。勾留延長される場合を除き、勾留請求の日から10日以内に起訴するか、しないかが決定されます。
検察官による起訴
起訴は検察官が行い、その権限は検察官のみが行使できるものです(247条)。これを起訴独占主義と言います。また、たとえ犯罪の証明が十分であっても、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により起訴しないこともできます(248条)。これを起訴便宜主義と呼びます。つまり起訴するかしないか、検察官が一切の権限を有しているわけです。
起訴された場合の被疑者の勾留
起訴された被疑者は被告人となります。被疑者の段階で勾留されていて被告人になった後も勾留する場合には、検察官が起訴状を提出すると自動的に勾留が継続されます。被告人の拘禁場所は刑事施設ですから、通常は起訴されると拘置所に移送になります。しかし、現実の運用は拘置所の混雑などでスムーズにはいかないようです。その場合はしばらく留置場に勾留されることもあるようです。
被告人になったことによる効果
被疑者が被告人になることで、捜査機関による接見指定はできなくなります。これは接見指定が「公訴の提起前に限り」行えると規定されているためです(39条3項)。もっとも被告人が余罪について起訴前勾留されている時は指定が可能です。
公判
検察官による起訴があると、公判が開かれます。
裁判所の手続き
裁判所は公訴の提起があった時は、遅滞なく起訴状の謄本を被告人に送達しなければなりません(271条1項)。裁判長は公判期日を定め(273条1項)、検察官、弁護人に通知します(同条2項)。
弁護人選任権等の告知
裁判所は公訴の提起があったときは、遅滞なく被告人に弁護人を選任できる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任できない時は弁護人の選任を請求できる旨を知らせなければなりません(272条1項)。弁護人の選任の告知は逮捕時(203条1項)、勾留質問時(207条2項)にもされますが、ここでも行われます。このように何度も告知を義務付けるのは、憲法37条3項で保障された弁護人選任権を実質的に保障する意図であるとともに、刑事事件における被疑者・被告人の権利の保護のために弁護人の果たす役割の大きさを示すものと言えます。
公判手続きは大きく分けて4つ
公判手続きは、冒頭手続き-証拠調べ-弁論-判決という流れになります。冒頭手続は、人定質問(刑事訴訟規則196条)-検察官による起訴状の朗読(291条1項)-裁判長による権利告知(291条4項前段)-被告人及び弁護人が事件について陳述(罪状認否等、291条4項後段)という順番で行われます。裁判長による権利告知とは、終始沈黙し、または個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨、陳述がされた場合、自己に不利益な証拠ともなりうること等を告げます。
窃盗罪では簡裁での審理も多い
窃盗罪は簡裁で公判請求されることが少なくありません。これは選択刑として罰金が定められている罪の訴訟(裁判所法33条1項2号)にあたるためです。簡裁では原則として禁錮以上の刑を科すことができません(同2項)。しかし、窃盗罪は同項の例外規定に含まれていますから、簡裁に起訴された場合3年以下の懲役が科される可能性はあります。
簡裁で起訴なら略式命令の可能性
窃盗罪で簡裁に起訴された場合、検察官が公判手続きの必要がないと思料すれば、略式手続の請求ができます。予め被疑者の同意を得た上で請求し、簡易裁判所が公判手続によらずに書面審理だけで刑罰を言い渡せます(461条以下)。簡裁だけの制度で100万円以下の罰金又は科料を科すことができます。被疑者にとっても罰金刑しかありませんし、早期に事件から解放されるというメリットがあります。平成27年の検察庁終局処理人員を見ると窃盗罪で公判請求したのは2万7336人、略式命令請求したのは7410人です。(平成28年版犯罪白書)。
万引き・窃盗事件における示談交渉のポイント
窃盗容疑で逮捕、勾留された場合であっても、全件が起訴されるわけではありません。嫌疑が不十分だった場合はもちろんですが、嫌疑がはっきりしていても総合的な判断で検察官が起訴しないこともあります(起訴猶予=248条)。起訴猶予となるか否かは、被害者との示談が成立しているかが大きなポイントを占めます。
被害者への謝罪が示談の基本
示談については刑事訴訟法、刑事訴訟規則、犯罪捜査規則等に規定がありません。しかし、司法警察員による微罪処分、検察官による起訴、起訴猶予を決定する場合において示談の成否が重要な役割を果たします。
示談を成立させるためには被害者への謝罪は前提になります。
窃盗罪での示談のポイント
窃盗罪は財産上の損害が生じますから、その部分の賠償をするのは示談を成立させるには必要な条件です。それに加え、精神的な損害に対する慰謝料も支払うことを躊躇すべきではありません。その上で強い反省の念を示すことが被害者の感情を和らげることになります。
身柄拘束からの解放の取り組み
依頼を受けた弁護人としては、身柄を拘束された被疑者・被告人を一刻も早く自由の身にすることを目指します。自由の身になると一口に言っても、一連の手続きの中で様々な方法が考えられます。
検察官に送致されずに釈放
逮捕後、自由の身になる最初のチャンスは検察官への送致がされずに釈放されるパターンです。司法警察員は留置の必要がないと思料すれば直ちに釈放しなければなりません(203条1項)。そして留置の必要性について最高裁は「犯罪の嫌疑のほか、逃亡のおそれ又は罪証隠滅のおそれ等から成るものである」(最判平成8年3月8日)と判示しています。この時点で釈放に向けてすべきことは犯罪の嫌疑が薄いこと、定まった住所や定職があり逃亡のおそれがないこと、罪証隠滅ができないように現場付近に行かないことを約束するなどして、留置の必要性がないことを司法警察員に理解させることでしょう。
検察官送致後、留置の必要性がないと判断され釈放
被疑者が検察官に送致された後、検察官が留置の必要性がないと考えれば直ちに釈放されます(205条1項)。どのような場合に留置の必要性がないと判断されるかは、勾留請求書に刑事訴訟法60条1項各号に定める事由の記載が求められている(刑事訴訟規則147条1項3号)ことから、定まった住所がある(1号)、罪証隠滅ができないように関係者と接触しない、現場に近づかないことが約束されている等(2号)、定職があり、身元を保証する者がいて逃亡のおそれがない(3号)など、同条各号にいずれも該当しない場合が考えられます。それが認められれば検察官としては勾留請求書に60条1項各号の事由が書けないことになります。
裁判官が勾留請求を却下して釈放
検察官から勾留請求が出されても、裁判官が勾留の理由がないと認める時は直ちに被疑者の釈放を命じなければなりません(207条5項)。そのため、勾留の理由がないことを裁判官に働きかけます。ここも60条1項各号に該当しないことを主張することになります。実際には検察官の勾留請求から、裁判官の勾留決定までは時間も少ないことから、同時期に働きかける場合が多いようです。
裁判官の勾留決定に対して準抗告する
裁判官のした勾留決定に対しては準抗告が可能です(429条1項2号)。理由として60条1項各号に該当しないことを主張します。なお、罪証隠滅、逃亡のおそれについては「相当な理由」が必要とされています。
起訴後勾留に対して保釈申請をする
起訴された場合は、保釈を請求します。保釈とは保釈保証金を納付して勾留の執行を停止し、拘束を解く制度です。起訴前勾留にはこの制度は適用されません。
万引き・窃盗事件の弁護活動にかかる費用相場
弁護人が事件を担当することになると、解決のための費用がかかります。示談には金銭が必要になりますし、示談をする弁護士の費用も必要になります。
示談金
示談には金銭が必要になります。窃盗などの財産犯であれば、被害者の損害を金銭によって原状回復させるのと同様の効果が望めます。もちろん、それだけではなく主に慰謝料という形で賠償をすることになります。
生じた損害は示談金で賠償を
事件になったことで何らかの損害が発生した場合(アルバイトに遅刻し時給が少なくなった等)は、その賠償をすべきです。
実費以外にも慰謝料が必要です。被害者の負った不快感、時には恐怖心など精神的損害を金銭で賠償する必要があります。その意味から慰謝料は示談金の一部であると言えます。
弁護士費用
示談をするには弁護士の力が必要です。被疑者の親族が被害者と示談交渉をしようと思っても、被害者は自分の住所など連絡先を知られたくないと考える場合が多いでしょうから交渉のテーブルにつくことさえ困難な状況が予想されます。そうなると弁護士に依頼するのが示談を成立させるには早道と言えそうです。

こちらも読まれています
相談料
弁護士への相談料は、最近は初回無料としていることが多いようです。2回目以降は1回5000円程度が相場と言えます。
接見費用
被疑者・被告人との接見の場合、事務所から勾留場所まで行く必要があります。また、身柄拘束を解くための行動は、司法警察員、検察官、裁判官の手続きに時間制限がある以上、迅速に行う必要があります。そのため費用としても勾留場所との距離にもよりますが1回3万円前後はかかるのが普通です。
着手金
弁護士が事件を担当する場合、依頼人は着手金を支払うことになります。刑事事件では自白している事件であれば事実関係を争うことがありませんが、否認事件では不起訴や無罪判決を取る必要があり、事実関係からして争うことになります。そのため、否認事件は一般的には高くなります。弁護士にもよりますが、通常の自白事件なら20〜30万円程度、否認事件なら30〜50万円程度でしょう。
自白事件の成功報酬
自白事件であっても弁護士の活動によって微罪処分、起訴猶予、略式命令、執行猶予付き判決、保釈許可決定、勾留に対する準抗告が認められるなどで被疑者・被告人にとって利益になることがあります。その場合には成功報酬を支払うことになります。事件や弁護士にもよりますが起訴猶予や微罪処分が10〜30万円程度、それ以外は20万円以下が相場と言えるのではないでしょうか。示談が成功した場合や、求刑より言い渡された刑が軽い場合にも成功報酬は必要となるのが普通です。執行猶予については平成28年6月から始まった刑の一部執行猶予制度も成功報酬が必要と考えた方がいいでしょう。
否認事件の成功報酬
否認事件では無罪判決を得ることが可能です。その場合には事実関係を争い、時間と手間をかけて争いますから、当然、成功報酬は高く設定されます。30〜50万円程度は必要でしょう。もちろん自白事件でも無罪判決の可能性はあります(ウソの自白をした場合等)し、自白事件の方が無罪判決の獲得は難しいですから、少なくとも否認事件での無罪判決と同程度の成功報酬は必要になります。なお、否認事件でも不起訴、執行猶予付き判決などでの成功報酬は必要になると考えるべきでしょう。
実費
弁護士が活動にあたって実際に経費としてかけた分は依頼人に請求されます。接見するための交通費や、通常の通信費などです。
日当
出頭したり、出張したりした際の日当が必要になります。概ね1回で3万円前後でしょう。また着手金を支払わずに、実際にかかった日数、時間によって支払額を決定する「タイムチャージ」という方式で支払う方法もあります。着手金で一律に支払うのではなく、かかった時間だけ支払うというものですが、大きな事件になると日数がかかり着手金方式より多く支払わなければならないということも考えられます。
万引き・窃盗の刑事事件で弁護士に依頼するメリット
刑事事件では弁護士がつくことで様々なメリットがあります。
示談交渉による問題解決
身柄の拘束を解くため、あるいは量刑判断などで示談が成立しているかどうかは大きなポイントになります。
示談で起訴を免れる場合も
刑法、刑事訴訟法、刑事訴訟規則には「示談」という単語はありません。一種の契約と考えれば、刑事関連法規に出てこないのは当然でしょう。そもそも刑事上の責任は個人間の交渉で排除できませんから、当事者の合意で有罪を無罪にすることはできません。あくまでも示談の結果によって訴訟法上の効果の発生や、裁判所の量刑判断に影響が出るだけです。しかし、検察官が起訴するかどうかの判断において示談が成立していれば被害者がもう処罰を望んでおらず、損害の賠償も済んでいると判断しますから、公判請求の必要は無いとして起訴猶予にする可能性はあります。特に窃盗罪は、経済的損害に対する賠償は可能ですから、それがされてしまえば被害者の処罰感情も和らぐ可能性はあります。そう考えると起訴猶予へのハードルは必ずしも高くありません。平成27年の窃盗罪の検察庁の終局処理人員10万8110人中、起訴猶予は3万5796人で、起訴された3万4746人(略式命令請求含む)を上回っています(平成28年版犯罪白書)。
示談で量刑判断も変わる
起訴された場合でも、裁判所は量刑判断においては情状面を考慮しますから、示談の成否は大きく影響します。示談を拒否して厳しい処罰感情を明らかにすれば、厳しい量刑が出やすいでしょう。逆に示談が成立していれば被害者は厳しい処分は望んでいないと判断され、厳しくない量刑となる可能性はあります。
外部への連絡・説明
逮捕され、身柄を拘束されている被疑者は外部との連絡を取る手段を持っていません。そこで弁護士が重要な役割を果たすことになります。
外部連絡は弁護士のみ可能
逮捕されると被疑者は外部と電話やメールなど、一切の連絡手段を使うことができなくなります。家族についても、勾留されるまでは原則として接見できません。そのような状況で被疑者と連絡を取れるのは弁護士だけです。被疑者の状態を家族や会社に性格に伝えることができ、外部との唯一の窓口として機能します。
手続きの見通しなど説明が可能
家族や会社の関係者が突然の逮捕で、どのような手続きが進むのかも分からない状況の中、弁護士は刑事訴訟法、刑事訴訟規則に基づく手続きの流れを熟知していますから、その後のことを予測することができます。身柄の拘束を解くためにどのタイミングで何をすればいいか、家族や会社はどう協力すべきか、適切にアドバイスをして被疑者とその関係者のために力になることができます。
処罰の軽減、回避につながる弁護活動
弁護士は身柄の拘束を早く解くこと、処罰を軽減、回避するための活動を行います。
示談交渉
弁護士が行う活動で最も重要なのが示談交渉でしょう。窃盗罪であれば被害者に謝罪し、損害を賠償することで被害者感情をやわらげ、起訴猶予や略式命令、即決裁判で執行猶予付き判決を受け事件を終結させることで被疑者の期待に応えることができます。仮に起訴されても示談が成立していれば量刑面での減軽や、実刑判決のところが執行猶予付きになることも期待できます。平成27年の窃盗罪での起訴率は42.1%で起訴猶予率は51.0%です。(平成28年版犯罪白書、出典は検察統計年報)。
早期の依頼で解放へ様々な活動が可能
窃盗容疑で逮捕された直後に依頼を受けた場合、弁護士は司法警察員に検察官送致をしないよう働きかけたり、送致されても検察官に勾留請求をしないように働きかけたりすることが期待できます。勾留されても準抗告したり、起訴されても保釈を申請したり、身柄の拘束からの解放に全力を尽くすでしょう。それによって処罰の回避や、自由の身になることなどが期待されます。
窃盗の場合、暴行罪や傷害罪などと比較すると、長く拘束されたりすることは少なくないかもしれません。それでも刑事事件には変わらず、刑事事件として手続きが進んでいきます。その中での弁護士の果たす役割は非常に大きく、できるだけ早く依頼することで、手続きがスムーズになります。逮捕されたら、まず弁護士に相談することが重要です。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

傷害罪で逮捕されたら弁護士に相談、傷害事件の示談交渉のポイントと慰謝料の相場
この記事で分かること 傷害事件で身近な人が逮捕された場合傷害罪と暴行罪、定義の違いは?...
-

「迷惑防止条例」とは?~痴漢などの犯罪に刑罰を与える各地の条例~
この記事で分かること 「迷惑防止条例」とは?東京都の「迷惑防止条例」による痴漢の規定「...
-

性犯罪で最も重い「強制性交等罪」(1)~「強姦罪」から改正~
この記事で分かること 「強姦罪」から「強制性交等罪」へ性犯罪の厳罰化が進む「非親告罪」...
-

この記事で分かること 強盗罪の定義とは?強盗罪は非常に重い刑罰が科せられる強盗が絡む他...
-

盗撮で逮捕されたら弁護士に相談!知るべき10のポイントと慰謝料相場を解説
この記事で分かること まず始めに、盗撮はどんな罪で逮捕されるのか盗撮で逮捕された場合に...
-

この記事で分かること 盗撮とは?事件になる典型的なケース盗撮行為で受ける刑罰公共の場所...
-

この記事で分かること 盗撮で逮捕されるときに適用される法令は2つある軽犯罪法と迷惑防止...
-

この記事で分かること 盗撮の構成要件とはどういう意味?軽犯罪法で規制される盗撮の構成要...
-

この記事で分かること 盗撮に関する刑罰・刑期・懲役についての規定盗撮で逮捕された場合は...