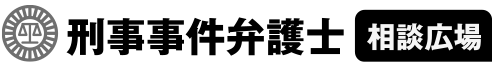被告人質問の流れとは?証人尋問との違いとは?
- 2025年1月20日
- 36,808 view
- 刑事裁判の進み方
- 刑事事件弁護士相談広場

証拠調べから最終手続きへ
刑事裁判のおおまかな流れは、被告人への人定質問から始まり、検察官による起訴状の朗読、裁判官による黙秘権の告知、被告人・弁護人の罪状認否に続いて、証拠調べが始まります。
証拠調べは検察官による冒頭陳述で始まり、証拠調べの請求、弁護人の証拠調べに対する意見陳述を経て、実際の書証や物証の取調べ、証人尋問が行われます。
この間、被告人としては最初に人定質問を受けて氏名、住居地、本籍、職業などを答え、罪状認否で罪を認めるのか、一部否認するのか、全面的に否認するのかを表明した後は、公判が行われている法廷にいるだけで、弁護人がほぼすべてを代弁するため、ほとんど声を発することもありません。
しかし証拠調べの最終段階になると、弁護人、検察官、裁判官が被告人に質問を行う、被告人質問が行われ、この質問に対して任意で答えることができます。
本項では、その被告人質問と、続いて行われる検察官による論告求刑について説明します。
証拠調べは被告人質問で終了
刑事裁判を時間軸で捉えると、中盤のほとんどの時間は証人や鑑定人に対して行われる証人尋問と言っても良いでしょう。その証拠調べの最後になるのは、弁護人、検察官、そして裁判官が被告人本人に対して質問を行う被告人質問です。
人定質問や罪状認否においては、裁判官の問いかけに被告人が答える機会がありましたが、それ以降の証拠調べにおいて、被告人が発言する機会はほとんどありません。その被告人に対して、直接事件に関する質問を行い、被告人自身も法廷で発言できるのが、証拠調べの最後に行われる被告人質問です。
事件に対する質問を受け、被告人自ら直接発言する機会なのですが、被告人質問も、他の証人と同様に自由に話せるわけではなく、あくまでも弁護人や検察官、あるいは裁判官の質問に対して答えるという形式で行われます。
被告人質問は、尋問ではない
被告人質問は、証人尋問とは決定的な違いがあります。
被告人質問は弁護側の弁護人から始められるケースが多いのですが、証人尋問と同じように、弁護側の質問が終われば、続いて検察側からの質問があり、最後に裁判官が必要だと考える場合のみ裁判官自ら質問をします。
これはそれまでに証人に対して行われてきた証拠調べにおける証人尋問と流れは同じなのですが、通常の証人尋問と被告人質問には、被告人には黙秘権がある、という点で大きく異なる性格を持っています。
被告人への質問に関しては、刑事訴訟法第311条に、供述を拒むことができる旨が規定されています。
刑事訴訟法
第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
2 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
3 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
反面、証人への尋問には原則として黙秘権は認められず、弁護人、検察官、あるいは裁判官からの尋ねに対して何らかの答えをしなければならないのです。
現実的な法廷テクニックとしては、言いたくないことは、「記憶にありません」、「わかりません」と答えれば良いのですが、被告人は質問に対して何も答える必要はありません。
しかし沈黙を守るのが得策かどうかは、弁護人と綿密な打ち合わせをすることをお勧めします。証言することで疑いが晴れることもあるのです。
嘘を言っても良いのか?
証人尋問では、証言において嘘をつくと偽証罪として、証人が刑事処分を受けることになります。しかし、法廷において嘘を語るのが良いのか悪いのかは別として、被告人は嘘をついても偽証罪には問われません。
これは、証人の場合は質問を受ける前に、「嘘偽りなく、真実を申し述べることを誓います」という宣誓をしているからで、被告人は被告人質問を受ける前に宣誓は行わないのです。よって、被告人は法廷の証言において嘘をついても、偽証罪の対象にはならないということを意味します。
もともと日本の刑事手続きは、被疑者や被告人は嘘を言う可能性があるという前提で行われているため、罪を少しでも軽くするために、被告人が嘘をつくことを自己防衛のひとつとして認めているきらいがあります。これは日本の司法の特徴で、諸外国では被疑者や被告人の嘘が発覚すると、偽証罪を問われて、さらに罪が重くなります。
また上記の刑事訴訟法第311条にも定められているように、通常は罪状認否の前に裁判官から、「被告人には黙秘権があります。言いたくないことは言わなくても構いません」という黙秘権の告知があり、法廷内でも被告人の黙秘権は有効だということもあります。
とはいえ、黙秘権告知の後に裁判官は、「この法廷で被告人の話したことは、全て証拠となりますので注意してください」と言い、実際に裁判官は法廷内における被告人の言動をすべて審理の材料とし、嘘をついていることが明らかになれば当然裁判官の心証は悪くなり、判決の内容に悪影響を与えることが考えられます。
法廷内での発言に関しては、前もって弁護人に相談し、適切な発言内容となるようにアドバイスを受けることをお勧めします。
検察官による論告求刑で最終手続きの開始
被告人質問を最後に証拠調べは終了し、刑事裁判は公判の佳境となる最終手続きに入ります。最終手続きは、一般的には検察官の論告求刑に始まり、弁護人の最終弁論、被告人の最終陳述と続けられ、結審となる弁論の終結を迎えます。
その後は裁判官が有罪判決とするか無罪判決とするか、もしくはどれくらいの量刑とするかを決める判決手続きが待っています。本項では検察官による、罪を問い、刑を求める最後の機会である論告求刑について説明します。
検察官による最後の追及
被告人質問が終わると、次は検察官による論告求刑が行われます。検察官は改めて公判で明らかになった事実も含めて、再度事件のあらましと被告人の犯した罪をまとめて訴えます。
ただしこれは、一般的には起訴した時点とさして変わらず、あくまでも警察や検察という捜査機関の目線で語る事件のまとめとなりますので、これだけを聞くと、罪の内容に関わらず、被告人が罪を犯した人と断定しているように聞こえます。
そして検察官は最後に、「被告人には、懲役○○年を求刑します」と、被告人に下されるべき量刑を裁判官に対して求刑します。
求刑の根拠は刑法と判例による
検察官が行う求刑の内容は、基本的には刑法に基づいています。刑法とは犯罪の種類や、その罪を犯した場合の量刑が定められているものですが、犯罪ごとに定められた量刑には、たいていの場合は幅が持たされています。
例えば窃盗罪の場合は、その量刑は「10年以下の懲役、若しくは50万円以下の罰金」とかなり幅の大きいものになっています。
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、コンビニエンスストアで108円の菓子を万引きしても適用される一方、被害総額数百万円になるような泥棒も同じ窃盗罪になります。
検察官は被告人の状況や犯罪の計画性、あるいは初犯か再犯かといった事件の特徴を考慮しつつ、過去の判例を当てはめ、もっとも妥当だと思われる量刑で求刑を行います。

こちらも読まれています
被告人が裁判の終盤にできること
刑事事件で起訴された被告人は、有利な判決を得たり、状況を好転させたりするようなことは、自身ではできません。
保釈が認められて社会生活に戻っているならば、弁護人と共に、裁判官の心証を良くするための活動を行うことができますが、勾留が続けられて身柄が拘束されたままの場合は、弁護人にすべてを託すだけと言っても良いかもしれません。
但し、裁判の終盤において、被告人質問や最終陳述など、最後のチャンスとして裁判官の心証を良くする機会が残っています。
裁判官の心証を動かす発言を
刑事裁判は、検察側と弁護側の争いで、どちらが勝つか論争を行う場であると思われがちですが、ひとつしかない犯罪事実に対し、双方の視点から見た見解を裁判官に示すだけの場だと言っても差し支えないでしょう。
検察側を言い負かすのではなく、裁判官の心証を動かすことができれば、最終的に判決を下す裁判官は、情状酌量を行う可能性もありますし、早期の社会生活への復帰を心から願うこともあるのです。
そのため、被告人にとって数少ない発言の機会である被告人質問や最終陳述では、事実を述べるのはもちろん、裁判官の心を動かすような発言が求められます。
しかし自分だけでは何が裁判官の心証を良くするのかの判断は難しいため、多くの経験を持ち判例も熟知している弁護士と十分に相談し、今後の自分の人生を左右する被告人質問、そして最終陳述に臨むべきでしょう。
有能な弁護士は、弁護人が行う最終弁論でも、大きな力になってくれるはずです。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

執行猶予中の生活とは?就職への影響や再犯するとどうなるか解説!
この記事で分かること 執行猶予中の生活は?どんな変化がある?執行猶予中に就職はできる?...
-

起訴されてから裁判までどのくらい?たいていの場合は起訴されて約2カ月後
この記事で分かること 逮捕から裁判までの流れ起訴から裁判までは約2カ月裁判まで2カ月か...
-

この記事で分かること 日本の裁判所刑事裁判の初公判~簡易裁判所のケース~刑事裁判の初公...
-

この記事で分かること 刑事裁判の最初の手続き冒頭手続きにおける人定質問とは?人定質問に...
-

この記事で分かること 黙秘権の告知~発言にはルールがある~被告人が行う罪状認否とは?淡...