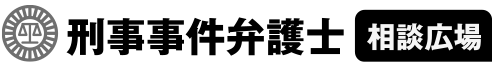黙秘権とは?弁護士無しでは黙秘を貫くことは難しい?
- 2025年1月20日
- 20,683 view
- もし逮捕されてしまったら
- 刑事事件弁護士相談広場
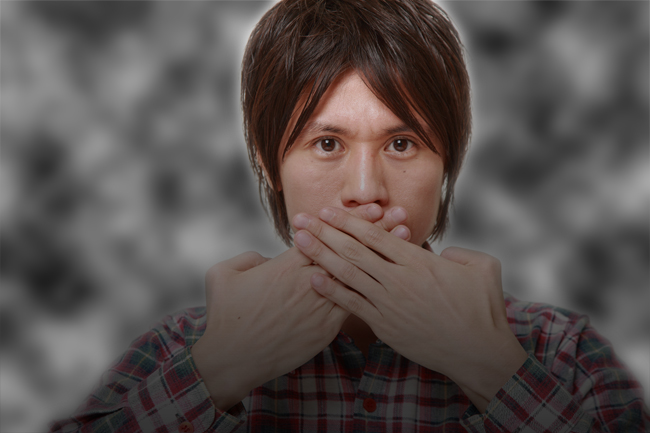
黙秘権とは?
「黙秘権」とは、捜査段階や取調べ、また裁判などの刑事事件の手続きにおいて、自己の意思に反して供述をすることを強要されないという権利です。一般的には自分にとって不利益となる証言はしなくてよいと解されていますが、利益になるか不利益になるかは関係なく、終始沈黙を貫き通してもよい権利とされています。
刑事事件の手続きが規定されている刑事訴訟法には、取調べや裁判に関する定めが多くありますが、取調べについては第198条に次のように記載されています。
刑事訴訟法
第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
○2 前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
(以上、抜粋)
この刑事訴訟法第198条の第1項は取調べに関する定めですが、第2項には、自己の意思に反して供述は行わなくてよいとする、いわゆる黙秘権の告知が取り決められているのです。
そして裁判においては同条第311条に、終始沈黙し供述を拒むことができる旨が規定されています。
刑事訴訟法
第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。
○2 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。
○3 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。
以上のように、刑事事件の被疑者や被告人が刑事手続きの中で、自分が言いたくないことは言わなくてもよいとする決まりがあり、それは黙秘権と呼ばれ、法律にきちんと規定され保障される権利なのです。
憲法にも定められている黙秘権
この黙秘権は刑事訴訟法だけではなく、憲法にもその権利の根拠とされる条文があるのです。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
この憲法の条文が黙秘権の保障を明言するものなのかどうかは、法律の専門家によっても解釈が分かれるところですが、この条文が存在しているのは、戦前の大日本帝国時代における官憲の刑事手続きの中で、供述を強要することが存在したことを暗に示しているとみられます。
歴史的な背景をふまえて、現在の日本国憲法が謳う個人の尊重、幸福追求権に反する行いとして、供述の強要は憲法において否定されているのです。このように黙秘権は、たとえ罪を犯した被疑者や被告人という立場であっても、憲法や刑事訴訟法などで認められている警察や検察の捜査に対する正当な対抗策なのです。
そもそも取調べに応じる義務はあるのか?
黙秘権があって、取調べで何も喋らなくてもよい権利があるのならば、そもそも取調べに応じる必要がないのではないか、という疑問が湧いてきます。憲法にも刑事訴訟法にも、自身の意思に反する供述をしなくてもよいと定められているのですから、逮捕後に長期間の勾留をしてまで被疑者を取調べる意味がないようにも思われます。
しかし、これも法律で定められている条文の解釈による取調べ受忍義務というものがあるのです。上記の刑事訴訟法第198条第1項の後半には、「但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」という文言があります。
逮捕または勾留されている場合を除いては、いつでも退去する、要するに取調べに応じなくてもよいとするものですが、これを反対解釈して、逮捕または勾留されている場合は、取調べに応じなくてはならない、と捜査当局は解釈しています。
この場合、供述を拒否し続けると不当な捜査当局による拘束が長期化しかねないので、法律家の間ではこの解釈は問題であると指摘しています。
黙秘権の行使は印象を悪くする場合も
刑事事件の被疑者や被告人には黙秘権があり、自分の意思に反して供述をする必要がないことはこれまで説明しました。
しかし事件の捜査を行う側の警察や検察は、「都合が悪いことがあるから黙っている」「事件を起こしたことをまったく反省していない」という印象を持ってしまうことは、理解しておく必要があるでしょう。
警察や検察からすれば、事件捜査の妨げをされるわけですから、当然の流れとも言えます。
黙秘権がなぜ大切なのか
黙秘権とは、刑事事件の取調べや裁判において何も話さなくてよい、という権利です。
そして黙秘を保ってよいのは、「自分にとって都合の悪いこと」だけではなく、話したくないことはすべて、なのです。逆に言うと、「自分にとって有利になること」も話さないでよい権利なのです。
被疑者や被告人に有利なことであれば、包み隠さず話せばよいのではないかと考えられるのですが、すべての人が自分の思いを上手く伝えられるわけではありません。口下手で人前では緊張して上手く話せない人もたくさんいます。
刑事事件の手続きにおいて、被疑者や被告人が絶対に供述や証言をしなければならないという規定があった場合には、うまく話せない人が不利な立場になり、上手に自分の立場を説明できる人が有利になってしまうこともあります。
また上手に説明ができる人であっても、刑事事件の手続きにおいては、刑法や刑事訴訟法をはじめとするさまざまな法知識がないと、警察や検察といった法律のプロによる尋問によって、負わなくてもよい罪を負わされるように言いくるめられてしまうおそれもあるのです。
被疑者や被告人が、その人の個性や法律的な知識不足により不利益を被らないために存在するのが黙秘権であるとも言えます。そして、被疑者や被告人へ適正なアドバイスをし、代弁してくれるのが弁護士であり、裁判においては弁護人として活躍してくれるのです。
判例は黙秘権に否定的?
以上のように、刑事事件の手続きにおいて被疑者や被告人を守り、法令にも規定されている黙秘権ですが、判例では権利の行使に関して否定的なものがあるのも事実です。
例えば、刑事訴訟法には捜査員が取調べを行う前には黙秘権の告知が必要であると規定されていますが、最高裁の判例では告知がなくとも手続き違反にはならないとされています。そして自分の名前を黙秘できるかどうかが争われた裁判においては、黙秘権が行使できるのは、刑事上の責任を問われるおそれのある事項に限られるとして、氏名には黙秘権が及ばないとの判断が下されています。
これらの判例は黙秘権の行使を制限するものであるという批判がありますが、取調べなどにおいて何をどこまで話すか、などの判断は自分だけで行わず、弁護士と入念に打ち合わせた方がよいでしょう。
刑事事件手続きにおける黙秘権の実状
実際の刑事手続きにおいて黙秘権がどの程度通用するかというと、よほど強い意志をもった人でなければ、黙秘を貫くことは難しいとされています。
その理由は、警察や検察には長年の捜査や取調べを続けてきて蓄積されたノウハウがあり、黙秘権を行使しようとする被疑者の供述を引き出すためのテクニックをいろいろと身に着けているからです。
取調べのプロに対抗するのは難しい
よくあるパターンとして、警察や検察は、「黙っているということは、言うと不利になることがある」と、容疑通りの行為をしているから黙っていると断定する態度を取り、被疑者の自白を迫ることがあります。こうした考え方をベースに、怒鳴りつける者、猫なで声で懐柔を図る者、あるいは無言でジッと被疑者を睨み続ける者など、取調べをする刑事や検事により、さまざまな手法があるようです。
取調べのプロである警察や検察を相手に、黙秘を貫くことは並大抵なことではありません。冤罪が明らかになった刑事事件でも、捜査段階で事実とは違う自白をしてしまったケースがよくありますが、これは必ずしも冤罪の被害者となってしまった人の意思が弱いわけではありません。
鉄のような意志を持った人でなければ、実際の取調べ現場において警察や検事の追及に口を開くことなく黙秘の意志を貫くこと自体が難しいということです。
黙秘権を行使したい時は、必ず弁護士のアドバイスを
黙秘権がまったく無意味なのだと考えることもできますが、うまく利用すれば被疑者にとってとても有用な権利になります。黙秘権を行使するという事は、警察や検察側に有利は供述調書を作らせないということで、これは自白以外で有罪の立証が困難な事件の場合、不起訴に持ち込むための非常に有効な手段になります。
逆に言えば、本人が黙っていても有罪を証明する物的証拠などが多くある場合には、下手に黙秘権を行使すると心証が悪くなるだけで、量刑が重くなってしまうことも考えられます。とはいえ、刑事事件に巻き込まれた場合、警察の捜査官や検察の検事といった人たちは刑事手続きのプロである一方で、逮捕された被疑者だけが刑事手続きの素人なのです。
そのため、警察の捜査官に言われるがまま、事実以上の罪を被らないように、逮捕された直後に「弁護士と話すまで、何も喋りません」というのは大変有効な手段です。被疑者の身柄が拘束された場合、刑事事件が得意な弁護士を知っているのがベストですが、そうでなくとも当番弁護士は誰でも呼ぶことができます。
冤罪である場合はもちろん何も認めないことが大切ですが、逮捕容疑通りの罪を犯している場合でも、まずは弁護士のアドバイスを受けてから取調べに望むべきです。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

この記事で分かること 取調室とはどんなところ?捜査官はあの手この手で取調べを行う身に覚...
-

盗撮事件が起訴猶予となる可能性はある?弁護士に依頼することが重要!
この記事で分かること 盗撮事件では起訴猶予に持ち込むことが重要盗撮事件は起訴猶予獲得の...
-

この記事で分かること 「盗撮で逮捕=有罪」ではない盗撮など軽微な事件は不起訴処分を狙え...
-

この記事で分かること 暴行罪における初犯と前科者の違い暴行罪について暴行罪はどんな場合...
-

この記事で分かること 盗撮で捕まった場合はまず弁護士に連絡!盗撮事件を弁護士に相談する...
-

この記事で分かること 状況別・逮捕時の相談先~まずは落ち着いて弁護士に連絡を逮捕された...
-

この記事で分かること 違法薬物を取り締まる「薬物犯罪」の種類覚せい剤取締法大麻取締法麻...
-

この記事で分かること 盗撮冤罪はなぜ起こる?盗撮冤罪の事例盗撮冤罪で逮捕された後の流れ...
-

公務員が逮捕されるとクビになる?公務員逮捕の実例と生活への影響
この記事で分かること 公務員が逮捕されると仕事を辞めさせられる?禁固以上の刑が下される...
-

不同意わいせつ罪とは?構成要件、犯罪となる行為と強制わいせつ罪との違い
この記事で分かること 不同意わいせつ罪とは不同意わいせつ罪の罰則不同意わいせつ罪の公訴...