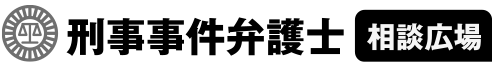逮捕とは?逮捕の定義と目的について解説
- 2025年1月20日
- 43,146 view
- 刑事事件の基礎知識
- 刑事事件弁護士相談広場
この記事で分かること

「逮捕」の定義は?
刑事事件では、たいていの場合は事件が発生した後に警察が捜査し、犯人と思しき者を「逮捕」します。一般的には犯人を「逮捕」することで事件は解決したというイメージを持たれることが覆いのですが、刑事事件の手続きにおいて「逮捕」はスタートであり、決して終わりではありません。
本項では、その「逮捕」について詳しく説明していきます。まず、これもあまり知られていませんが、「逮捕」は憲法第33で規定されているものです。
憲法
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
憲法は国民の権利を守るものですから、条文の上では「逮捕」されない旨を定めているものですが、この文章を読み解くと「司法官憲が発する、犯罪を明示した令状により逮捕される」と解釈できます。
司法官憲とは司法に関する公務員を示しますが、憲法の上では裁判官のことを指します。裁判所の裁判官が令状(逮捕状)を発行すれば、その令状に記載されている罪を犯したと疑われる者は「逮捕」される、ということなのです。
この場合、現行犯で「逮捕」される場合には令状が必要とされていません。
司法上の「逮捕」の原則
対人的な強制処分である「逮捕」およびその後の「勾留」は、司法のうえで以下に示すいくつかの原則に則って行われなければなりません。
- 事件単位の原則
「逮捕」も「勾留」も、被疑事実ごとに行われなければならず、逮捕状の発布は犯罪の事実を元に事件単位で行われなければならないという原則です。
- 一罪一逮捕一勾留の原則
同一の事件について複数の「逮捕」や「勾留」は原則的に認められず、ひとつの犯罪事実に対する「逮捕」は1回に限られるとするものです。
ただし、釈放後にまた犯した罪が常習一罪の一部となる場合には、例外が認められるとされます。
- 逮捕・拘留の一回性の原則
逮捕と勾留は厳密に期間が定められているものであり、同一事件での再逮捕や再勾留は禁止されています。
しかし新証拠の発見、逃亡や証拠隠滅のおそれの出現など、身柄を拘束することの必要性がある場合には例外が認められます。
- 逮捕前置主義
被疑者の勾留を請求するためには、同一の事件事実につき被疑者が既に「逮捕」されていることを必要とするものです。
以上のような原則は一般人には理解し辛いものであり、万が一刑事事件の被疑者として逮捕されてしまった場合には、その手続きに違法性がないか、弁護士に相談することをお勧めします。
「逮捕」=「有罪」ではない!
一般的に「逮捕」と聞いてイメージするのは、罪を犯した者を警察が捕まえる、ということです。それは間違いではありませんが、「逮捕」された者はまだ犯罪者とは確定しておらず、司法の手続きが始まったにすぎません。
警察などの捜査機関が「逮捕」する者は、罪を犯したと疑われる者を意味する「被疑者」と呼ばれ、「逮捕」されたから有罪であるという考え方は誤りなのです。「誤認逮捕」という言葉がよく聞かれますが、必ずしも犯罪者だけが「逮捕」されるとは限らず、司法の考え方からすれば犯罪者という呼び名は、裁判で有罪判決が確定した時に初めて与えられます。
司法のうえでは、「逮捕」された者は推定無罪の「被疑者」であり、起訴された後には「被告人」に呼ばれます。「逮捕」というのは、刑事手続きのひとつに過ぎず、罪を犯したからといって必ず「逮捕」しなければならないという規則もありません。
もし家族や友人・知人が警察に「逮捕」されてしまったとしても、その人をすぐに犯罪者扱いするのではなく、何が罪に問われているのか、逮捕状は正当なものであるか、手続きに違法性はないかなど、弁護士などの専門家の力を借りながら明らかにしていくべきだと考えられます。
「逮捕」の目的は?
警察などの捜査機関は、どうして被疑者を「逮捕」するのでしょうか。
刑事事件を起こした犯人を確保し、罪を与えることが目的であるということは容易に想像できるのですが、後述するように身体拘束を伴わない「逮捕」もあり、刑事手続きのひとつではあっても、罪を犯したものは必ず「逮捕」しなければならないという規則はありません。
被疑者の身柄を拘束しないで犯罪の捜査をする「在宅捜査」や、「逮捕」せずに事件を検察に送致する「書類送検」といった手続きもあるのです。
それでは、「逮捕」が行われるのはどういう状況か、そして「逮捕」の目的について確認してみましょう。
逃亡と証拠隠滅の可能性があると「逮捕」される
刑事事件の被疑者を「逮捕」する時には、「現行犯逮捕」などの場合を除き、裁判所が発布する令状(逮捕状)が必要です。その際、警察は逮捕状を申請する理由として、「被疑者には逃亡の恐れがある」、「被疑者が証拠隠滅する可能性がある」ということを挙げます。
裁判所はほとんどの場合、警察の言い分を認めて逮捕状を発布するのです。この手続きは、刑事訴訟法第199条の第1項に定められている規定によるものです。
刑事訴訟法
第百九十九条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
要するに、警察が犯人だと考える相当な理由があり、それを裁判官が正当だと認めれば逮捕状は発布されるのですが、その理由は被疑者に逃亡の恐れがあって、証拠隠滅の可能性の可能性があるから、ということなのです。
しかし、詐欺や共犯者のいる組織的な犯罪の容疑ならともかく、条文の規定にもあるように比較的軽微な罰金や科料という刑罰で済むような犯罪で、「逮捕」という自由を奪われる強制処分を受ける必要はないのです。
万が一刑事事件の被疑者として「逮捕」されるような事態に陥ってしまった時には、自分が逮捕される容疑を考えた上で、いち早く弁護士を手配してその後の対応を任せた方が良いでしょう。
「逮捕」されない特権がある
国会議員は「逮捕」されないという、不逮捕特権があると聞いたことがある方がいるかもしれません。これはただ国会議員だから「逮捕」を免れるということではなく、きっちとした理由があるからです。
まず、不逮捕特権は憲法第50条に規定されています。
憲法
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
不逮捕特権は、時の権力者が議会における反勢力の議員を不当に「逮捕」し、権力の濫用を行ったという過去の反省を踏まえて制定され、現在においては国会議員の活動を保障するものでもあるのです。
この特権は国会の会期中に限られるものですが、会期前に「逮捕」されていたとしても、議会の要請があれば釈放されるという定めもあります。しかし実際に犯行を行った際の「現行犯逮捕」にこの特権が及ぶことはなく、もし国会銀が人を殴ったとしたら、国会の会期中だからといって「逮捕」されないということはありません。
そして国会議員に加え、天皇及び摂政など、国務大臣、外交官、在日米軍の構成員など、国家の元首にも、さまざま制度により条件が定められた不逮捕特権が与えられています。
「逮捕」されるとできなくなることは?
「逮捕」されるということは、警察官に手錠をかけられるというイメージだけがありますが、必ずしも手錠をかけられ警察署に連行されるというだけではなく、それ以外にもさまざまな制限が科せられます。
国民は憲法によって自由が保障されていますが、罪を犯した者に自由を与えたままにしておくと、逃げて行方をくらましたり、犯罪の証拠を隠滅したりしてしまう恐れがあるため、条件付きで罪を犯した可能性のある者の身柄を、警察などの捜査機関が拘束する行為が「逮捕」なのです。
「逮捕」によって制限される自由
刑事事件の被疑者が「逮捕」によって制限される主な自由は、「移動・行動の自由」と「外部交通の自由」です。「移動・行動の自由」の制限とは、被疑者が自分の意志で行動できる自由が制限されるというものです。
具体的には、被疑者は「逮捕」されると留置場などの刑事施設に入れられ、取調べなどで留置場の外を歩くときには、手錠と腰縄を付けられて、警察官などの監視の下で行動を指示されるというものです。もちろん一度「逮捕」されてしまったら、釈放されるまでは勝手に施設の外に出ることはできません。
「外部交通の自由」の制限とは、被疑者自身が電話をかけたり、手紙を出したりする自由が著しく制限されるということを示します。「逮捕」されると、その直後に携帯電話やスマートフォン、タブレットなどは押収されてしまいますので、被疑者自身が直接外部に電話をしたり、メールを出したりすることができなくなります。
ハガキや便箋・封筒を買えば、留置場から手紙などを出すことは可能ですが、逮捕直後はかなり難しいでしょう。勾留が決まり手紙を出す機会があったとしても、書かれた内容はすべて検閲されてしまいますので、私信が他人の目に晒されるという状況下で「逮捕」がいかに異常な状況なのかを実感することになります。
さらに検察が裁判所に許可を取り、接見禁止処分を言い渡された被疑者は、手紙すら書くことはできません。接見禁止とは、弁護士以外の人間と接見と呼ばれる面会が禁止されると共に、手紙を出すこともできなくなるうえ、被疑者宛ての手紙も接見禁止が解除されるまで手渡されないのです。
以上のように、被疑者の「移動・行動の自由」と「外部交通の自由」が極端に制限されることが「逮捕」なのです。
「逮捕」されたら、唯一の頼りは弁護士
もし刑事事件の被疑者として「逮捕」されてしまったら、上記のように移動や連絡の自由が制限されてしまい、これから何をされるのか、何をすれば良いのか分からない人がほとんどでしょう。そこで、頼りになるのが弁護士という存在です。
原則として、警察官は「逮捕」時に黙秘権の説明と弁護士を呼ぶことができる旨を伝えなければなりません。おそらく「逮捕」直後は気が動転して、被疑者自身も覚えていないかもしれませんが、何も言わないで被疑者の身柄を拘束することは違法逮捕となります。
弁護士を呼ぶタイミングは早ければ早いほどよく、知り合いに弁護士がいない場合でも当番弁護士制度を利用して、なるべく早くコンタクトを取るようにしましょう。弁護士はいつでも被疑者と接見することが可能で、これから行われる刑事手続きについて説明してくれ、どういう対応方法が良いのかを教えてくれるでしょう。
また家族や友人・知人が逮捕されてしまった場合にも、すぐに弁護士に連絡を取って、被疑者はひとりではないことを伝えてあげましょう。この場合は私選弁護士となりますが、当番弁護士や国選弁護士よりも精力的に動いてくれる可能性が高くなります。
「逮捕」されてしまった被疑者と連絡を取るのは、最初のうちは弁護士を介するしかありませんので、こちらもなるべく早くコンタクトを取るべきです。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

刑事裁判見に行く方法~被告人の家族や友人、知人ができること~
この記事で分かること 刑事裁判を傍聴するための基礎知識刑事裁判の被告人の家族としてでき...
-

この記事で分かること 保釈とは保釈が認められるためには?保釈の流れ保釈金の金額相場保釈...
-

この記事で分かること 刑事事件の被疑者が逮捕されないケースがある在宅捜査書類送検その他...
-

この記事で分かること 逮捕状とは何か逮捕までの流れ逮捕状がなくてもできる例外的な逮捕逮...
-

サイコパス(精神病質者)の特徴とは?犯罪者とは限らない意外に身近な障害
この記事で分かること サイコパス(精神病質者)とは?サイコパスの特徴犯罪者にサイコパス...
-

この記事で分かること 逮捕権とは?「逮捕権」は正しく行使されなくてはならない!一般人に...
-

この記事で分かること 手錠を掛けるだけが逮捕ではない!?逮捕後に手錠を掛けられるのは逃...
-

留置所の差し入れで嬉しいものとは?差し入れ可能な物はどんなもの?
この記事で分かること 留置場とは?どんなところ?通常逮捕の場合、最低限の持ち物は許され...
-

この記事で分かること 「労役場留置」とは「労役場留置」という刑罰はない?罰金刑や科料に...
-

この記事で分かること 労役場における「労役場留置」とは?「労役場留置」日当の計算方法は...