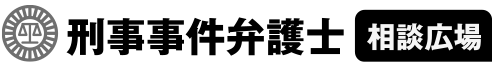殺人罪の刑期はどのくらい?懲役何年の決まり方
- 2025年1月20日
- 162,675 view
- 犯罪の種類
- 刑事事件弁護士相談広場

人の生命を奪ってしまえば、重い刑罰が科せられるということは簡単に思い付きます。しかし「殺人罪」の成立は、故意か過失か、計画性の有無など、複数の要件が突き詰められて判断されます。刑罰も5年以上の懲役から死刑までと、大きな幅が設けられています。
人を殺せば罰せられる~「殺人罪」の定義
日本の刑法や特別刑法などには、刑事事件となる数多くの犯罪行為が規定されていますが、その中でも人が犯す行為として想像しやすく、重い罪が科されると考えられるものは「殺人罪」です。
「殺人罪」は日本だけでなく、いつの時代でも、世界中のほとんどの国においても重罪とされているものです。
「殺人罪」とは、文字通り人の生命を奪う、すなわち人を殺す行為で、殺人を法律で禁じておかないと、不平や不満を持っただけで、人が人を殺してしまっても問題がないという社会になってしまいます。
社会を安定的に維持するためには法律が必要で、社会の存続自体を脅かしかねない仲間の生命を奪うことは、法律の中でも最も重要な禁忌行為にするのは当然と言えます。
「殺人罪」というのは、そういう意味で究極の犯罪行為なのです。
刑法での「殺人」の規定は幅が広い
日本の刑法の規定による「殺人」の規定は、第26章に「殺人の罪」として、ある程度の幅を持って定められています。
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百条 削除
(予備)
第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する
ここには、人を殺しただけではなく、その準備を行った者、自殺に関与する行為を行った者に対する規定もされているのです。
そのため、以下に説明するように「殺人罪」で逮捕・起訴される人の数は、「殺人」の被害者として命を落とした人の数よりも、かなり多くなっています。
「殺人」は年々減少している?
法務省がまとめた「平成29年版犯罪白書」によると、殺人の認知件数は,平成16年から減少傾向にあるとされ、平成28年は戦後最少の895件となっています。
そして「殺人」の検挙率は100.7%で、高い検挙率を保っていると発表されています。
この認知件数というのは、警察が犯罪を認知した件数という意味で、当然ながら実際に犯罪が起こった犯罪件数ではなく、検挙率が100%を超えているのは、前年に認知した犯罪を当該年に検挙したものがあるためです。
そして、刑法に定められている「殺人の罪」には、自殺関与や同意殺人、未遂および予備が含まれている反面、強盗殺人罪や強盗致死罪などによる被害者の数は含まれていませんので、広い意味での人を殺した事件の数として捉えるには不十分とも言えるでしょう。
一方、警察庁が発表した「平成28年の犯罪情勢」によると、「殺人」による被害(死亡)者数は総数362人(男性165人、女性197人)となっています。
こちらも減少傾向にありますが、10年前には男性の方が被害(死亡)者数は多かったのですが、その状況は逆転し女性の割合が増えてきているのが特徴的です。

こちらも読まれています
「死刑」以外の刑罰もある「殺人罪」
「殺人罪」の刑罰には、意外と幅があります。
刑法によって定められた刑罰は「死刑、又は無期、若しくは5年以上の懲役」です。
人を殺したのだから「死刑」という簡単なイメージで判決が下されることはなく、上記のように、刑法が定める「殺人の罪」に幅があることも一因となり、「殺人罪」が成立してもその刑罰はさまざまな結果として表れてきます。
つまり、裁判によって「殺人罪」として有罪が確定した場合、被告人に科せられる刑罰は、最低でも5年以上の「有期懲役」か「無期懲役」、そして最も重い場合には「死刑」となるのですが、「死刑」と懲役5年では大きな差があり、「殺人罪」には量刑にかなり幅があるのです。
「殺人罪」と「死刑」の関係性は?
長らく日本の刑事裁判においては、「永山基準」と呼ばれる「死刑」が求刑される基準がありました。
1968年に4人を射殺した永山則夫元死刑囚の裁判において、83年に最高裁判所が死刑適用の基準として挙げたものですが、基準の中に複数の命を奪った場合に「死刑」の判決が下されるべきというものがあったのです。
「死刑」になるのは2人以上殺した場合で、殺したのが1人だと最高でも無期懲役といった不文律が存在したとも言われています。
しかし、裁判員制度が導入された現在、事件の内容が非常に悪質なものであれば、被害者が1人であっても「死刑」が求刑され、そのまま「死刑」の判決が下されるケースも出てきています。
犯罪に対する厳罰化の流れということもありますが、果たして「死刑」が人を殺した罪を償うのに適しているのかどうか、という議論もあります。
「死刑」制度廃止の議論と合わせて、今後も世間の注目を集める点となるでしょう。
複雑な事情が絡む「殺人罪」
殺人事件は単純ではありません。
行きずりの殺人や無差別殺人を除き、知っている人の生命を奪う行為には、それなりに大きな理由があるでしょうし、殺される側にも犯人との関係性など、さまざまな理由や状況があると考えられます。
特に家族や親族が被害者あるいは加害者となってしまう殺人事件においては、感情的なもつれも相まって、非常に複雑な状況となってしまいます。
現在では刑法から削除されていますが、かつては日本では、自己または配偶者の直系尊属を殺した者について、刑法第199条に定められる通常の「殺人罪」とは別に、第200条に「尊属殺人罪」が設けられていました。
通常の「殺人罪」とは違い、「尊属殺人罪」は無期懲役、または死刑のみと刑罰が定められており、刑罰の下限は高く、より重いものになっていたのです。
こうした過度の厳罰化の規定は、1973年に日本国憲法下で違憲であると違憲判決の確定判決が下され、それ以降は死文化され適用されなくなり、1995年の改正刑法で正式に削除されました。
この違憲判決のきっかけとなったのは、性的虐待を繰り返した実父を娘が殺したという、考えるだけで気の重くなるものでした。
こうした事件の加害者を厳罰に処することは問題があります。
つまり刑事事件の審理には被害者と加害者の事情を鑑み、ある程度の情状酌量が必要だということで、現在の「殺人罪」には死刑から懲役5年以上という幅が持たされているとも言えます。
これは「殺人罪」に限ったことではなく、ほとんどの犯罪は刑罰に幅が持たされています。
「殺人罪」が成立する条件は?
人が人を殺してしまったら、すべてが「殺人罪」に問われるとは限りません。
「殺人罪」がどのような場合に成立するのかは、被害者と加害者の関係性はもちろん、複数の要件から判断されます。
ただ人が死ぬ行為を行っただけで「殺人罪」となるわけではなく、殺意があったかどうか、または計画性があったのかどうかも判断される基準となるのです。
「殺人罪」には、殺意があったことが必要
交通事故のように、加害者の過失で結果的に相手を死なせてしまった場合は、「殺人罪」ではなく刑法第210条に定められる「過失致死罪」、あるいは第211条の「業務上過失致死傷罪」になります。
(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
「殺人罪」が成立するには、事件が起こった時に加害者が被害者に対して殺意を抱いていたかどうかが重要となります。
しかし殺意とは加害者の心の中だけに存在するもので、取調べや裁判で「殺すつもりはありませんでした」と主張して、加害者が「殺人罪」を否認することもよくあります。
とはいえ、加害者が刃物を使って刺したり、紐やロープで首を強く絞めたり、崖の上から突き落としたりして、その行為によって明らかに相手は死ぬという行為で犯行を行った場合には、その行為そのものに殺意があったと見なされてしまいます。
「殺人罪」には、計画性が必要だという見方
加えて、殺意の有無と共に「殺人罪」となるかどうか、または刑罰の重さを決める大きな要素になるのが、計画性の有無です。
事件を起こしてしまった際、加害者があらかじめ被害者を殺す準備をしていたか否かという点です。
被害者に会う前に加害者が刃物やロープなど、人を殺すための道具を用意していたとすれば、最初から相手を殺害する考えがあったと見られます。
このような場合、殺意はなかったと主張してもあまり説得力はありません。
さらに計画的な殺人は、感情にまかせて衝動的に犯す殺人より悪質だと判断されます。
しかし事情によっては、用意した道具は、自分の身を守るために準備していたのであり、相手を実際に殺す気はなかった、というケースも当然考えられるでしょう。
「殺人罪」が成立するのは難しい
明らかな殺意を持って、計画的に人を殺したという証拠が明確であれば、「殺人罪」が成立してもやむを得ないかもしれません。
しかし、上記のような殺意や計画性は、簡単に証明できるものではありません。
必ずしも「殺人罪」で処罰される訳ではない
例えば、人を殺してしまった場合でも、傷つける意思しかなかった時には刑法第205条の「傷害致死罪」にとどまります。
また、意思があって殺したとしても、自分の命を守るためにやむなく人を殺した場合には、刑法第36条1項に定められている「正当防衛」が適用され、犯罪にはなりません。
そして夢遊状態にあり、本人が自分の行為に気がついてない時にも、刑法上の罪に問えないことになっています。
とは言え、被告人の主張は裁判官、あるいは裁判員によって判断され、有能な弁護士のアドバイスがなければ、殺人の罪で起訴された場合、なかなか裁判という場で反論したり、量刑の軽減を得たりということは難しいでしょう。
もし万が一、家族や親族、友人や知人が殺人事件の犯人として逮捕されてしまい、助けたいと考えるならば、優秀な弁護士に依頼し、弁護人となって活動してもらうことが、最善の方法だと言えるでしょう。
逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!
ご自身・ご家族やご友人が
逮捕されてしまったら、今すぐ弁護士にご相談を!
このようなことでお困りですか?
- 身に覚えがないのに警察に呼ばれてしまった
- 逮捕されたことで解雇されたり、退学になるのは困る
- 今すぐ釈放してほしい
- 被害者の方と早期に示談したい
- 事件の前科や逮捕歴を残したくない
- なんとかして不起訴の可能性を少しでも上げたい
この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
都道府県から弁護士を探す
弁護士に相談することに不安が残る方へ
関連記事
-

死刑になる罪はどのようなものがある?日本の刑法上では12種類
この記事で分かること 日本で最も重い刑罰である「死刑」「死刑」が宣告される罪は少ない反...
-

量刑とは?刑の重さはどう決まる?量刑に影響する要素について解説
この記事で分かること 量刑とは法定刑と処断刑、宣告刑の違い量刑の決め方量刑を決めるとき...
-

この記事で分かること 銃刀法違反とは~銃刀法の目的と内容銃刀法の内容銃刀法違反の基準~...
-

軽犯罪法違反とは?罪に問われる可能性のあるケースと処分・罰則の内容
この記事で分かること 軽犯罪法違反とはどんな罪なのか軽犯罪法違反に問われる可能性のある...
-
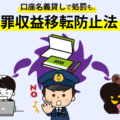
銀行口座を貸してしまったらどうなる?「犯罪収益移転防止法」トラブル例
この記事で分かること 口座の売買は違法!犯罪収益移転防止法違反になる犯罪収益移転防止法...
-

この記事で分かること 「殺人」に関係する犯罪の定義「殺人未遂」に問われる行為とは?他人...
-

この記事で分かること 窃盗罪とは?どんな罪?「窃盗」と「強盗」の違い「窃盗罪」における...
-

この記事で分かること 性犯罪における「わいせつ」とは?「公然わいせつ罪」とは「公然わい...
-

詐欺罪とは?詐欺罪で逮捕された場合の流れと弁護士へ相談するメリットについて解説
この記事で分かること 詐欺罪とは?刑法における定義詐欺の手口の種類「詐欺罪」の立件は難...
-

この記事で分かること 食い逃げは「詐欺罪」に問われる?「詐欺罪」の定義と刑罰は?食い逃...